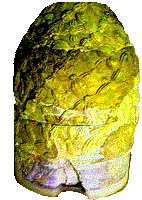�@�@�@���������ʍ��̃t�B�W�J
�@�@�@�R�g�^�}�̊�Ƃ��Ă�
�@�@�@ �g���������
�@
�@ �@�@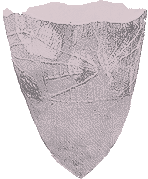 �@�@�@�@
�@
�@�@�@�@
�@
�@�ꕶ�̓�ڕ��l�́A�\�ۂ��������Ă����ł��邪�A����������̒q�d�́A�C���[�W��\�ۂ��������邱�ƂŁA�p���Ă���̂܂܂̐��E����e�ł��邱�Ƃ��d���Ă���.�B���܂ɂ����A�����Ă���킽���������̂��Ƃ̖@�̊j�S���A�����ɑ����Ă���B
�@��C���[�W�͂��܂����N�O�̓ꕶ�����̔g��������y��ł���B���̂͂邩�ȑO�̑��n���̊���A�����āA���̌�̒����Ή�����ӊ��̓y��ɂ�����܂ŁA�v�ꖜ�N�ȏ�ɂ��킽���āA�����̊�͒��ۉ����^�u�[�Ƃ���K�͂̂��ƂɁA�`�ʂƂ������̂��������Â��Ă����B�O�������E����̑��ւƒ��ۊҌ����Ȃ������B�����ɂ́A�h�u���v��Ώۉ����������Ƃ͂��ʁh�Ƃ�����j���㌾�ꐸ�_�̐x���ӎv�����Ď���B���̋K�͂́A�L�I���t�̕�������ɂȂ��Ă��u���������ʁv�Ƃ������Ƃɂ݂���s�����Ƃ��Ă͂��炫�A����Ɍ���ɂ������Ă���炵�̂Ȃ��̖{���̕�����A�Љ�̐[�w�S���ɂ܂ŋ����͂��炫�����Ă���B
�@ �@�@�`����҈��V��
�@ �@�@�`�����҈��V��
�@�@�@�@�@�@�@- �Ռo�E�q����`
�@
����A���V�i�C���͂����A�����̊�́A�g��������킩��݂�ƁA��������l�A�ܐ�N�قǎ��オ���邪�A�u���v���Ƃ��đΏۉ����A���̐����𒊏o����Ƃ������ۉ���Ƃɂ����āA�͂��߂Ē��o�����Ƃ���̐����l���B�����A�v�z�ɂ����Ă�B.C.1700�N���̒����ł́A�E�ɂ��������Ռo�E�q����`��\��͂ɂ݂��邲�Ƃ��A�u�`����҈��V��
�@�`�����҈��V��i�`����҂Ƃ́A����ƈ����A�`�����҂Ƃ́A�������ƈ����j�v�Ƃ���A�z�����ɂ��ƂÂ������E�̍��x�Ȓ��ۗ��_�̑̌n�����i�s�����B���̒��ۓI�����ɓK�������^���̊l���ƁA���ێv�l�𗼗ւƂ��āA�\���͋ɓx�Ƀ\�t�B�X�g�P�C�g����Ă���B
�@ �i�q����`���Ռo�ɒlj����ꂽ�͍̂E�q�̎��ゾ���A���̎v�z�̊�b�͂��łɟu������ɂ������Ƃ����Ă���j�����ŁA�u��v�̑��ݍ����́A���ۊT�O�ł���Ƃ���́u���i�^�I�j�v�Ƃ���A���̗��_�̐[���ƃp�������Ȃ������ŁA�u���̐���̕��l�̒��ۉ��͂����܂������W���A�V�̈Ќ�����e���鐹�Ȃ�Պ�Ƃ��āA�S�C���鋰��ׂ����̂ɂ܂Ő[�����Ă����B�����ߖ�̊w���l�A�b�ʕ��܂����b�W�i�g�E�e�c�j���̂悤�Ȓ��ە��l�́A�A�z�F���̐�ΐ��̍��݂ɂ܂ŕ\������āA�����ɗ�����҂��Њd���A���|���s�����B
���Ռo�E�q����`�ɂ������̊T�O�́A�L�`�ł́A�V����̉A�z�̓����������邷�ׂĂ̂������݂���̂��w���B���Ȃ킿�A�`�����Ƃ��Ă̕��ł���B�����鑶�݂̍����ł���`�̂Ȃ��`����Ƃ��Ă̓��i�^�I�j�ɑ��āA��̓I�ȏۂ��������鑶�ݕ����Ӗ������B���`�̍Պ�Ƃ��Ă̊�݂̂Ȃ炸�A�l�Ԃ��܂߁A�n��ɑ��݂��錻�ۖʂɂ����Ĕc���������邷�ׂĂ̌`�ۂ���ł������B
�������̌��`�ɂ������Ƃ��������́A������p���Đ��߂��Պ���`�ۂ������̂��B�l�̌��̂������ɂ͂��܂ꂽ��̎��́A�{���̈ӂ͌����ɂ���̂ŁA�����������B-
�u�����v����Â�蔲���B���悤�Ɋ�͓V����̉A�z�̓����������A�܂育�Ƃ��s���A���̂����Ȃ��_���Ȃ��̂ł������B����䂦��𐧂���҂́A���̏ۂ����i�����Ɓj�Ԑ��l�ł���Ƃ��ꂽ�B
�@���_
�v�z�𖾂ɂ�������
�@
�Ռo�⊿���ɂ������ɐ������݂��{�I�Ȉʒu�Â��́A��炵�̂Ȃ��Ɉʒu�Â���ꂽ���i���悢���{�̊�ɂ����Ă��A��Ƃ������̂̌Ñ�ɂ�����d�v�����l�����Ă݂�ƁA������͂���Ȃ铹��݂ɂƂǂ܂炷�A���Ȃ鐫�i��ттĂ������낤���Ƃ́A�z���ɓ�Ȃ��B�����̔g������⒆���̉Ή����y��Ȃǂ̌`�Ԃ��݂�A����炪�����ɓ���݂Ƃ��Ă̋@�\����E���A�Ȃ�炩�̐��_�I�ȈӖ���S���Ă����ł��낤���Ƃ͖��炩���B����䂦�A���̐���ɂ͂��炭�v�z��ǂݎ�鎎�݂́A�����A���Y���_�����̋Ïk�����j���{��p���e�m���_�a�̐v�v�z�ɂ�����A���p�I���_���瓖���̌��ꐸ�_�̐[�w�\�����𖾂��悤�Ƃ����ƂƂ܂������������Ƃł���A�������炱�̗̌��ꐸ�_�̂͂��炫���\�S�ɋ��ݎ�邱�Ƃ��\�ƂȂ낤�B
�@
�������A���̉𖾂͓��ɂ����Ă͌Îj�Ó`�ȂǗ���ׂ������������Ȃ�����ł���A�܂�������Ƃ��ĉ��p�\�Ȋ����ɂ��L�q������Ȃ��a.�b�ꐢ�I�ȑO�̖퐶���炻��ȑO�̐V�Ί펞�オ�ΏۂƂȂ�B�����ɌÓT�w�⌾��w�A�����w�A���j�w���X�̏]���Љ�Ȋw�n�l���w�̌��E�������Ă���B�B��A�Ȋw�I���ؐ��ɂ���Č����\�Ȏ��R�Ȋw�n�Ɛl���Ȋw�n�̒��ԂɈʒu����l�Êw�Ɋ��҂�������Ƃ��낾�B�������A���R�Ȋw�I���@�ŔN������߁A�������ɑw�ʊw�ƌ^���w��g���������������ő��ΔN������߂邱�Ƃ͂ł��Ă��A�����ɂ������l�X�̐����E�����E�Љ�̂��肳�܂܂Ŗ��炩�Ƃ��铥�ݍ������͍���ł���B�܂��ē����̊������ЂƂтƂ̐S���̊j�ɂ܂Ŕ��邱�Ƃ͑z������ق��Ȃ��A�w��Ƃ��Ă̌����ȍ���͂ł��Ȃ��B��j�Ƃ͂����A���������ɂ���ЂƂтƂ̕�炵��l�����Ȃ̂ł��邪�A�O���������ƕ��������ȍ~�̎Љ�Ƃ̊Ԃɂ͂��̂悤�Ȋw��𖾏�̕s�A��������������Ă���B
�@
��������\�N�̂���A�����Y�̒n���w�I�ȗv�ƂȂ��Ă���|�C���g��K�ꂽ���̂��Ƃł���B���̂�����͌Õ����₽�瑽���̂����A����ȋu�̂ЂƂɗ������Ƃ��A�ꕶ��������ӊ��ɂ����Ă̓y��j�Ђ������ɎU������˂����łЂƂ�فX�Ɣ��d�������邨������̎p�ɂł������B�����ƁA���̂������܂ŁA�c�ɂ̂�����Ƃ���̂��炵�̂Ȃ��ɂ��̂悤�ȓy��j�Ђ��܂��ꂱ���i���������ł��낤�B�킽���������̐S����Љ�̂��肩�����l����Ƃ��A�����������Ђ����܂Ɉ₷�ꕶ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̓q�g�̂��Ȃ������͂邩�ȋ�������ł͂Ȃ��B�����̎g�p�̗L���Ƃ����ǂ�����ɂ��Ă��A�ꉹ�ߐg�̌��ߓ����A���A�Ăɂ��͂Ȃnj��݂ƂقƂ�ǂ����ʌ���������ЂƂтƂ��邵�Ă����͂��̂��ׂ̎���ł���B
�@
���̊w��𖾏�̕s�A�������z���āA���ɂ��Ǝ����ꐸ�_�̂͂��炫�������g�p�̑O�ƌ�łǂ��ω������̂��A�܂����҂̌��ꐸ�_�ɋ��ʂ̂��̂�����Ƃ���A�����ɂ͂��炢���@�Ƃ͉������T�������K�v������B�S��ɂ��ꂾ���Ȃ܂Ȃ܂������Ղ��ɂ̂����Ă���ꕶ�����ł���B���̖���������̎��_���𖾂��A��j�Ƃ��鎞�㐸�_���猻��̈Ӗ������߂Ȃ��ẮA�������������œ�����Ñ㐸�_�̕��͂���Ñ�⌻����Ȃ��߂Ă��Ў藎���̊ς͔ۂ߂Ȃ��B
�@
���̂ւ�͊e�����@�ւł��ӎ�����Ă��āA��r�l�ފw�A��r�����w�A����w���̊w�ۓI�ȑ������ł��������z���悤�Ƃ��������͂łĂ���B�������A���ۏ�́A���O�Ƃ͗����ɁA���ꂼ��̊w��̋���ׂ����ꂪ���m�ɂȂ��Ă���ƁA���̊Ԃ̃M���b�v�͂Ђ낪�����ƂȂ�B�p��ЂƂ�ɂƂ��Ă��A�w�ۊԂŋ��ʂɒ�܂������̂��Ȃ��̂�����ł��낤�B���̕s�A�������A�]���w��̕��@��A���Ăɐ^���Ă͂��܂����w�ۓI�Ȏ��݂Ȃǂŏ��z������Ƃ̔M�ӂ́A���ĂɗR�����邻���w��̊�Ղ��̂��̂�����Ȃ�������A���������Č���_�b�̂ЂƂ��炢�͑n��Ă��A���ǖ��ʂȓw�͂ɏI���\���������B
�@
�𖾂̕��@
�@
�����ŁA�����ł͖���������ƕ�������Ƃ̊Ԃɂ��邱�̕s�A�����ɑ��āA�]���̉��Č^�w��̎��ؓI���@�_����͂�������͂Ȃ�āA���ɂ��Ȃ��@�ɏ]���A�u���v�ւƒ�������A�u���v�ɓY���āu���v���J���Ă������Ǝ��̎v���̕��@�ŗՂ݂����B�����ł́A����ΏۂƂ��ĔF������̂ł͂Ȃ��A���֏o��Ƃ����F���ɑ�ւ��m�F�̕��@���̂�B��̓I�ɂ͂���́A������p�̎���ɂ��̌��I�ŁA�����������I���_����ςĂ������ƂɂȂ�B��������A���̃M���b�v�ֈ�{�̊������������ꎩ�̂��L���Ӗ��ł̌�����p��i�̂ЂƂ̍�Ƒ̂Ƃ��ĉ˂��킽�����݂ƂȂ�B���Ƃ��`�ʕ\�����킴�Ɖ�������悤�ɂ݂���ꕶ�Ƃ�������������̐��_�́A�\���`�ʂɂ������Ȃ����ۉ����̂��̂̃v���Z�X���^�u�[�Ƃ��Ă����̂ł���A���̐���́A�̏ۂ���ђ��ۉ��ɂ���Ă��̖{����������߂āA��������g�ݗ��Ă����_�𒀈ꒁ���悭�؋����ĂĂ������Ƃ���w����e�����E������ނ̂��̂ł���B���������ď]���w��̑Ώۂɂ͓���܂Ȃ��Ƃ��낪���낤�B���̓Ǝ����́A���ꎩ�g�ɂ����āA���ꎩ�g�ɔ�������Ǝ��_���ō�Ƃ��Ă͂��߂Ă��̓����̔閧�ւƔ��邱�Ƃ��ł���B
�@
�q�ςł���ׂ���Ƃ��w��ɂ����āA�|�p�ʼn𖾂���ȂǂƂ��������ƁA�������ɍ��f���������������Ȃ낤�B����̏펯����͓��R�ł���B�������A���̌��������ʍ��̎v�z�N���͗��j�I�ɂ݂Ă��A���ۊT�O�����������ĊT�O��_���I�ɐςݏグ�Ă��������^�w��̂悤�ȃV�X�e�}�e�B�b�N�Ȏv�z�\���̂��������Ƃ��Ă��Ȃ������B������c�ɑ�\�����D��č\�z�I�ȓN�w�v�z�����邪�A�����͂����܂ŎR���A��a�G�A�\�y�A�����A���{��A�m��̂悤�ɁA��x�E�����E���Ď��w��E�|�p�����łȂ������̂�A���A��e���A���{�I�[���ɐ����������̂ł���A�`���͊w��̂悤�ɂ݂��Ă��A���e�͈�E���E���̂悤�Ȍ����Ȋw�̑̌n���Ȃ��Ă��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ́A���҂��炵���Ύw�E�����Ƃ���ł���B�����Ė��́A����炪�ʂ����ĕ��̂���������o�I�ɂЂ������āA�����j�ɁA�Ǝ����W�����Ă������̍��ŗL�̊w��E�|�p�������̂��낤���Ƃ����Ƃ���ɂ���B
�@
����ɑ��āA�l���C�E�m�Ԃɑ�\�����a�́A�o�~�ɂ����ẮA���������̌`���͓��̂��ӎ��������̂ł����Ă��A��{�I�ɂ͕�ꌾ�ꐸ�_�̂���������o�I�ɓ��I�Ȏp�ő����A���ꎩ�̂̉^���ł������v�z�ɂ܂ŏ������Ă���B���̈Ӗ��ŁA�_�����^�����A�u���̍��ɂ�����a�̂́A���y�̎��o�Ɉʒu�Â��������̂ł���v�Ƃ����Ă��邪�A�a�́A�o�~�́A���|�Ƃ�����W�������̎���i�ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ��A���̈��E��傻�̂��̂����ɂ�銈�����܂܂̓��I�ȓN�w�v�z�ƌĂׂ���̂Ȃ̂ł���B�����A�v�z���������̂Ɛ�������Ƃ̂������́u�����_�̎����ʂ̐S���v�ƑO�����āA�C���h�_���w���̂ɂ����u�ނ�_�̐₦�Ԃ̂����͋}���ǂ��ӂ���͂������H�̖�̌��i-����W)�v�Ɖr�ލs�ׂɂ����f����Ă���A�܂��A�u�̂͐��������@���̂��̂ł������B���ꂪ���b�̂����S�ł���B�i�������̎w�E�j�v�B���X�A�̌��ꐸ�_�ɂ��ƂÂ����_���E�w����A��ꌾ�ꐸ�_�ւƁA�����ɂ͂��炭�@����������Ă���͂��̉̂Ƃ����|�p�`���ւƒu�������悤�Ƃ��鎎�݂́A�킽�����������ꐸ�_�̂ЂƂ̓Ǝ��Ƃ������ׂ����R�ȌX���ł������B
�@ �ȉ��̍�Ƃ̂Ȃ��ŁA���X�Ɍ����ɂ��Ă������肾���A���̗̌��ꐸ�_�ɂ��v���̂��肩���Ƃ������̂́A��E���E���̌��ꐸ�_�ɂ��v���Ƃ́A���̕���������e�E���@�_���܂���������Ă���B���������Ă����ɓ������Ԃ��Ԃ��قȂ��Ă���B�^���Ƃ�����{�I�ȊT�O�̈Ӗ�����Ƃ��낳�������ł͂Ȃ��B
�@
����͌|�p���g�ɂ��Ă�������B���m�̂悤�ɁA���̍��̌|�p�̖��ł����i�̂قƂ�ǂ́A��x�E�����E���Ď��|�p������A���A��e���A���{������Ă������̂��B�������A���I�Őg�̂��Ƃ�������ꐸ�_�̎������玩���I�ɒB�����ꂽ��i������B����ȍ�i�ɑ��ẮA��E���E���̌��ꐸ�_�ɂ��v���͓K�p���Â炢�B��{�I�ɕ�ꌾ�ꐸ�_�̂����������ē��I�Ȏp�̂܂ܑ����A�A�́E�A��̂悤�Ɋς鑤�����ꎩ�̂̉^���ƈ�̉����ĎQ���A�������Ȃ���A�[�������ɂ܂ł��ǂ蒅�����Ƃ͓���Ȃ�B���Ƃ��Ό�����p�̋�̉^������*���m�h�̐��؎u�Y�◛�Z���ɂ݂����A�̍�i�Q�������ł���B�B���������x���́A���ۓI�ɂ݂Ă��A������̉��ă~�j�}����A�[�g��A���{�̌���v�z�Ƃ̘_���`���̍�i���x�����͂邩�ɗ��킵�����̂ł���A�]�����w���]�̑Ώی��O�Ɉʒu���Ă���B�������A���̐��ʂ����Ƃ����ꌾ�ꐸ�_���z�������E�ł����ڂ����ߓ�������́A�܂��A��Ƒ����A���E�I�|�X�g���_���̗���������āA����܂ł̈��Ă̒��ۊT�O�ɂ܂��f�킵������̓`�����^�T�O���P�����Ƃ���ō�Ƃł����Ƃ����A���������Ƃ������̂�ɂ��āA�u�����I�u�W�F�N�g�Ƃ��ĂƂ炦�邩���Ƃ��ĂƂ炦�邩�v�Ƃ������̖{���I�Ȓn������̖₢�����ƂƂ��ɂ����炵���͂��߂邱�Ƃ��ł����Ƃ����A�����ɂ��̎���̃W�������̒u���ꂽ�����ʒu�̍K�^���ɂ������B����Ȋ����̓`�����^�T�O��j������i���]�������߂Ă����̂��B
�@
�Ƃ���ŁA�����Ȃ鎞��ł��낤�ƁA�w����|�p�����̊�Ղ́A���܂Ƃ��������݂Ƃ̐g�̂��܂߂��i���̏�Ȃ����Đ��������Ȃ��B����́A���Č��ꐸ�_�ɂ���m���E�������ŋߑ�w��̕��@�_��ł����Ă��}�b�N�X�E���F�[�o�[�ł����u�w���A�슴�����邽�߂ɂ������̎����iEine
Sache�j�ɐ�S���邱�Ƃ��K�v�ł���v�Ɗw��ɐ旧���āA�������E�ƕs���s���̊W�Ő������钼���̕K�v���Ɍ��y���Ă��邱�Ƃ�����M���悤�B�Ƃ�킯���̊w��̕��@�_��\�ʏ�Ŏ�e���Ă��������̂��̍��ɂ����āA�ߑ�w��̕��@�͐^���ł��Ă��A����ݏo�����������ꐸ�_���̂��̂͑̌��ł����A���̒��ł̃g���[�X�����ł��Ȃ��B�����̋����ė���Ȃ��A�����āA���Ƃ������t�̃`�J���̎菕���œƎ����_�ƓƎ����@�_�������Ȃ��ẮA�w��Ȃv�Z���Ƃł����Ȃ����낤�B
�@
�u���������ʁv�Ƃ������ꐸ�_����݂��ꍇ�A���ēN�w�ɓ�������̂Ƃ��ẮA���̍��Ǝ��̎v�z�E�N�w�Ƃ������̂́A����ƂƂ��ɕ\�����f�B�A��ς��Ă��Ă���B�ꕶ�ł͓ꕶ�A���̌�͘a�́A�A�́E�A��A�o�~�B�����Č��݁E�E�E�̏��ɁB
����A�����ȍ~�̓N�w�E���w�ƌĂ�Ă�����̂́A���Ԃ͂��܂ł������ߏ������̗A���p�b�P�[�W�\�t�g���i�ɂ����Ȃ��B�o�O�̑����ɂ��S�炸�A���܂��A�ق��ڂ����ʂ��Ă���̂��݂�ƁA���܂��ƊE���ŁA����̎v�l��~�����p�ɂ���Č떂�������ƂŋƊE��������}���Ƃ���Ӑ}�̂��ƁA���Еt����A�A���o�C���ɗ��p����Ă���悤���B��ꌾ�ꐸ�_�ւ̎��o�����@�����܂܉��ēN�w�E���w�̒���T�O����ʼn^�p�\������Ƃ���������Ƃ����܂܂̂���珤�ނ́A�N�w�E�v�z�Ə��i�������Ă��Ă��A���̍��Ǝ��̊m�ł���v�z�E�N�w�Ƃ͉��̂Ȃ����̂ł���B
������m�h�Ƃ́A1970�N��O��̓��{�ŁA�|�p�\���̕���ɖ����H�̎��R�I�ȕ�������́i��������m��ƋL���j���A�f�ނƂ��ĂłȂ�����Ƃ��ēo�ꂳ���A���m�݂̍�悤����̂̓������璼���ɉ��炩�̌|�p����������o�����Ǝ��݂���Q�̍�Ƃ������w���B�i��
�؎u�Y�A���Z���A�֍��L�v�A�g�c���N�A�{�c�^��A���c���F�A������ �Q�A�|�q�N��A���R�o�A���䔎�A�H���^�A�����T�V�A���j�E�E�E���̓��m�̑��݂̌�����Ƃ��ďA�C�x���g�Ȃǂ������o�������Ă䂫�A�Ƃ�킯�A���m�Ƌ�Ԃ̗��`�I�Ȑړ_�Ƃ��āu�ʁv�Ȃ����u�E�v�ɒ��ڂ��A�ʂ̕\�Ɨ��A�E�̂�����Ƃ�����Ƃ������ʑ��]�����˂Ƃ��ċ�Ԃ̕��߁A���݂̑����I�������\�ɂ������@�̌n�́A�܂������Ƒn�I�Ȃ��̂ł������B���̍�i�ɂ͂˂Ɂu���ɂ���ă��m�͍݂邩�v�A�u���ɂ���Ď������͂��������̂��v�Ƃ����ݖ�i���N���j�����݂��Ă���B�������A�����ݖ���A�W���X�p�[��W���[���Y����m��`�I�ŊA�a�ȃ^�u���[��I�u�W�F�ɕ����߂Ă����̂ƈ���āA���͂�����A���m�Ƌ�Ԃɉ����āA�����Ƃ̋Y��ƂƂ��ɁA���̓I����_�I�ȉ������ʼn����Ă������B���݂ւ̖₢�̓����́A���m�ɂ���i�ɂ��T�O�ɂ�����킯���Ȃ��A���m���Ԃ߂���q�g�Ƃ��̃q�g�̐U�������K�肵�Ă��郂�m�̍\���Ƃ̈ˑ��������Y��i����͊W�Ƃ����ÓI�T�O�ł͑������Ȃ��j�̂Ȃ��ɂ����Ȃ����Ƃ��A���͍�i���̂ɂ���Ď����̂ł���B���ɂ����āA���m�h�͐^�ɓ��̂��ƕ]���Ă����B�v-
1986�N���q��L�s���m�h�t�W�J�^���O/���p�]�_�� �����q�����_�������p�B
�@
��Ƃɂ�����O�̗��ӓ_
�@
���_�́A�܂��A�ߑ���w�̑��^���_��]���̒�������ⓩ����̊Ӓ��́A�������ʂɂ���邱�ƁB���ہA����Ȃ鑢�`���̍��۔�r�ȂǂŊO�ʓI�ȓ������������A���_�Ǝ���������ςݏd�˂悤���A���̔�r��������፷�����̂��A�ߑ㎩�R�E�Љ�Ȋw�̂��̂ł������A�]�����w��A�T�O�A�_���v�l���݂͂������Ƃ��납�琶�ݏo���ꂽ�A���̐���̔��̓�͌�����A�ǂ݉������Ȃ��B
�@
���_�́A���������āA���̊�́u���v�Ƃ��āA�u���v�Ƃ��č݂邠�肩�����A�^�I�I�ȗ��@�ł͂Ȃ��A�܂����Ă̊T�O�v�l�ł͂Ȃ��A�킽���������̌Ñw�ɂ͂��炭�u���i���Ɓj�v�̂��������āu���v�ɂ����ĒǑ̌����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B����������̌��ꐸ�_�ɂ������������œǂ݉����K�v������̂��B
�@
�Ȃɂ�����������邪�A��܂ƌ��t�́A�����ނ˖퐶����ɒ蒅�����Ƃ����A���̂قƂ�ǂ͌��݂��g�p����Ă���B���Ƃ��A���̌�̌�������ɂ����āA���̗p��╶�@�ɂ͌��݂܂ł������ȕω��͂Ȃ��A�h��⏕�����Ɋ����ΊT�ˏ��E���w���ł��lj��\�ł���B���̂�܂Ƃ��Ƃ̂���ɌÑw�Ɉʒu�Â������A�āE�ɁE���E�͂̏����A�n���A�g�̌�A�ߓ����A���A�[����Ƃ�������Q�́A�퐶�ȑO�ɂ܂ők���ɈႢ�Ȃ��A���̑啔�������܂Ɍp������Ă���B�܂�A�u���i���Ɓj�v�́A���̂܂ܗc�����炨�N���A������*�i���X�}�V���܂ł�����Ŗ��ӎ����Ɏg�p���Ă��鎄�����̌����g�̉����ꂽ���ƂȂ̂ł���B
�@
�v���Ƃ������̂����Ƃɂ���Đ[�߂�����̂ł������ɂ����āA���̂�����̎菕���Ȃ����ẮA�Ȃɂ��ł��Ȃ��̂͂����炩�ł���B������ɗ́A�����Ƃ����u���Â̎���㉁i�����j�����Ă��邵�Ƃ��鍑-(�^��)�v�̌��ꐸ�_���G�����̈Ӗ����痣��āA�u㉁i�����j������������v���ꐸ�_�����̈����̊��o�̗Z�ʐ���ސ��I�ɍL����Ӗ��̈�̂Ђ낪��̂Ȃ��̌����̂Ђт����Ђɐ[���������肽���B���ꂪ���̍��̎v���̕��@�Ȃ̂ł���B�������ĕ��ɒ�������A�N�������u���i���Ɓj�v�̌Ñw���猻��̎v�l���ł͋y�т����Ȃ��������́A�������ȃ`�J�����䂫�������Ƃ��\�ƂȂ�B�u���Ƃ̈ꉹ�ꉹ�́A�㓪�ɐ�x�]�����ׂ��v�Ɣm�Ԃ������悤�ɁE�E�E�B
�@
��O�_�́A�Ñw�ɂ͂��炭�u���i���Ɓj�v�̂��������āu���v�ɂ����ĒǑ̌����Ă����ۂɁA�含�I���f�ɂ��ׂĂ̐M��u���Ȃ����Ƃł���B�؋��݂̂ŁA�S�̂f���Ȃ����Ƃł���B���ɂ��Ă����̐��E�ɂ����Ă��A�݂̂��炻�ꎩ�̂����݂����킯�ł͂Ȃ��B��������A�����݂��̂��̂̋����̓��e�܂ʼn�㈂��邱�Ƃ͕s�\���낤�B�܂��āA�S���̊j����ɂ��Ă����Ƃ��͂����ł���B�������A���g���Ȃ݂Ă����X�ɂ��āA���̃g���b�v�ɂ͂܂��āA�v�l��~��ԂɊׂ��Ă��܂����Ƃ������B�����������Ƃ��Ă��A�ꌹ�I�����̖����g���Ɋׂ�Ȃ����Ƃł���B�܌������悤�Ɂu�ꌹ�Ƃ������̂́A���ł����Ƃ�����v�B�ꌹ���߂�ׂ����؋����Ă��ꍇ�ɂ���Ă͕K�v�ƂȂ�̂͊ԈႢ�Ȃ��B�������A����͑��̋@��ɏ��낤�B�����ł͏ڍׂȌ含���f�ł͂Ȃ��A�g�̂�}��ɒ���������̌��q�Ɏ�����u������Ƃ����Ă����B����ŕ�����͕̂���B����Ȃ����̂͂���ȏ�含�Œǂ������܂킳���ɁA�ł������Ă������������Ă�����̂ł��낤�B
�@�{�_
�u�����Ȍ�A�����Ȋw�₪�h�������A���Ɩ{���ɍ��𐘂�āA���{�I�ɁA�Ñ㐸�_�̋N�ė���Ƃ�����������āA�Ñ�̘_����q�˂ė���K�v������B�v�@-
�܌�
�@ �g���������B
�@ - ���̊�ɂ͂��炭�O�̖@�B
�@�@�@�@��A
���̊�ɂ͂��炭�@�̊j�S�́A�L�I���t�ɂ܂ł��p������A�l���C�������̒����Ɣ�r���āA�u���������ʍ��v�Ɖr���̌��������ʋ֊��@�ɂ���B
�@
����́A�T�O���ɂ��̏ہA���ۉ���r���āA�������ɂȂ��钊�ۗ��_�̍\�z�����ۂ��A�����镨������̂܂܌����������A���I�ȋP���̂܂܂Ɏ�e���Ă������Ƃ���_���ł���B����Ώۉ����Ȃ����ƂŁA���ƈ�̉����ʂ����A��������Ђ炢�Ă���S���I�����Ƃ������̂ɁA�[����������A���܂����邢�̂��̉ʂĂ܂ł��A������Ȃ��[���^���Ă������Ƃ���v���ԓx�̂�����ł���B
�@���̂킽���������̂����ЁE�v���̂�����Ƃ������̂́A���Č^���ꐸ�_�ɂ�钊�ۊT�O�Ř_�����\�����Ă����v�l�@�Ƃ́A�܂������قȂ������̂ł���B���҂́A���̂܂܂ł͑��e�ꂸ�A�^��������Η����邩�A�������Ă��܂����̂̑��������B�����A���̎v�l�̂͂��炫���̍��{�I�ȈႢ���킽���������́A���قǎ��o���邱�Ƃ͂Ȃ��B��ʓI�ȓ��퐶���ɂ����ẮA���̂��Ƃ����ڂȂ�炩�̎x��ɂȂ邱�Ƃ����Ȃ����炾�낤�B�������A�ȉ��ň����悤�ɁA���̌��ꐸ�_�ɔ�����v�l�̈Ⴂ�̎��o���@�Ƃ������̂͂��ꂾ���ōς܂Ȃ��B���ɔ䌨������̂���������Ȃ��قǂ������Ȕߌ��ɂȂ������s��ł���̂��B
�@
������p�⌻�㕑���̌���ɂ��ƁA�����̈Ⴂ����i��g�̏�ɔ@���Ɍ���ɂȂ��Ă��鎖�����̓I�ɖڌ��ł���̂ł��邪�A�����ł́A���܂�G��Ȃ����A���ꐸ�_�����ڂ�������Ă���V�`���G�[�V�����ɐg�������ĂȂɂ��n�肾�����Ƃ����Ƃ��ɂ́A���Ȃ炸�A���Č^���ꐸ�_�ƕ�ꐸ�_�Ƃ̎v�l�@�̈Ⴂ�ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�B�������A���ꂪ�U���`�����w�⌤���_���Ƃ������ꎩ�̂̍�i�ƂȂ�ƁA�o���Z�̂Ƃ����`�����`�͕ʂƂ��āA�u�g�́v��A�u���́v�ł݂��Ă������̔@���ȍ��ق́A�������ĕ������Ȃ��Ă��܂��B���Ƃ̓����Ӗ��E�T�O�Ƃ������̂�跗�����Ă��܂����炾�B���Ƃ�IT�ɑ�\����錻��́A�قȂ錾��V�X�e���Ԃł́A�����I�����̊ϓ_���炱�Ƃ��W�R�I�ɑΔ䂳���āA�����ł��܂��悤�Ƃ���X�������܂��Ă��Ă���B����A�|��^�哱�Ƃ����ׂ����Ƃ̎���ł���B�����ł͉��Č^�ƕ�ꌾ�ꐸ�_�Ƃ̎v�l�@�̈Ⴂ�͂��͂⑶�݂��Ȃ����A�䂭�䂭�͏��z������ׂ����̂��炢�ɂ����~�߂��Ă��Ȃ��B
�@����ȃP�[�X�������āA���Ďv�l�@�Ƃ̂��̌���I���ق����o���邱�ƂȂ��A���݁A�����X�^�C���ɂ��Ă��A�Ȋw�Z�p�ɂ��Ă��A���ꂾ�����ĉ������킽���������ł���B�������A�ˑR�A�����ŁA�ꕶ���\�����Ƃ��ĂƂ肠�������̔g���������ɂ͂��炭�@�́A��ꐸ�_�̐��ł���a�́E�o�~�����āA���܁A���m�h�║���ɂ����錻����p�̊j�S��A�ЂƂ�ЂƂ�̐����̖{���̕����ɂ܂ŁA�ꖜ�N�ȏ�ɂ��킽���Ĉ�т��Ă͂��炫�Â��Ă���̂ł���B
�@����̑�\�I���t�w�҂̂ЂƂ�A�����i�͂����u
�Ñ�ł́A�l�Ǝ��R�Ƃ𑊑Ή����đ�����ӎ����Ȃ������B�l�Ǝ��R���Ђ�����߂āA�����ɂ���R�A�������ɂ����A�����Ď��B�����������̂̂Ƃ��đ����Ă����B�v�ƁB�������A���܂̌ÓT�����Ƃ��ق��Ă���͂��̔ނ̐��@����Ñ�l�̂��̂̌����́A�Ñ�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ����낤�B�T�����i�����ĐK���𗎂Ƃ��A�q�g�ɂȂ����Ƃ���i���_�҂��咣�̂悤�ɁA�킽���������́A�Ñ�̎v�l�@�Ƃ����K�����̂ĂāA���������ĉ��Ă̐i���I�v�z�ւƐi�����Ă������낤���B�������ɁA�������ɉ��l��u������̂��̂̐��E�ł́A������A������d�C����@�ɕς�����悤�ɁA�Z���Ԃɓꕶ�y�킪�퐶�y��ɂƂ��Ċ����Ƃ������I�ω��͂�������B�������A���Ƃ̐��E�ł͖����������������ւ�鎖�Ԃł��Ȃ�������A���ɂ�錾�ꐸ�_�����ς�����i��������͂��邱�Ƃ͂Ȃ��̂��B����̐���������̓d�C����@����������炸�A���ꌾ������铯��l�����g���Ă���B
�@
�l�Ǝ��R�Ƃ𑊑Ή����Ȃ��Ŏ~�߂Ă����킽���������̂����Ђ̘_���́A�Ñォ�炩��炸�A�������ʂ̖{���ł��炷���{�l�̂��̂̌����ł���B�������A�g�ӂ̂��̂��������A���Č^�̐����l���ƂȂ��ċv��������̂킽���������́A����ŁA����̎Љ�E�o�ϊ����ł͐����^�ɖ|�ӂ��ꂽ���̃t�B�N�V�������E�ɐg��u���āA���̂�Ώۉ����Ȃ��璊�ۊT�O�v�l�i���Ă̂悤�Ȍ����ȊT�O�v�l�ł͂Ȃ��j���ǂ������āA�����ł́A�d�����痣�ꂽ�ƒ��A�ЂƂ�ɂȂ������̖{���̐��E�ɂ����āA���ɂ�錾�ꐸ�_�Ɋ҂�A���̂�Ώۉ������A���Ή������A�����Ő��܂ꂾ�����̂Ƃ��Ă̎����̂Ђ炫�֗^���邩�����ł��̂��Ƃ⎩�Ȃ֑Ώ��������Ƃ������Ђ��Ђ炢�Ă����B
�@
�u���@�A�ڃH�b�Ƃ��Ă��E�E�E�B�v
�Ȃǂ����킸�R�炷�Q���߂������Ƃ����������A�F����̂Ƃ��Ắu�l�ԁv�Ƃ����T�O���������������̓�E�O�S�N�O�ɔ������ꂽ�ɂ����Ȃ��Ƃ������B�g�Q���V���^�C���ł͂Ȃ����A�킽���������ɂ����ẮA����Ȑ����^�T�O�v�l�����A���̍l�������蒅���Ă܂��S�N���܂肵�������Ă��Ȃ��B��q�����Ƃł����@�\���Ȃ����ۊT�O�p��ɂ���ׂ�ƁA���̂悤�ȂȂɂ��Ȃ��Q���߂������Ƃł���Ȃ�����A���̐[�x�͐[���B�ɎדߊƈɎדߔ������u���Ȃɂ₵�A�����Ƃ����B���Ȃɂ₵�A�����Ƃ߂��v�ƌ������킵�Î��L�������Ƃ߂������݂ɂ܂��L���Ȍ��t���l�A����������̌��ꐸ�_�ɂ܂ł��ǂ��Ñw�ɑ����邱�Ƃł���A�g�̉�����Ă���䂦�ɁA�����L�̂��������A���킢�������̂Ђ낪��������Ă���B
�@
������̒ꂩ��̊�сA���邢�͔߂��݁A�{��ɂƂ��ꂽ�Ƃ��A����l�́A���m�炸�A�g�̉����ꂽ�Â����ƂΌ����Ɋ҂��Ă��܂��B���̎��A�i���X�}�V�̎��_����̒��ی���̈Ӗ��̎˒��́A���E�̕\�w�ɂƂǂ܂�ɔ����āA���ɂ��ƂÂ������̂��Ƃ́A���I�ǖʂɉ�������q�������́A���������Ē��ړI�ȈӖ��̈���������Ĉ�����Ƃ������ׂ����ɂӂ����S�̐��E�݂̍�悤���Ђ炫�o���Ă���B
�@
�킽���������͏�ɁA���̓�̈قȂ鐢�E��*�X�E�B�b�`���O�����Ȃ���邵�Ă���̂ł���B�ʂ̂Ƃ���ł��G�ꂽ���A���������̍��Ƃ��ق��������O���l���t���猩�����{�l�N�w�҂ւ̊��z������B�����̗A���N�w������h�C�c�l���C�M���X�l���������A�u���{�l�N�w�҂̏Z�܂��Ƃ͓�K���ĂɂȂ��Ă���B�킽�����Ƃ̋c�_�͊K��̗m�Ԃŗ��H���R�Ƃ����߁A�������ނ́A�������K���̏�̕����ւ���Ă͘a���ɒ��ւ��A�������������Ă܂��A�オ���Ă���B�v�ƁA������̌����́A�ނ��݂����{�l�N�w�҂̐��_�\���̗Ⴆ�ł���B
�@�������ꂪ�������邩����A�킽���������̖��ӎ����̖{���ł́A�T�O���ɂ��̏ہA���ۉ������Ȃ�����A�����\�w�̂ł����ƂƂ��A����Ώۂ��Ђ�����߂āA�����镨������̂܂ܓ��I�ȋP���̂܂܂ɒ�����e���Ă������Ƃ��邾�낤�B���ꂪ�킽���������̊�{�I�ȃ��W�b�N�t�B�[���h�Ȃ̂�����B���������������ꐸ�_�ƈ�x���ꐸ�_�Ƃ̒��ۊT�O�Ɋւ���v�l�@�̈Ⴂ�ɂ��Ă��������Ă���B�u�����l�́A���ۖ����̕\�����钊�ۊT�O�́A����o�����炻��̕��ՓI�Ӗ������𒊗����Ē��ۓI�ɍ\�����ꂽ���̂��ƍl���Ă���B�䂵�āA�C���h�l�́A���ꂼ��̌o���I�����̂����ɒ��ۓI�T�O���A���炩�̎��̓I�����̂悤�ɓ����Ă���ƍl����B�ނ�̎v�ҕ��@�́A�����邢�́A����҂̖{���́A���ꂪ�S�����A���ꂪ����Ă��镁�Ղɂق��Ȃ�Ȃʂ̂ł���B���ʁA���ۓI�Ȍ����Ƌ�̓I�Ȍ������̂Ƃ̋�ʂ��A��ʂ��ꂸ�Ɏg�p�����B���ۊϔO���A�����ɋ�̓I�Ȏ����Ƃ��ĕ\�ۂ����B���ۖ������A��̖����Ƃ��ėp������B���ۊT�O�⎞�ԓI�ȊϔO�����̐����镨�̂ł��邩�̂悤�ɕ\�ۂ����̂ł���B�v�܂��A���{��Ƃ�����ꌾ�ꐸ�_�ɂ����̂̑������ɂ��Ĉ���l�H���A�u�Ì�́A�{�����N�I�Ȃ��̂ł���V�i���C���h��Ƃ͈Ⴄ�B���݂̕��ߌ`�Ԃ�ΏۂƂ��đ����Ȃ��B���܂��܂ɕ��߂��ꂽ�����̐��E�̂Ȃ��ɂ���A�����ɐڂ��Ȃ��琶���Ȃ�����A���ꂼ�����̂��̂Ƃ��ċÌł�����{����F�߂Ȃ��B���ߌ`�Ԃ��A�o���I�����Ƃ��Č��O���Ă��Ă��A���������͂��������`�Ō���Ă��邾���ŁA�{���͂Ȃ����̂ł���A������{���͋��\�ł���Ƃ����̂��A�����̒��ς���B���֓����敧�����ݘ_�̒����I�e�[�[���Ȃ���ςł��邪�A������V���ȂǓ��m�N�w�̍ŏI�ɖڎw������n�ł���B�������Ȃ���A���傤�Ǖꍑ��ɂ����Ă͂��悤�Ȑ��҂̂悤�ȑԓx���N�ɂ��Ƃ��̂ł���B�v
�@
�������A���̎���A���ꐸ�_�Ԃɉ�����邱���v�l�@�̌���I���ق����o���邱�ƂȂ��A�Ƃ�킯���̌��͂̂ЂƂɂ������Ȃ��w�̃V�X�e���哱�ŁA�����̊��Ƃ����a�Ƃ��A�قƂ�ǂ̒��ۊT�O���肪�����ł��邪�A���ċߑ�v�l��B��̐��E��ɁA�Ђ�������̂܂ˊT�O�v�l�𐄂��i�߁A���̍����v���Ă����A�T�O�̈Ӗ�����Ƃ���Ƃ͗����ɁA���Ȃ炸��A�����̊T�O�E�_���́A�ՊE�_���}����B�����Ă������ȂȂɂ������������Ƃ��āA�����A�o�ς�@���Ȃǂ̎Љ�V�X�e���A�y�ѕ����S�ʂɂ킽��S�ʕ���������炷���낤�B
�@���̗��R�̑��́A�킽�����������A�����g�p���Ȃ�����A���̃��[�������o�������ʂ܂܁A���Č^�v�l�@�Ƃ����T�O�v�l�Ɉ���I�ɑ����Ă��܂��ƁA�C�Â��ʂ����ɕ��ɔ�����{�I�ȃ��W�b�N�t�B�[���h�̘g�݊O���Ă��܂��A�����ɋN�������ꌾ�ꐸ�_�Ƃ̘�����Ԃ��A����ȋ�����Ԃɕώ����Ă��܂�����ł���B�����Ȃ�ƁA���Ă��܂������ɂ̗Z�ʐ��͎����āA���͂��������̏C���͌������ɕ����҂����ɂȂ��Ă��܂����B���ӂ̑�O�҂��A��w�Ƃ��������Ƃ�������w���W�Ԃ��閳�m�Ȃ�����҂���ȂÂ��āA�ނ�̎�����̂��ƁA������Ԃ��Ӑ}�I�ɂ��肠���A�����˂�������Ƃ́A���Ԃ̃x�N�g�������ǂ݈Ⴆ�Ȃ���A�ȒP�Ȑ헪���[�N�ƂȂ�B�������P���Ș_���ł���B����o�����畁�ՓI�Ӗ��𒊗����Ē��ۓI�ɍ\�����ꂽ���Ă̒��ۊT�O�́A�킽�����������v������ł��钊�ۊT�O�Ƃ͈Ⴄ�̂ł���B�āE�ɁE���E�͂Ƃ������ɕ����ׂ����ۊT�O�́A���̏u�ԂɁA�T�O����T�O�̖{���ł���W�K�肪��������n�����͂��߂�B��w�⌤���@�ւ��A�����Ȃ�w��̐���ł���Ɩϑz���鑽���̋U�P�I�w�҂́A����璊�ۊT�O�Ƃ��̊W�Ԃ̘_���\�z����ʼn^�p���Ă��A���Č��ꐸ�_�Ɍނ��Ă�����ƐM���Ă���悤���B���A���̊��Ⴂ�͎Љ���N���b�V���ɓ����Ă��܂��B���ʂ��܂������ƂɂȂ��Ă����Ȃ̔ƍߐ��͒I�グ���A�w�ۓI�Ȍ������s�����Ă����ȂǂƖ��ӔC�ɚ����̂͌����Ă��邪�B
�@���́A�T�O�v�l�̕���Ƃ����ߋ��̌o�����������Ă������̂ł���B�����̋ߑ㉻�����������܂�A���̉ߒ��ŁA��ꐸ�_�Ɖ��Č��ꐸ�_�Ƃ̎v���̍��{�I���ق������܂��ɂ����܂܉��Č^�_����^���ĊT�O�v�l���^�p���Ă��������ʁA�Ō�͔s��Ŕj�]����ق��Ȃ����������E�o�ς̂���l�B�܂��A����Ɠ����Ƀp�������Ɍ��ۂ��Ă��������{�̐�O���p�j�⋞�s�w�h��M���ɂ����N�w�j�̍d�������ϔO���̂킩��₷�������𐼓c�̐��E�I���E�`���̌����ⓖ���̓��{�N�w�G���i�`�X���ɂɂ݂邩��ł���B�푈�́A�����E�o�ς̈�`�Ԃɂ������A�|�p�����͂����̔��f�ł���Ƃ��������ɗ��Ȃ�A�����炭���̔s�킪�Ȃ��Ƃ��A��ꌾ�ꐸ�_�ւ̐[�����@�̂Ȃ��܂܂ɁA�c���������������̋����I�T�O��Ԃ́A���������������ŁA�x���ꑁ����A���K�͂̕���Ɍ����������Ȃ������͂����B
�@
�Ƃ��낪�A���ɂ́A���ۗ��_�̍\�z�͋Ȍ������ɂȂ���Ƃ�����ꐸ�_�Ɖ��Ďv�l�Ƃ̍��ق̖��͒Nj������ǂ��납�A���̖��͕���Ă��܂����B�����ɂ́A�s��ɂÂ�GHQ�̐�̐�������������e�����Ă��邾�낤�B�������A���Ƃ��ƁA�钷���r�����銿�Ӂi���炲����j�̂悤�ɁA�ߐ��ȍ~�A���邢�͂���ȑO����킽�����������g�ɓ��݂��Ă��銿�Ӂi���炲����j�Ƃ������́B�����Ă�������m�Ӂi�悤������j�֔s����@�ɕϐg���Ă��܂�*�i���X�}�V�̌X�����ɂ����̉ߔ��̌��������߂���悤�Ɏv����B
�@
��w�S�����ɂ������钷�̎w�e���銿�Ӂi�J���S�R���j�̖����ɂ���ׁA���݂͂�����͂邩�ɗ����m�Ӂi�钷�ɕ���ĉ��ɁA���E�S�R���Ƃ��Ă����j�S���̎���ł���B���ĕ��������̈��|�I�ɗD�ʂȌR���́A���Z�́A�ߑ㎩�R�Ȋw����Z�p�͂�w�i�ɂ��đS���E�����|�������A������Ă̒n���I�K�͂̎��Ԃł��邪�A�ߑ㎩�R�Ȋw�ЂƂ�ɂƂ��Ă��A���̎�e�Ɖ��p�ɂ݂���悤�ɁA�킪���ł́A���͂�Ȋw�́A���j�o�[�T���ȕ��Ռ����Ƃ��Ď~�߂��Ă��܂��Ă���B�\�����āA���̐��������ƌ��E����ɂ�錾�ꐸ�_�Ŗ₢������҂ȂǗ�O���̗�O���A�悭�Ă�����Șb�̂ЂƂ��炢�ŕЕt�����鎞�ゾ�B����ɂ��܂�AIT�̔��Ԃ�������A���Ă̎ړx�����ɂ��ƂÂ����E�W���̈ꌳ�����ꂽ�w��V�X�e���𒆐S�ɁA�ӂ����сA�킽���������̓i���X�}�V���哱�̃R���Z�v�`���A���v�l�̖\���ɂ܂����܂�A��O�ȏ�̋��̋Ɍ��ɂ܂Ői�����Ƃ��Ă���̂�����ł���B
�@
���̂܂܁A�����ꐸ�_�Ԃ̎v���̍��ق̎��o�Ȃ����Ď��Ԃ��i�s���Ă����悤�ł���ƁA���̌��ʂ͐�̑��ȏ�́A�ߌ��I���Ԃ��������낤�B���ɑ҂��Ă���N���b�V���́A�����͊w�̈�`�Ԃɂ����Ȃ��푈�Ƃ́A�܂������Ⴄ�z�����ł��Ȃ����������Ƃ��Č����͂����B
�@
������Ƃ����āA�ߋ����疢���ɂ킽���Ă̈��̕�����ߑ㎩�R�Ȋw��r�˂��悤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�����ł́A���i�Ȃ����ɂ��v����[�߂āA�����ŗ���ꂽ���_���炻��q�ɁA�i���X�}�V�ł͂Ȃ��A��ꌾ�ꐸ�_�̑��Ή����ꂽ���ɂ�������_�������o������ŁA���݂�ᔻ�I�Ɏv�����݂�r������O�Ș_���ł����đg�ݗ��Ē�����ƂȂ��A����̌��ꐸ�_�͕a��ł��܂��Ƃ����A�ǂ̌��ꕶ�����ɂ��Ó����邠���炩�Ȍ������q�ׂĂ���ɂ����Ȃ��B���̖��Վ������܂܂ɂ���ƁA�킽�������̈ӂɔ����A�C�Â��ʂ����ɁA�w��Ƃ������͂�w�i�ɂ����i���X�}�V����������̂��ƁA�헪�I�ȊO����������͕̂K��ł���A���̕a�̓x�����ɉ����āA�N���b�V���̎S����܂��傫���Ȃ��Ă��Ă��܂��Ƃ������Ƃł���B�����Ԃ�ϔO�I�ɂȂ��Ă��܂������A�o�ρE�Љ�̘g�g�݂��Ƃ��ɂ��̌X���������Ă���B�܂��A�l�I�Ȃ��Ƃł͂��邪�A������p�V�[���ɂ�����\���̗L�����߂��闼���ꐸ�_�Ԃ̊����́A�����̒u�������܂�������Ɛ����̌��ʂ�����̂ł���A�u�ԏu�ԁA�����r�����Ƃ���ł̔��f�����܂���ڂ̑O�̌������ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@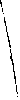
�@���Ȃ݂ɁA��ɈӐ}�I�ɒ����u��{�̖_�̂��Ƃ����́v�́A���̈ꕔ�ł��낤���A����Ƃ���͂�_���ꂩ�A�����~�����ł��낤���B������g���ĂȂɂ��������Ƃ����O��ɂ�������ŁA���Ɖ��߂���A�`�ʕ\���̃V�X�e���ɑ����钆���E���Č^�̒��ۊT�O�v�l�i�����܂Ńi���X�}�V�̎��_����ł���j���͂��炫�����B����A�_�����邢�͑~�����Ƃ��ċ�̓I�ȑ��ݕ��Ƃ��Ă����Ƃ�A�����ɂ�������N�Ƃ��āA���́u���v���̂���S�̓I���_�ɒ�������A�����ɓY�������t�������Ă������Ƃ���g���������̎��ォ�猻�ヂ�m�h�ɂ܂ł݂���A���ɂ���I�Ȍ��ꐸ�_���͂��炫�����B
�@ ���܂�ɒP�����������āA�킩��ɂ�����ɂȂ�����������Ȃ��B�i�R���Z�v�`���A���A�[�g�ɑ�����C�^���A�̃��[�`���E�t�H���^�i�̂悤�ɃL�����o�X�̕����I�i�C�t�������̂܂܍�i�Ƃ��Ē�����̂�����B������͂����ł�����q�������̑S�̓I�����ݏo���͂��Ȃ��B�����܂ŊT�O�Ƃ��Ă̔��|�p�ł���A�I�u�W�F�N�g�|�p�Ȃ̂ł���j�B�������A�����ł͉��Č^���ꐸ�_�ƕ�ꌾ�ꐸ�_�Ƃ������̂��킽���������ɓ����ɑ��݂��Ă���A���̂��ꂼ��̎~�ߕ��ɂ�錾�ꐸ�_�̔����̂������́A���ʂƂ��āA�܂������قȂ������E��������ł����Ƃ������Ƃ��@���Ă���������悢�̂ł���B
�@�����āA���́u��{�̖_�̂��Ƃ����́v�ɂȂ�ł��������A���钊�ۓI�u�T�O�v��u�������Ă݂�Ƃ����B���́u�T�O�v�ɑ���킽���������̎v���́A���́u��{�̖_�̂��Ƃ����́v�ɑ���Ɠ��l�ɁA��͂��̕������������Ă͂��炫�o�����Ƃ��������Ă��悤�B�ǂ�ȍ��̌��ꌗ�ɂ����Ă��A�u���v�Ɓu���v�ւ������錾�ꐸ�_�̃A�v���[�`�Ƃ������̂͂܂������p�������ȓ����������Ă���̂��B�킽���������̕��ɂ���I�Ȍ��ꐸ�_�́A���Ƃ���̓I�Ȍ������Ƃ��āA���́u���Ƃv���̂��琶�܂�o�����S�̓I���_�ɒ�������A�����ɓY�����u�����Ёv���͂��炫�����B�����Ȃ��Ƃ���ꌾ�ꐸ�_�̂͂��炫�������ꂽ�Ƃ���̘a�́E�o�~�ɂ����Ă͂������B���ƂɘA�́E�A��͂��������͂��炫���̂��̂��哱�����Ƃ���Ő������Ă���B�Ƃ���ŁA�u��{�̖_�̂��Ƃ����́v��`�ʂ̂��߂̐��Ƃ��ĂƂ炦��A���̕`�ʂɂ�����\�������Ƃ��Ă̐��E�ʂƂ̊W�������������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B����Ɠ��l�A�u�T�O�v�ɂ������ẮA�T�O�̖{����`�ƁA���̂ق��̊T�O�┻�f�Ƃ̊W���A�_�����Ƃ������̂���̂Ɍ��Ă����Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂����B�����łȂ��ƊT�O�̕����̂Ȃ��ʼnʂ��������A�Ӗ��͂Ȃ��Ȃ낤�B���Ƃ̊W�Ȃ��ɂ͊T�O���̂͒�`���ꂽ�Ӗ��@�\���������Ȃ��̂ł���B�������A���ɕ�炷�킽���������́A�T�O�v�l�Ƀi���X�}�V���ł����Ƃ��Ă��A�����A��܂Ƃ��Ƃɑ���Ɠ��l�ɁA�W�������āA���̊T�O���̂Ɂu���v���̂��̂Ɠ��l�̐[���Ӗ����������邩�̂悤�ɍ��o���āA�Ȃɂ��Ȃ��Ƃ���ɐ[�����������Ă��܂��B���̔w��ɂ͂����錾�t�ɂ͌������Ƃ��Ă̋�̐�������Ɗς��ꐸ�_���͂��炢�Ă��܂�����ł��낤�B���������v���̕������́A�_���I�Ȓ��ۊT�O�v�l�Ƃ͐����̂��̂ł���B�T�O��`�̉��ɂ���ɈӖ�������Ƌ��߂Ă����S���́A���Ă��Ă����ɎЉ�o�Ϗ����f�����������z�Ɏx����ꂽ�Ƃ��A�T�O�ɐ_��I�ȈӖ���t�^���ăZ�N�g���̌X����悵�A�ꍇ�ɂ���Ă̓J���g���܂ŕK�R���Ă��܂��B���Č��ꐸ�_�̂��݂��������w���_�Ƀi���X�}�V�A���ۊT�O�̂��ƂŋƊE���p��ɕ���������w�w���A���̑������̎v��������͂��̌���̉��X�w��Ƃ�������̂̑唼�������ł��낤�B�T�O�ɂ���ȏ�̈Ӗ����^���Ă��܂����̍\���͐V���@���̑�ڂ̉ʂ��������ƂȂ��ς��Ȃ��B�u�����o���v����u��Ζ����I���ȓ���v�ւ����āu�哌�����h���v����u�ꉭ���ʍӁv�ւ̓����͉������̂ł͂Ȃ������B����͂���ɐ����o�ς̈��ՂȌ��ʘ_�ł������łȂ��A��ꌾ�ꐸ�_�ƁA���ۊT�O�ɂ��v���̂��肩���̑���m�ɂł��Ȃ����������E�吳�E���a�Ƃ������㐸�_�̂��肩���ɋN�������ׂ����ۂł͂Ȃ��������낤���B�����Ă��܂ł��킽���������͂��̎v���x�N�g���̈Ⴄ��̌�������l�̓��̂Ȃ��ɗ��������A�ɉ������g�����������Ă���̂ł���B
�@�ЂƂ@�u�]���v�Ƃ������Ƃ��ɂƂ��Ă݂悤�B�u�R����́A���{�����̓����ł���u�]���v�����������|�p�ł���v�ȂǂƂ����g����������B�܂��A�u�]���̕��|�v�Ƃ���o�傪����B�\�̂悤�ɁA�u�]���v�͐_��I�Ȃ��̂Ƃ��āA���̂���ʂ��ƂŊς���̂��Ăэ��ޕ\�����Ƃ������B����������ƁA�N�������̐[���Ӗ������𑠂��Ă������ȁu�]���v�ɔ[�����Ă��܂������Ȃ����낤�B�������A���Ƃ��Ɓu�]���v�Ƃ͓��ʏ�ɍ\�����ꂽ�R���e���c�̃}�[�W�����]���̂��Ƃł���B�u�]���v�͓��ʂƂ����������̏ہE���ۉ������Ƃ���Ő����������ʋ�ԂɁA�`�ʕ\�����ꂽ�R���e���c���\������ۂ̃��C�A�E�g�f�U�C���Ɋւ���p��ł���B�i�O������Ԃł��낤�Ƃ����ɒ��ۉ��������͂��炢�����̂Ȃ�A����ԂƓ����w�E���Ó�������j�B����ƃj���A���X�̍��ɔ䂵�āA���̂��Ƃ̎������ƁA���ꂪ�Ӗ�����̈�ɂ����Ă̓}�[�W�����]����������������̂ł͂Ȃ��B�܂�A�u�]���v�Ƃ������Ƃ́A�����ł������ɂ�錾�ꃋ�[������͊O��āA���ۉ�������O��Ƃ��錾�ꐸ�_�Ƀi���X�}�V�������_����݂����ۊT�O�̈��Ȃ̂ł���B�ĎO�������A���̍��̌��ꐸ�_�͌��������ʍ��Ƃ��āA���ی����ɂ�炸�A�钷�����u���̂̂��͂�v�Ƃ��Ă̐��E�̂Ђ炫��������B������A���p�]�_�Ƃ݂̂Ȃ炸�A����ґ��܂ł��u�]���v�ɐ_��I�ȈӖ��^���āA���̂܂ܓ`���I�ȓ��{�̌|�p��i��]���E�����Ƃ�����Ƃ��̃L�[���[�h�ɂ��Ă��܂��Ă���B����ł́A��j����̓ꕶ�̈Ӗ����a�́E�o�~�̈Ӗ��������đ����̌|�p��i�̈Ӗ����T�ꂸ�A�����̍�i������ł��܂��B��ꌾ�ꐸ�_�̖��������݂������ЂƂ̌��ʂɂ����Ȃ����̂𒊏ی����ɂ���čl���悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�u�]���v�Ƃ������Ƃ������o�����r�[�ɁA�����ŁA�v�l��~�Ɋׂ�B����ȏ�u�]���v�Ƃ������Ƃ���`�J�����������ƂȂǂł��Ȃ��ł��낤�B�u�]���v�͑�ڂƉ����Ă���̂��B���ۉ������Ȃ��Ƃ������̌��ꐸ�_�́A�]���ݏo�����Ƃ͂��Ă��Ȃ����A�]���Ɍ�点�悤�Ƃ����Ȃ��B���ɁA���E�́A������������A�Ђ��߂���̑��݂Ő��藧���Ă���A�Ȃɂ��Ȃ���ԂȂǂ͂��߂��瑶�݂��Ȃ����Ƃ�m���Ă���B�́E�o��ɂ��Ă��A���ɒ�������A�����������ɁA���ɂ����Đ����̑��݂��Ђ炢�Ă������Ƃ͂��Ă��Ă��A�]����n��o�����Ƃ͂��Ă��Ȃ��̂��B�u�]���v�Ƃ́A�i���X�}�V���_�Ŋς����́A�v�l��~�����Ȃ̓��̂Ȃ��̋�Ԃ��ċA�I�Ɏ������Ƃɂ����Ȃ��̂ł���B���ɂ��v����[�߂�ۂ̏�Q�ɂ����Ȃ�Ȃ��p��̂ЂƂȂ̂ł���B
�@�C�X�����v�z�Ⓦ�m�N�w�ɒʋł��Ă����䓛�r�F��A���̉b�N�������Ă���悤�ɁA�ΏۂƂ̈�̊���厖�ɂ��铌�m��ʂ̎v�l�ɂƂ��ẮA���ēI�T�O�v�l�̖{���Ƃ������̂́A���̂��̂������낵���Ƃ���ł������������Ȃ����̎v�z�Ƃ������ׂ����̂ł���B�܂��Č��������ʂ��ƂŐX�����ۂ����邪�܂܁A���I�Ɏ�e���Ă�����Ƃ�����ɂ�錾�ꐸ�_�ɂƂ��āA�ΏۂƊώ@��̂Ƃ��Ď̏ہE���ێv�l���Ă��������I���i���Ƃ��j�v�l�̂�����́A���ɂ����Č���[�߂Ă����ׂ��킽���������̐S������݂�ƁA�t�ɁA�v�l���~���Ă��܂����l�����ł���Ƃ�����B����ȉ��Ďv�l�@�ŕ�ꌾ�ꐸ�_�����邱�ƂȂǂł���͂����Ȃ��̂ł��邪�A���������A����痼�҂̎v���̕��@�̈Ⴂ�̊m�F�Ȃ����Ă����Ȃ��Ă���̂��A���̍��̊w��A�|�p�ł���B�����́A���R�Ȋw�������ł���悤�ɁA�����q�ς��Ȃ�����A���͂��̋����Ă��v���b�g�t�H�[���́A���Y�Љ�̂����������ł���A�ێ�ł���A���z�Ƃ����y�ϓI���ړI���ɊҌ������ނ̂��̂ł���B�����́A�܂��A�L�j�����j�ɂ킽��Ñ�̘_����q�˂āA���ƁA���Č���ɂ��v�l�̈Ⴂ�m�����A������������A���q�Ƃ��������ŁA���Ⴂ�ɂ��ƂÂ����i���X�}�V���ɂ͍~���Ă��������A�O�Ɍ������Ă̓i���X�}�V�̔��[�Ȏ��_����ł͂Ȃ��A��O�ɖ��������ʂ��Ǝ��̓O�ꂵ���헪�I�v�l�ŗՂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
������A�u�������v�Ƃ͉ʂ����ĂȂ�ł��낤���B�L�c���v�ɂ��A�Ñ㕶���ł́A���ʕ\���Ƃ��A���܂��߁A�ނ݁A�ȂǂƂ̊֘A�p�@�Ƃ���Ă���B��ʓI�ɂ͌l�̈ӎu�𖾔��ɂ���ԓx�ł���A����͌��̂����悤�ɐ_���E�����ƂɂȂ���A���݁A�T�ނׂ����Ǝ~�߂��Ă���B�@�u�������v�������ʁA�_�̈ӎu���z���Ă��܂��A���𗎂Ƃ����Ƃ����`�����B�������A���̔ނ́@�u�������v�Ƃ������S���������߂���悤�Ɍl�I�ȐS�̑���l�ɂ̂݊Ҍ����������Ƃ͊ԈႢ�ł���B���̎~�ߕ��́A�l�ԂƂ�����̂�����Ƃ��Č��t�𑀂�A�\���₢�̂������̊�̂ɏ�������Ƃ��錻��I�ȉ��߂���o�����̂ɂ����Ȃ��B�Ñ㕶���ɎU�������u�������v�́A���ꎩ�̂ւ̌��y���^�u�[�Ƃ���Ă������m�̊�{�s�����̂͂��ŁA�Ñ㕶���̐����Ȃ��L�ڂ̕��͂���̂݁A���̖{�����𖾂��邱�Ƃ͓���ł��낤�B�u�������v�̓������ȂǂɊҌ����s�������ł͂Ȃ��B����͐��c�����Y���A���ǂ̗v���Łu�䍑���L�̎�̓I�����͌Ȃ����đ����ނ��Ƃł���v�Ƃ����ē������h���v�z�̍����Ƃ������_�ɂ܂ł��q�����Ă���Љ���l���܂߂��L���̈�ɂ��������ł���A�Ȃɂ��A�����ƁA�[�����ꂱ���u���������ʍ��̃��^�t�B�W�J�v�Ƃ������ׂ��u���v�Ɓu���v�Ɓu���v�Ƃ̊W�̓N�w�I�ȍ��{���ł�����B
�@
�u���v���u���v��Ώۑ��݂Ƃ��ĊT�O�v�l�ɗ��߂Ƃ����u�ԂɁu���v�͂���܂ł̋P���������������̕������݂ƂȂ�B�����ɂ��́u���v��Ώۑ��݂��Ȃ߂��A���̂ЂƂł���u�l�v���܂��A�ϔO�I�ȑ��݂��Ȃ߂��āA���̂��̂��͑~���܂��Ď��Ɏ���B��������̂����邪�܂ܓ��I�Ɏ�e���悤�Ƃ���̂�����������̌��ꐸ�_�ł���B�����̂ЂƂтƂɂƂ��ẮA�u�������v�����̂�O����������A���ۉ��������̂̑�������\�������������炷���̂Ȃ̂����炽�߂Đ�������K�v���Ȃ��A�݂Ȃ悭�m���Ă����ł��낤�B
�@���Ȃ݂ɁA�u�������v�́u�����v�Ƃ́A�A�́E�A��ɂ�����Ō�̎��E�����w���u������v�́u�����v�Ɠ��l�ɁA�u���Ɓi�������j�̏I�����w���Ă��邾�낤�B�u���v���u������v�Ƃ́A���錩�n��ݒ肵�A���̘_���ł����āu���v�����邱�ƂɂȂ�B���̌��n�����S�Ƃ�����̂̐ݒ�ł���A���ۂ�Ώۉ����邱�Ƃ̈Ӗ��ւ̏Ȏ@��Y��Ă��܂�������̉Ȋw�I��ς̐ݒ�ł���A�ϔO�I��̂��ݒ肳��āA�u�������v�ƂȂ����u�ԂɁA�����Łu���v�Ɓu���v�͕������A�u���v�͂����܂��ɂȂ�B���ꂪ�A�A�̘A��̍��̏o�����Ȃ�悢���A���A���̐��E�ł́A�u�������v�ƂƂ��ɁA�i���Ƃ��������̕ϓ]���d�˂Ă��鎖�ۂ̃C�}�͓r��āu���v�͏I�����A����ł��܂��B���̐_�b�I�ɉ��߂��ꂽ�킩��₷����̂ЂƂ��A�`�����̖��S�ɂ��A�u���v����ςɑ����Ă��܂����u�������v�̎��Ԃł��낤�B�`�����́u���v���A���S�����̂�ݒ肵�A�����ɂ���ɑΉ��������ۂ���̂Ɠ��l�ɒ��ۓI�ȑΏۂƉ����Ă��܂����̂ł���B�����ł́A�{����ςɂ��A�q�ςɂ������Ă��Ȃ��u���v���E�ɂ����āA�u���v�́u���v�ɓY�������̂ƂȂ炸�A�ϔO�ƂȂ��Ă��܂������}����B
�@�����āA���́u���������ʁv�Ƃ����֊��@�͕����Ƃ����u���v���Œ艻���鑕�u���������߂ɁA�������ɂȂ���₷���Ȃ����͂��̖��t�ȍ~�̂ЂƂтƂɂ��^�u�[�Ƃ��Čp������A���܂ɂ����A�����Ă킽���������̊�{�I�ȕs�����Ƃ��Ċ����Ă���B����́A�������l�ł��G�ꂽ�悤�ɁA���������ɍۂ��A���E�ł��ޗႪ�Ȃ��悤�ȕ\�ӂƕ\���̂܂������قȂ�ӂ��̕����V�X�e������������A���̖{�����u���ȁv�ɂ���Ă��̂܂܊������A���ۊT�O�́u�����v�ւƂӂ�킯�āA��ꐸ�_�̂�����������Ȃ��悤�ɂ��Ă����A��l�̓w�͂ƁA���������͂��炢�����ʂɑ��Ȃ�Ȃ��B�����ŁA�ꌩ�A���ۊT�O��|���ł��ӂꂩ�����Ă��邢�܂ɂ����Ă����A����猻���̊�w�ɂ́A�×����قƂ�Ǖς���Ă��Ȃ���ꐸ�_����������A�̐S�ȋǖʂł́A���̕�ꐸ�_�������K�͗͂����đO�ʂɂłĂ���B
�@�܂��A����Ɏ����s�����͓��{�ɂ����������Ƃł͂Ȃ��B�l�C�e�B�u�A�����J���̂���l�ɁA�e�B�b�s�[�i�C���f�A���e���g�j�ɏ��҂����Ƃ��u�킽�������́A���l�̍l�������L��ƌĂ�ł���B�ނ�͂킽���������ւ��Ă����������ł���v�l�A���ێv�l�ɑ��邩�炾�B�킽�������́E�E�E�v�ƁA�݂Â���̕����������w�����u���ŁA�̑S�̂Łv�����āA�e�B�b�s�[�̒����̘F�́A���̂܂��̂Ȃ�̕�������������c���炻�����Ă���Ƃ����Ӑ}�I�Ɏc�����\�y���w���āA�u���̑�n�ƂƂ��ɍl����v�Ƌ������q�ł킽���Ɍ�����B���̂Ȃ��ŊT�O�_�����\�������l�����������ɁA�g�̂�}��ɂ����A�ւ���S�̐��E�Ƃ����u���v�̋P�������֒ǂ������̂Ȃ̂��B���̖��́A�������������̒������̊T�O�v�l���^�u�[�Ƃ��Ă��Ă��A����ȃ^�u�[�͖��J�̕��K���ƈ�R���錻��l�ɁA�ۉ����Ȃ��ŖS�̕��ɂ܂Œǂ�����Ă��܂����ނ�ɂƂ��āA���܂Ȃ��A�킽���������ɂ͑z�������Ȃ����炢�ꂵ���؎��ȍő�̖��ł���Â��Ă���B����͐����J��̘b�ł͂Ȃ��A���݂̘b�ł���B�����Ă���́A�����̂킽���������̕�ꐸ�_�̊�{�ɂ���������Ă�����ł���B
�@
���ɂ��ǂ��B���̊�͊G�A�܂�`�ʂƂ������ۉ��ւ̗U�f�ɂ͈�̂炸�A�Ȃ��̕\�ۉ����������������Ă���B���̃^�u�[�̂͂��炢���́A��̕\�ʂ��A�\�����邽�߂̊�̂Ƃ͂����A���ɃC���[�W�i�C���[�W�Ƃ͊ϔO�ł���A����Ƃ�����̂��̂���e����ۂ̖W���ƂȂ���̂ł���j���t���Ȃ��悤�A����̓I�ȓꕶ��Y�킹�Ċ�̂������ƈ�̉������Ă����i�L�k�Ƃ�����̕��ɂ����������܂ށj���̓�ځi�����j�̂͂��炩�����ɂ���B�ꕶ����̂��̓�ڂ��A�{���W�[�j�̒��ە��l��V���C�A���̃e�B�b�s�[�ɕ`���ꂽ�����X�g�[���[��g�[�e���̂悤�ɁA���̕����̕���萫�������ǂ����͂킩��Ȃ��B�������A�����ŏd�v�Ȃ̂́A�ꕶ�ɂ͂��炢���v�z�́A�A�z�Ƃ������@�̋��ŁA�⍓�Ȃ܂łɒ��ە\�����ɂ߂������u�E�����b�W�i�g�E�e�c�j���̎v�z�Ƃ́A���ۉ��v���Z�X�̗L���A���Ȃ킿�\���`�ʂƂ����v���b�g�t�H�[����u�����u���Ȃ����Ƃ����Ӗ������ɂ����āA�܂������ɂɈʒu�������^�N�w�ł������Ƃ������Ƃł���B
�@
�O�������E������E�ւƒ��ۂ��A��\�ʂ�\���^�u���[�Ƃ݂Ȃ��āA�����։A�z��������������u�E���̒��ې��E�B����ɑ��āA���ׂĂ�����̂܂�e����ƁA�̏ۉ��A���ۉ��A�C���[�W�����^�u�[�Ƃ��A��̓I�ȕ��ւƕ��킹�Ă������ꕶ�v�z�B�i�ǂ̍��̌Ñ�y��ɂ��݂��Ȃ��Ǝ��̂��̂Ƃ��āA�ꕶ�O������݂�������ˋN�Ɏ{�����l�ʃC���[�W�\���̈Ӑ}�I�Ȕj��Ȃǂɂ́A���̃^�u�[�v�z���Ïk����Ă���j���������āA���̗����E����e���鐢�E�͎R����̋P���ЂƂƂ��Ă��A�r�����������قȂ������e�ƂȂ��Ă���̂ł���B�������A���̍����₪�Ē������N�̉e���̑���Ƌ��ɁA�퐶�ƌĂ�鎞�オ�A�ꕶ�Ɏ���đ�����B�����ł̂��̂̕\���́A�퐶�y��⓯����̓����Ɏ{���ꂽ���l��G�ɂ݂ĂƂ��悤�ɁA�������N�̉e���������ēy��\�ʂ���^�u���[�Ƃ��Ĉ����A�܂��ꕶ�ł͂��܂�݂����Ȃ���������A�����l�X�������Ƃ��������\���ƂȂ��Ă����B�₪�Ă����́A���̌�̑D��n�A����`���������Õ��̍ʐF�i�ʐF�Ƃ����F�ɂ��\���\�����܂��A���ۉ��̃v���Z�X���o�������ł����\�ƂȂ�Ȃ��j��ɂƂ��Ċ�����A���ɂ͍��x���ۉ������ł��݂����ꂽ��������e�����ӂ�ŁA���N�v�z�̉e����Z���������q�@�lj�̎�����}���邱�ƂƂȂ�B
�@���������J��Ԃ��ɂȂ邪�A���̂͂��炫���܂������������錾��A���Ƃ��A�����ߑ�̂悤�ɕ\���̂��߂ɑ����_���̏ۂ��A���ۂ������ʂ̃p�[�X�y�N�e�B�u�ȑ��^���_�ɕK�R����Ɏ��������ۊT�O�Ř_���v�l����C���h�E���[�}����n���@�B�����A���ۂ�r���āA���ɂ����Ē��������Ă����킽���������̕��̎v���̂͂��炫�B���̗��҂͂܂��������̈�������ꐸ�_�ɂ���B���̌��ꐸ�_�̈Ⴂ�́A�Ñ�y��̕��l��G��ɒ��ڔ��f����Ă���B�����ꕶ�����Ƃ��ɃC���h�E���[�}����n�̌Ñ�y��́A�\�z�I�Ȑ��i��������t�H�����ւ̌X�������B�����āA�����֎{�����l��G�́A�^�u���[�Ƃ��Ă̊�Ɛ藣�����Ƃ��\�ł���A�Ɨ����Ă͂��炭���l��G�Ƃ��ċ@�\����B����A���̐���ɑ�\�����ꕶ�y��́A���ꕶ�̃^�u���[�Ƃ��Ȃ��B���҂�藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B���l������Ό`���̂������Ă��܂��̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�Ō�̐R���@�C����ƕ��i�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���^�E�}���A�E�f�b���E�O���c�B�G�C���@�@Leonardo
da Vinci
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̒��ۋ�Ԃł����_������@�̑�\��B�@�B�e�@�L
�@ ������ŁA�G��Ƃ̓^�u���[�i�ȉ��A�^�u���[���L�`�̈Ӗ������Ŏx���̂Ƃ��Ďg�p�j��O��Ƃ��Đ������Ă���B�Ñ�y��ł��낤���A�A���^�~���̓��A�ǂ�剾���̓V���ǂł��낤���A�ߑ�̃L�����p�X�n�ł��낤���^�u���[�͂����֕\�����~�߂郁�f�B�A�Ƃ��āA�����𒊏ۂ����ϔO�̃[����Ƃ��ċ@�\����B�O�����̗��̂���ʂւƒ��ۂ��A�܂茻�����̏ۂ��Ċ�̂Ƃ��Ă̓��֗��Ƃ����^�u���[��ŁA����ɒ��ۉ����ꂽ��Ԍ`���ł���A��ʊO�Ɉ�_�Ɏ������鎋�_�����������p�[�X�y�N�e�B�u�Ȑ}�@�ł����āA�������z��l�̊ϔO�C���[�W���f���Ƃ������̂��A���Ƀ��l�b�T���X���̒��ۉ����ꂽ��Ԍ`���}�@�ō\�������`�ʂ��ꂽ���̂���ʂɁA�킽���������͐����G��Ƃ��ł����B���̕`�ʕ\���̌����v���Z�X�́A����̐i�W�ƋO����ɂ��Đ�������̕\���@�Ƃ͏�Ƀp�������ȊW�ɂ���B��������ł́A����o�����ӂ邢�ɂ����ĕ��ՓI�Ӗ������𒊏o���A�����œ������ۊT�O������ɍŏ�ʂ̒��ۉ����ꂽ�[���|�C���g�̋ɓ_���_�ɕۏ���A���͂�_�Ɠ����ɂȂ������_�̂��Ɓi����A�_�E���B���`�̂��̎��_�͂��łɐ_����D����������_�ł������j
��͂茻���𒊏ۂ����ϔO�̃[�����Œ��ۊT�O���\�z�E�_���Â��Ă����B����A���ۓI���_�ƊϔO�̏��ݒ肵�Ȃ����ƂŐ��E������̂܂܂ɋP�����悤�Ƃ������������ʍ��ɂ����āA���i����Ȏ��o���Ȃ��A�킽���������͖|�ۊT�O�ɂ�鉢���_���v�l���܂����Ԃ��ʼn\�ł���ƐM������ł���B�����A�����ɓ��ٍ̈��̂����ĂȂ������Ƃ͈قȂ�A��������ɂ͐����Ɏ����A���邢�͊m�łƂ������ߓ����}�@�ɑ�\�����悤�ȓO�ꂵ�����ۘ_���v�l���͂��炢�Ă���B�����Ă���ȉ��Ă̒��ێv�l�́A���̈�̌��ۂł�����p�ɂ����ČÓT�I�ȃp�[�X�y�N�e�B�u���_���p������Ă�������l�ȓW�J������Ȃ����ɓ����v�l����т��Ă͂��炫�����Ă���B�L���r�X���Ƃ��t�H�[���B�X���A�_�_�C�Y���A�V�������A���X�����̋ߑ�|�p�v���͂����ŏȂ����A���̌�̕���ΏۂƂ��������i�I�u�W�F�N�g�j�|�p��T�O�|�p�i�R���Z�v�`���A���A�[�g�j�ɂ����ẮA���̖����̂����ɔނ�̗��j�I�v�l�̖{���������Ă��悤�B�ЂƂ���̃C���X�^���[�V�����A�p�t�H�[�}���X�ɂ����Ă����ۉ����ꂽ���Ԃ̃x�N�g����������ꂽ�����ł���A����ɔނ�̂����C���[�W�����ۂ������|�p�ł����A�`�ʕ\���̐������钊�ۉ��ɂ���̌����͌ÓT�G�掞��Ƃ��������ς���Ă��Ȃ��̂��B���R������IT���ŁA����܂ł̃|�b�v�A�[�g����{�̃A�j������������ŔĐ��E�I�ɗ��s���Ă��郁�f�B�A�A�[�g��R���e���c�|�p�ɂ����Ă�����͓����ł���B
�@�����ɑ��ē��m�G��̓����́A�����G��̂��̃p�[�X�y�N�e�B�u�Ȉꌳ���_����\�����ꂽ���̂Ƃ͈قȂ�A���������_���ʂɋ���������\���ɂ���ƈ�ʓI�Ɍ����Ă���B���̗�ɂ悭�Ђ����̂������ɔ�����R����ł���B������̈ꌳ�I�Ȏ��o�d���̕��@�ɑ��āA
��̉��̊ϓ_���瑽���I���_���ꌳ�I�ɂ܂Ƃ߂��A����瑽�ʂȎ��_���������ɑS�̓I�Ȏ��_�ւƑg�݊����邢���鍂���A�[���A�����̊e���_���ʂɂ܂Ƃ߂�O���@�ƌĂ���@���������B�����ł͑��p���_�I�Ɏ���đS�̐�������Ă������Ƃ����͂��炫������B�������R���͂����܂ŎR���Ƃ��Đ��E�̎�̒��ۂ̃v���Z�X���o�āA��������ʂւƉf���A�ϔO���č\�����ăC���[�W�`�ʂ������n�̊G�ł���B�����ɂ́A�����ɂƂ��Ȃ��Ď̏ۂ���Ă��܂������E������B
�@
�Ƃ��낪�g���������́A��_����̕`�ʂ����ނ��Ă���B�����Ɏ{���ꂽ��̖ڂ́A���m�ɂ����ƁA�f�U�C���Ƃ��Ă̕��l�\���ł��Ȃ��B���ۉ��ɂƂ��Ȃ��̏ۂ�����Ȃ��Ŋ�̂Ђ炭�F���ƈ�̉�����Ƃ��ċ�̓I�ȌW��荇�������߂Ă������p���̂��́A���̎p�������ɂ���č��ꂽ���̂ł���B�������Č`�����ꂽ��́A���ꎩ�g���\�������������Ȏ咣�������Ƃ�����I�Ȑ��_�ւƏ�����B�����ɂ����ď��߂āB�������̑��݂��A���邪�܂܋��������Ď�e����Ƃ������Ƃ��\�ƂȂ�B���̂��߂��A���͂�l�����t���ʂ܂łɕ\�����ɂ߂������u������Ƃ������A���̐���́A�Ј��I�ł��A���ГI�ł��Ȃ��A���邢�́A����ł��Ȃ��B�����₩�Ȍ����ɔg���������āA�Ȃ��قǂł�邭�c��݁A�����āA�Ȃ��炩�ɋt�O�p���ɍ�݂䂭���炩�ȃt�H���������B�����ւƓꕶ����̉����ʂ����Ă���B
�@
�������āA�g���������͊�̖{���Ƃ��ĕ��������i���j�̋@�\�����݂̂Ȃ炸�A���̊킻�̂��̂̂�������炵�āA���łɋ�i���j�Ȃ鑶�݂ƂȂ��č݂�B�̏ۂ��Ȃ��͂��炫���݂�䂦�ɁA�u���b�N�{�b�N�X�Ƃ��āA���l�Ȏ��_�����������̂��������I�Ɏ�e���A���A�����ݍ���ł�����̂��B����́A�u�āE�ɁE���E�́v�ɑ�\�������̐��E��e�̂��肩���Ɠ����ł���B����A�t�ɂ��̊킪�A��ꐸ�_�ݏo���Ă���Ƃ���������������B�����Ă��̐��_�́A�u�Ȃ����đ����މ䍑���L�̎�̓I�����v�Ɛ�O�A���c�����Y�ɂ��킵�߂����́u���E�V�����̌����v�_����|�X�g���_���̐��E�I�����ɂ��܂ꂽ��A70�N��ɐ��ݏo���ꂽ���m�h�̈�A�̍�i�Ȃnj��ݔ��p�̍őO���ɂ܂Ő���N���̂������͂��炫�����Ă���̂��B
�@
���{�̒������p�j�̂Ȃ��A�ꕶ��ɕ�ꐸ�_�̎����I�Ȃ͂��炫�Ő��������̂́A���̃��m�h�̔��p�ƌ��㕑���ȊO�ɂ͌�������Ȃ��B���̂ق��͂��ׂāA�A�����ꂽ���̂��x�[�X�Ƃ��Ĕ��W���Ă����B��ʂɔ��p�j�ň����Ă�����{���p�͊O�����ꕶ�����Ŕ��������ނ̍��̌��ꐸ�_�����f������i�̒��A�����A���^���A�悭�����Ă����̍��������ꂽ���̂ł���B�����ɂ��킪���Ǝ��̌|�p�G�悪�Ђ炢���Ƃ����Ă��铍�R����]�ˏ����̎R���悳���A�����ɂ������̗�ɘR�ꂽ���̂ł͂Ȃ��B���{���p�j�͓Ǝ��Ɏ����I�ɔ��W�i�����Ă������̂ł͂Ȃ��B�퐶�ȗ��A���̂ǁA�ړ����ꂽ�|�p�v������{���A�a�m�����A������J��Ԃ��Ă��������̗��j�ł���B������P�Ɏ��ԏ��Ō��āA���ׂ����̂����{���p�j�Ƃ���Ă���B
�@
�ꕶ�ȍ~�̋�̗�����������グ�Ă݂�B������y��Ɉ₳�ꂽ���`��̖̂퐶�G�Ƃ������̂�����B�����ł͂��͂�̏ہE���ۂ�������ꕶ�ꖜ�N�̃^�u�[�͖�������Ă��܂����B�O��������ɒ��ۂ����C���[�W�\���ƂȂ������̊G�́A��⓺���Ƃ����^�u���[�Ɛ藣���Ă���������B���̊G�͒����E���N�̌��ꃁ���^���e�B�[�ŕ`���ꂽ���̂��B����̂ɒn��I�ȍL������������ɓ����̏����ƋO����ɂ��ċ}���ɏ��ł���B���̂��ƁA�Õ��̍ʐF�悪�o�����邪�A������܂������⒆���G��̃_�C���N�g�ȉe�����Ă��邱�Ƃ͂��炽�߂Đ����̕K�v���Ȃ����낤�B�Õ��̐Εǂ���ʂ̃^�u���[�Ƃ��āA�����̊w���l�A�����Ď��Ⓓ�A�����Ƃ����O���v�z�̃��`�[�t�ŕ`����Ă���B�I�NJ��ɂ͍����ˌÕ��lj�ɂ�����B���̃v���Z�X�����猩���Ă�����̂́A�e�����������ȂǂƂ������Ղ������̂ł͂Ȃ��B�����̈Ⴄ�����̌��ꐸ�_�ɋ������\�������̂܂܂����Ă��āA��������f�B�t�@�C���������̂��̂ł���B�Õ����オ�I���������Ƃ́A�����Ƃ������x�ɃV�X�e�}�e�B�b�N�ȕ����G���A������A����������p����͈�ς��Ă��܂��B
�@
�Ȃ��A�t�s���邪�A���̊��艺�邱�Ɩ}���O��N��A�ꕶ�����ɂ́A����l������������ƕ]������Ή����y�킪���܂��B���̔g���������Ƃ���ׂ�ƁA���A�S�V�b�N�I�ȕ\���ɌX�����炢������͂�����̂́A�������ɂ��̃v���~�e�B�u�Ȗ������͔������B���āA���̔g���������͒����̊�{���f���̂悤�ȑ��݂ł���A�Ή�����]���鐶��������Ƃ������ʑ��I�ŁA�ߑ�R�����ɂ��ƂÂ����p��ȂNj��ۂ��Ē��R�Ƃ��Ă���B�i��������C���h���[�}����n�̗p��ŁA���̖��������㐸�_�̂͂��炫�͂��邱�Ƃ́A�{���A�����I�ɕs�\�ȍ�Ƃł���B���Ƃ��ΉΉ����y��̕]���ɂ݂���悤�ȁA�����͂��ӂ��Ƃ������`�e�����̊�͋��ۂ��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A���̊���I���ꂠ�邢�́ALife��Vitality�Ƃ������Č�̖|���ɂ͂��łɎ�q���T�O�I�Ӗ���p�����͂��炫����p���Ă��邩��ł���B�j
�@
���̊�͊T�O����������͂��炫�łł������������̂ł���B�܂�A���̐���ɂ͂��炭�@�Ɠ����@���͂��炭���������㌾��ɍ������Ì��E��܂Ƃ��ƂŁA���ɂ����Ďv����[�߂Ă����Ȃ��ẮA���̖{���ɂ��܂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Č^�̊T�O�_���v�l�̗�������ލl�Êw�͂��߁A�����l�ފw�A�����w�܂��A�|�p���w�ȂǓ��{�̏]���̊w��̂قƂ�ǂ̕��͍�Ƃ́A���̓_���N���A�ł��Ă��Ȃ��̂ŁA���Ԃ��̑����̊̐S�Ȑ��_�����ݎ��Ă��Ȃ��B
*�X�E�B�b�`���O�F ���ꂾ�������A�킽���������͕����g�p�ɂ����Ċ����Ƃ����\�ӕ����Ƃ��ȂƂ����\����������p�ɃX�E�B�b�`���O���Ȃ���g�p���Ă���ƓI�����������Ă������A���̗p����ؗp�����B�����g�p�ɂ����Ă���ł͂Ȃ��B�킽���������́A�̐S�Ȑ��E�ς����Ԃ����ɂ����Ă��A�����ƁA���̃v���Z�X�A���ʂ��܂������قȂ�v�l�@���X�E�B�b�`���O���Ȃ���邵�Ă���B�ߐ��͐钷�������ӂƕ��ɂ�錾�ꐸ�_�ԂŁB�����Č���ł́A���Č��ꐸ�_�ƕ�ꌾ�ꐸ�_�Ƃ̊ԂŁB
*�i���X�}�V�Ƃ́F�ȉ��ɐ钷�����ߐ��̊��Ӂs�J���S�R���t�Ɏ��������������̂̌����ƌ���̉��Ă���Ƃ������̂̌����A��ɒ��ۉ����ꂽ�T�O�v�l�Ɏ��������������̂̌����Ƃ����킹�������Ӗ��Ƃ��Ďg�p�����B
�@ �u���Ӂs�J���S�R���t�E�i�m�Ӂj�Ƃ́A�����i���āj�̂ӂ���D�݁A���̚������ӂƂԂ݂̂����ӂɂ��炸�A�傩�����̐l�́A�݂̎��̑P������s���T�A�V�T�t��_�ЁA���̗��i���j�������߂��ӂ����ЁA���ׂĂ݂Ȋ��Ёs�J���u�~�t�i���āj�̎�Ȃ�����Ӗ�A����͂���Ԃ݁i���Č�j����݂���l�̂݁A�R��ɂ͂��炸�A���i�p��j�Ƃ��ӕ���������邱�ƂȂ��҂܂ł��A�������Ɩ�A��������Ԃ݁i�p��j����܂ʐl�́A����S�ɂ͂���܂����킴�Ȃ�ǂ��A���킴�������i���āj���悵�Ƃ��āA������܂˂Ԑ��̂Ȃ�ЁA��N�i�S�N�j�ɂ����܂�ʂ�A���̂Â��炻�̈Ӂs�R�R���t���i�m�j���ɂ䂫�킽��āA�l�̐S�̒�ɂ��݂��āA�˂̒n�ƂȂ��̂ɁA��͂��炲�T��i���Č^�̔��z�j�����炸�Ǝv�ЁA����͂���Ӂi���Ă̎v�z�j�ɂ��炸�A�c�R���s�V�J�A���x�L�R�g�����t��Ǝv�ӂ��Ƃ��A�Ȃي��Ӂi���ēI���_�j���͂Ȃꂪ�����Ȃ�Ђ������A�E�E�E�v
- �钷�@�i�@�j���͚F�����lj��@
�@�@�@�@��A
�@ ���t�̂ɂ݂� �u����(�^�})��g��(�L�n��)�v ���܂��͂�Ƃ����i�����Ɗ��S���Ɋւ���_�����A���łɂ��̊�ɂ͂��炢�Ă���B���̘_���́u���������ʁv���Ƃƕ\���̊W�ɂ���B
�@
���̖@���A���̂̕ϐ��������ꂽ�g��̌����������̂��̃J�^�`�ƂȂ��Č���Ă���B���̘_���́A���R���C�}�E�R�R�ւƌJ�����A���{��̖{���ł���ă��^���W�J���Ȍ���ɂ�����S�̓I���������݂������̘_���Ƃ������ׂ����̂��B�u���܂��͂閽�Ɍ������v�Ƃ����Ì��ɂ͂��炭�_���Ɠ����͂��炫�āA����܂ň��̓y�ɂ����Ȃ�������́A���܂�A���܂����̋��̂Ƃ��Ă̊��S�������Ɍ������A���̉ʂĂ̊��S���������J����ꂽ�Ƃ��Đg���Ђ炫�A�C�}�E�R�R�̉i�����̂Ȃ��ɐ����đ���B��́A�ł���Ȃ���A���̌��S�̐��E��X����u��v�Ƃ��ĕۏႳ��A������Ȃ����̑S�̐��E�̊U�ւƖ����ɐi�s���Ă��������������Ƃ��āA�p���h�b�N�X�ɂ݂����i�����̓��I�_����X���Ă���B
�@�u���������ʍ��v�Ɖr�F���`���Ɍ������l�����̏W�A���̔����̂́A�u����(���Ƃ���)�̍�(����)���鍑���^��(�܂���)�����肱���v�ƂÂ����A���̑O��̃e�N�X�g��ǂݍ��킹�Ă݂�ƁA��������́A���̍��̌��i���Ɓj�ɂ́u����(�^�})��g��(�L�n��)�v�Ƃ����^���������l�ł����i�����̘_���A���邢�́A�����ʂ�u�^�}�i�ʂ��邢�͍��j�E�L�i���j�E�n���i����y�яt�j�v�Ƃ����i����A�̘_�����͂��炫�A�������̐^��(�܂���)����ۏႵ�Ă���Ă���A���������_���\�����������Ñ�̖@�̂͂��炫���u�R�g�E�^�}�v�ł���Ƃ����l���C�̐[���v�����ǂݎ���B����́i�����ł͗��ʂɍۂ���̂Ƃ��Ă̐l���C�̒u���ꂽ���͂ɂ͗�������Ȃ��j�����Ƃ����O�����ӎ�������ŁA���̃��^���_�̂��ƂŎ����̂��Ƃ�����Ă���B�܂��u���������ʍ��Ō���������v�Ƃ������l���C�̂��ƂΎ��̂́A�u�N���^�l�݂͂�ȉR�����ƃN���^�l���������B����͐^���U���v�Ƃ����_���I�p���h�b�N�X�ɂ����Ă͂���B���A����������̓p���h�b�N�X�ł��Ȃ�ł��Ȃ��A���������̂��̂ł��Ȃ��B�����܂Łu���������ʁv�Ƃ������Ƃ�ޓƎ��̑Ό�I�Ȓ��ׂɏ悹�āA��������͂��炫�����������Ό��@����ł�����ł���B�܂��āA�P�Ȃ�O���֑R������ȃi�V���i���Y������ł���`�v�z�ł͂Ȃ��B��ꐸ�_�̎����ɂ��ƂÂ�����ÂȎv�������I�ɏ����ꂽ���Ƃł���B
�@�^���́u��Ӎl�v�ɁA
�u�ЂƂ���̓����Â隠�͌\���i����j�̂���̂܂ɂ܂Ɍ��i���Ɓj���Ȃ��āA�݁i���Áj�̎������i���j�����i�Áj���炢�ЙB�ւ邭�ɖ�A����̓����i�����j�隠�o�����낱�������Ӂp�͖��Â̎���㉁i�����j�����Ă��邵�Ƃ��鍑��A����̓��̓����o���V�������Ӂp�͌d���i����j���i����j�̂����㉁i�����j�����āA���Â̎��ɂ킽���p�隠��A������ɔ䚠�ɂ̂�㉁i�����j������������E�E�E�B�v�Ƃ���B
�@���E�̎~�ߕ��́A�u�����������ʁv���Ƃ���{�K�͂Ƃ��鍑�̐��E�ƁA�����́A����A���܂ł������ł��邪�A����V���̂悤�Ɂu���������鍑�v�A�܂�A��q���̐ݒ�̂��ƂŌ�����i�����j�G�A�����Ƃ����\�����ꂽ���̂���`�Ƃ��Đ��E�֑Λ����悤�Ƃ��鍑�Ƃł́A���̐��E�̌������͂܂�ŕS���\�x�قȂ������̂ƂȂ�B���̍��ق��A���̍��̕M�����l�E�l���C�ɂƂ��āA��Ȃ�A���炽�Ȃ�����Ƃ��Ď������ꐸ�_�ւ̎����ƂȂ�A���ւāu����������(��)������v�Ɓu�����������ʁv���Ƃɂ��u���v�̗s���l���r�܂��߂��̂ł������B���̎v�z�́A���ւƏ�����ʑt�ቹ�Ƃ��āA�ނ̊i��������A�̉̂̋������x���Ă���B
�@�������Ȃ���A���݁A���̂����Ƃ��̗v�ȕ��̃G�b�Z���X�����߂�����Ă���B���邢�́A�Y�p����Ă��܂��Ă���B���̍��͐l���C���ւ荂���r���悤�ɂ��Ƃ��Ɓu���������ʁv���ł���B�����āA���̎v�z�̌����ƂȂ��Ă���ꖜ�N�ȏ�ɂ��킽�閳�������㌾�ꐸ�_�̂͂��炫�́A���܂��A�킽�������̈ӎ��̒�ł́A�قƂ�ǂ�����Ă��Ȃ��̂��B�����A�Â��͓��y�A�V���A�ߑ�ł́A���Ă̎�q���̐ݒ�̂��ƂŌ�����i�����j�G�A�����Ƃ������̂���`�Ƃ��鐢�E�A�����Ă��̕����ɂ͂��炭���ۘ_�����E�̗��i���Ƃ��j�ɂ�����D���Ă��܂��A�̐S�Ȃ��Ԃ�̑����̌��ꐸ�_�̂͂��炫���ӂ����l���Ă݂悤�Ƃ��Ȃ��B����ǂ��납�A�l���C�̌ւ�A���Ȃ킿�����Ƃ���㉁i�����j�������Ȃ������w��ɂ��钊�ۉ���ނ��Ă����u�����������ʁv�Ƃ����ӎv���t�ɃR���v���b�N�X�Ƃ��ĂƂ炦�Ă��܂��B
�@
�����قǎ��グ�������Ȓ������ł������s��̌�����̃R���v���b�N�X����Ƃ͂����u���{�l�̔�_���I���i�́A���̂�����_���I�������̂�������т����v�ҍ�p���͂��炩�ʂ悤�ɂ����Ă���X��������B���łɌÑ�ɂ����Ċ`�{�l���́w�����̐���̍��͐_�Ȃ��猾�������ʍ��x�ł���Ɖr���Ă���B�����ɂ����ẮA���ՓI�ȗ��@���A�ʓI�Ȏ�����܂Ƃ߂���̂Ƃ��č\������Ƃ����v�҂��͂��炩�Ȃ��B�v�ƁA�u���������ʁv���Ƃ�ے�I�����̂Ȃ��Ō���Ă���B
�@
�Ƃ��낪�A�����́A�t�Ȃ̂ł���B�䚠�ɂ̂�㉁i�����j������������B- ㉁i�����j�Ƃ́A���A�ʁA�F�A�����Ă��ꂪ�`�ʂ����}�́A���Â���������̏ہE���ۂ��Ă͂��߂Đ���������̋������݂ł���
- �܂�킽���������́A�������̏ہE���ۂ����A�����Ő��܂��ϔO�I�\�ۂ���؊������A���̂��Ƃ���{�S���Ƃ��āA�āE�ɁE���E�͂ɂ݂���悤�ɁA���ۓI�ȊT�O�m�ɑ��邱�ƂȂ��A�u���̕ω��ɂ��@�q�ɉ����A���̂��ƂŁu���́v�̗s���������܂ŋ�̓I�ȕ����̂��̂Ƃ��āA�l�H�̎�����ꂸ�A���I�ɂ����Ƃ߂悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�����ɂ͂��炭�v���͉��Č��ꐸ�_�ɂ��͂��炫�Ƃ͈Ⴂ�A���E�������I�ɑĂ������Ƃ��ł���ƂĂ��Ȃ��\�����߂Ă���B�l���C�́A��������o���Ă����B
�@���ꂩ���琔�S�N��A����́u�ʑ�-��n�v�Ƃ�����i���܂��ɂ��āu����͐l�ނ��܂��m��Ȃ������`�J�����v�ƂԂ₢���j������B�����̓��{���p�E�łْ͈[�ɑ����Ă������m�h�ɕ��ނ����֍��L�v���B������킽�����̓G�|�b�N���[�L���O�Ȉꌾ�Ǝ~�߂�B
�ꕶ�ꖜ�N�̈�̒��ۉ���r���ė������ɂ�錾�ꐸ�_�̊j�́A�ꕶ���f�B�A�������Ĉȗ��A���������ʂ��ƂƂ��Ẳ́E�o�~�Ƃ������ꃁ�f�B�A�ɂ��̐��_���p����Ă����B���̐��_���A�|�X�g���_���̗���̂Ȃ��A�����Ԃ�����I�ł͂��������A�ӂ����у��m��g�̂��̂��̂����f�B�A�Ƃ��āA�n��Ɏp���������u�Ԃ̂��Ƃł���B���ۉ������Ȃ��ŁA�������Ɛ��鐢�E�Ƃ́A�퐶�G�ȗ����ۉ��̗��̂Ȃ��Ɉ�����Ȃ��������{���p�E�ɂ����ẮA�o���ł����Ȃ�������فi���������₵�j���ɂ��ӂꂽ�������鐢�E�ł���B
�@
�u���Ƃ��܁v�����Ƃɐ��삪�h���Ă���Ƃ���A�j�~�Y���I�㐢�̉��߂́A�u���v�ɂ����āA�u���v�ɒ�������A�u���v��[�߂Ă����Ƃ����킽���������̕�ꐸ�_�̎v���ɔ����Ă���B����́A���ċߑ��ώ�`�̂����炵���A���ׂĂ�Ώۉ����Ă��܂��A�����ł��܂��C���[�W�����ꂽ�\�ۂɂƂǂ܂��Ă�����̎v�l��~�̎Y���ł���A�܂��A���邢�͎╧������e�����ߒ��������炵���Ƃ���̌��ۂ̔w��ɂ��_���̓�����ݒ肵�Ă��܂��K����K���ɂ��܂�A���ɂ����Ďv����[�߂Ă������Ƃ��킷�ꂽ���M�̂ЂƂł���B
�@
�u���i���Ɓj�v�́A��G��̂��邱��Ƃ��āA��فi���������₵�j���ɂ��ӂꂽ�u���v�̂ЂƂł���B����Ƃ��Ă��Ƃ����ɂ����Ƃ��A�u���i���Ɓj�v�́A�u���v�Ƃ��āu���v�ւƂ͂��炫�����u���i���Ɓj�v�Ɛ���B���́u���i���Ɓj�v�ɐG��āA�钷�����u���̂̂��͂�v�������A�X�̐g�̂�}��ɂ��Ȃ�����A�����ŎY�܂��S�̐��̎����ɗ^���邱�ƂŁu���Ɓv�Ƃ��Ă̎v���E�v�l���͂��߂ĉ\�ƂȂ�B�킽�������͂���ȁu���v����e����u��v�Ƃ��đ��݂���B�����āA�܂��ɂ��̂͂��炫�����������y���ꂪ���̔g������̐����������u��v�ł���B�`����̓��i�^�I�j�Ƃ����Ќ��ɂ݂������ی�������e�����b�W�i�g�E�e�c�j�����{�������u�ł͂Ȃ��A�����܂Ŕw��ɒ��ۉ�������ݒ肹���A��̓I�ȁu���v�Ƃ��Ă���u���v���u���v�̂͂��炫�̂܂܂ɁA���̂͂��炫���Ƃ߂��ł���B
�@����Ȕg���������́A�����Ŏ�����e����u��v�Ƃ��āA�������̐^��(�܂���)�R�g�^�}�i�ʁj��e��ւƓW�J����ɂӂ��킵���A���炩�ȋ���̌����������Ă���B�����ăR�g�^�}�̊�Ƃ��Ă̓��I���̂̎p�����Ƃ�A����z����Ƃ�����莞����Y�ݏo���A�s���A�i�����̂Ȃ��ɛ������Ă���B���̎p�͂܂��A�u�Ȃ���ӂ�U(�J�M��)��y(�n���J)�ɂ�����v�����ЂƂ̃R�g�^�}�̊�Ƃ��ẮA�킽���������̃C�m�`���̂��̂̎p�ł͂Ȃ��낤���B
�@�g���������Ɍ���ɂȂ��Ă���A�Ȃ���ӂ�U(�J�M��)��y(�n���J)�ɂ����邱�̖������ƁA�ЂƂ̋�̓I�Ƃ��ẴC�}�E�R�R�Ƃ̊W���́A���܂��A�킽����������ꐸ�_�������ė����Ă��郍�W�b�N�t�B�[���h�ł���B�����ꂸ�ɂ����ƁA���̃��W�b�N�t�B�[���h�̂��ƂɁA�������o�R������x�N�w����e����Ă����B�����āA�����ɑT�ɂ݂���悤�ɁA�����ꐸ�_�̓N���܂ł����Ǝ��̉Ƃ��č炩���Ă���B���̍��̑T�́A�Ñ��x�̒��ۘ_���͉������āA�g�̂����ɂ�����̓I�ȌƖ����Ƃ̋�̓I�W�Ɏ������u����Ă����B����͂܂��A���̑T�̉e�������Ƃ�����R����ɂ��̓����������ɂ�����Ă���B����͒��ۉ������\���@���Ƃ炸�ɁA���n�ɂ��a���ւقǂ����E�ɂ��݂Ƃ����`�ʂ��������@�ł���B�u���v�Ƃ��Ă̘a���ւ�͂�u���v�ł���n��Y�킹�A�`�����܂��A��_�Ȗ��R���c���āA�����ł͂��߂Đ��܂�o�����̍��Ǝ��̖������o�́A����N���O�̂��̔g������̎p���Ƃ�������̖������o�ƗZ�ʂ��Ă���B�U(�J�M��)��y(�n���J)�ɂ����铮�I���̂̔g������́A���ꂪ�O����������ւƂ�����āA�E�ɂ��݂ɂ��R���̖������o�ƂȂ����B���̖������o�ɂ��̂�킹�Ă������o�́A�a�̂ɂ����Ă݂���̗�͂�����ł��E����B���̓K��͐��s�ł��낤�B
�@
�s���Ȃ��@���ɐS�́@���ݐ��݂�
�@�@ �ʂĂ͂����ɂ��@�Ȃ�ނƂ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�ƏW
�@���̉̂ɂ͂��炢�Ă�����̂́A�B���̏�ł͂Ȃ��B���������㐸�_�����W�b�N�t�B�[���h�Ƃ����A���̔g���������Ɍ���ɂȂ��Ă�����̂Ƃ��Ȃ��A�Ȃ���ӂ�U(�J�M��)��y(�n���J)�ɂ����閳�����o�B�����ւƂ��̂�����A���R�䂦�ɂ����C�}�E�R�R���i���ł���Ɠ��I�Ɋ��������Ƃ���̃p���h�L�V�J���Ȋ���̏�ł���B���ꂪ�A�u�ȁE��E�ށE�ƁE���E��E�ށv�ƌ����ׂɂ悭�����o�łĂ���B�������ĐS�ׂ��̂Ȃ�ނƂ���ނł͂Ȃ��A����������낱�т̂Ȃ�ނƂ���ނł���B
�@
�������Ȑ��ʂւ��̂𐂒������������Ƃ��A���̗����_��S�~�Ƃ��鐅�́A�u�ԓI�ɕ\�ʒ��͂Əd�͂���J������A�����ŁA�͂��炸���A�݂�����̋��ɂ̋��̂̎p�����߂ĝ��˗x��B���̏u�Ԃ́A���̂��̂��̎p�𗯂߂��p�B����Ȍ��������܂��A������邩������Ȃ��B
�@�@�@�@�O�A
�@ ���������ʘ_���Ɖi�����̘_���̂��Ƃɂ́u�����Ɖ���̘_���v���͂��炭�B����͕��̍�ƌ��ꂩ��݂��ꍇ�u�~���E�ʂ��E�@���E�܂�E�����E�Ȃ��E�ڂ��E�Ԃ��E�u���E�Q��E�P��E����E�@��E��E����E�ڂ��E�łE�E�����E�����E�ςށE���ށE�����E���E�~���E�Ă��E�E�E�v�Ƃ����u�`�D�v�ŏI����\�I�ߊ�{��������āA���邢�́u�āE�ɁE���E�́v�ŕ�݁A�u���v�łЂт����A�҂�����̓I�Ȃ͂��炫�����ɉ����Đ���u���Ɓv�̘_���ł���B���������̂܂܋�̓I�Ȍ��ݔ��p�̊j�Ɛ����A�u�܂��E������A�Ђ���E�݂��A�����E�����A��i�����j�E���i���j�A�����āE����v�ȂǂŐg�̂����Ɍ�����������Ƃ́A�������邱�Ƃŋp���āA���Ǝ҂Ƃ̌����݂�������A�����i���ւƉ�������ƂƂȂ�B�Ȃɂ�������́A���̐��킪������_���ł���B
�@
�������邱�ƂŁu���v���p���ĉ�������B�����Ă���Ƃ����͂��炫�����݂���B�܂��邢�y�U���Ɍ����Ă������o��������悤�ɁA�u���Ɓv�ɂ��Ȃ��K�͂��u���v�֓K�p����B��������ƕs���R�ł͂Ȃ��t�ɁA�����Ȏ��R�������܂�łĂ���B�܂��A���̂͂��炫�͈ȉ��̂悤�ɑ��l�ȓW�J�͂������Ă���B���̂ЂƂ��u�J��{�Ԃ��v�Ƃ��������s�ׂł���B�����Y���̂悤�ɁA�ǂ̎���낤�����̐ؒf�ʂ���͓����K�͂̂��Ƃɐ����������t�H�������p������킷�J��Ԃ��̘_���W�J�B���̑�\�Ⴊ�ꕶ�y��ł���B�ꖜ�N���āA�i�ŋ߂̍l�Êw�̐��ʂɂ��Γ��{�ł́A���ӑ����ɐ�삯��16000�N�܂�����{�i�I�Ȓ�Z�������͂��܂����Ƃ���-���ђB�v���j������A�ꕶ���_�̌����͂����Ƒk��\���͂���B�Ƃɂ����قƂ�NjC�̉����Ȃ�悤�Ȑ̂���A�p��������ς����ɁA�����ꕶ�̎{���ꂽ�y������葱���A�g�������邱�ƁB���̌J��Ԃ��̂Ȃ��ɁA�P�����ł͂Ȃ��A���͂䂽���Ȍo���ƊJ���������ݏo����Ă���̂��B�����ЂƂ̃T���v�������t�̂Ƃ�����r���p����Ă���a�̂⌻��ɂ�����o��̒�^�ł���B���̒�^��s���R�Ɗ�����̐l�E�o�l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��͂����B���̔��肪���邩�玩�R�����A�����Ă܂�ɂ́A�i���ւ̎Q�����܂œ��邱�Ƃ��\�ƂȂ�B�Ƃ����܌��㊴�o�ŕs��`�̉́E�o������݂��邪��^�̋����K�͗͂̂܂��ɂ͍��܂��邵���Ȃ��������A���ꂩ��������ł��낤�B�����̗�͂܂��ɁA�u���v�����āu���Ƃv�ɕ\���ւ̔��肪���邱�Ƃł����āA�p���āA���R���l���ł���Ƃ�����ꐸ�_�̃A�v���I���Ȗ@�̂͂��炫���킽���������̐S���̊�w�ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ����Ă�����̂��B
�@
�ꖜ�Z��N�O�ł��낤�ƁA����ł��낤�ƁA�l�͎��R�����Ƃ߂Ă�܂Ȃ��B�Ⴆ�A�y��\�ʂɁA�G��`�����ƂŎ��R�����B������A���ꂪ�܂��_�ӂɒʂ�����̂Ȃ�A�Ñ�l�Ƃ����ǁA����l�Ƃ����Ȃ��̂��B��������ƖL�����k���Ȏv�l�����A���m�ȍ�Ƃ��Ȃ����Ă����̂�����A�G��`�����炢�̂��Ƃ́A�Ƃ����ɂ���Ă̂��Ă����͂����B�������A����������̌��ꐸ�_�́A�퐶�܂ł̈ꖜ�N�ȏ�ɂ킽�萢�E��Ώۉ����ăC���[�W�֎����������Ƃ���U�f��f����A�����ŕ`���Ƃ������グ�ɂȂ��钊�ۉ�-���邪�܂܂̂��̂̋P�������������Ă��܂���q���̐ݒ�����o�I�ɋ֊����āA�����őS�̓I�����̐��N����@�ɏ]���A�`���Ȃ��ł����B�y��Ƃ�����O�����邪�A�C���[�W�\�����ꂽ�y��̑����͔j�邱�Ƃ�O��ɐ��삳�ꂽ�A�ے�̂��߂̑��݂ł���B���̔j��ɍۂ��Ă͍��J�I�Ȋe��Ӗ������^����Ă������낤�B�������A�����ł͂��̍��J�̂������Ӗ��͈���Ȃ��B�Ȃɂ��s���ł���B�������āA�������J�w�i���̂��̂��A�`�ʂ��߂��錾�ꐸ�_���̂��̂��A�����ɓI���i���āA�J���g�ɂȂ��炦��Ȃ�A���̐��_�̐挱�I�`�����̂̂͂��炫���A���݂̕�ꌾ�ꐸ�_���@��N�����Ȃ��畨�ɂ����āA���I�ȉ�Ƃ����Ă����B���ؐ��ɂ��̖{����u���ߑ�w��̋ߎ��l�I�Ƃ͈قȂ�A���̔\���I�𖾂Ƃ������ׂ���Ƃ́A���S�ŋq�ϓI�Ȋm�肪�\�ƂȂ�B�Ȃ�ƂȂ�A���̍�Ǝ��̂���ꌾ�ꐸ�_�̂͂��炫�ɂ���āA�ߋ��Ɩ����Ƃɂ���ċK��i�����j���ꂽ�����݂��i���̍��ւƉ��������A���R���܂߂��ߋ��Əo��킹�Ă���邩��ł���B���̘_���Ƃ́A�u���ꂽ������������Ђ�������錋�_���܂�ň�������̂����A�ȉ����c�����E�V�����̌����ł����_���Əd�Ȃ��Ă���B�u�E�E�E�i���̉ߋ�����i���̖����ւƉ]�����Ƃ́A�P�ɒ����I�Ɖ]�����Ƃł͂Ȃ��A�i���̍��Ƃ��āA�����܂ł���X�̎n�ł���I�ł���Ɖ]�����ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�V�n�̎n�͍������n�Ƃ���Ƃ��������A��������o�ė���̂ł���B�v�Ȃ��A�Ǝ��̌`�Ԃł��邱�̔g������y��̗ތ^�Ƃ��āA�����ˋN�y�킪���邪�A���̓ˋN�ɕ����ꂽ�l�ʃC���[�W���Ӑ}�I�ɐؒf����Ă���B�ȏ�̂��Ƃ������j���㐸�_�ɕ\���`�ʂւ̋֊����͂��炢�Ă������Ƃ͖��炩�ł��낤�B�����āA���̌Ñ�̂ЂƂтƂ̕`���Ȃ��ł����I�����d�v�ł���B���̈ꖜ�N�ɂ���Ԑςݏd�˂́A����ɁA�����Ė����ɁA�傫�ȈӖ��������Ă���Ƃ�������B
�@
����Ɍ��t���p���ƁA���ɔ����K��-����������-�Ƃ�������̂��ƁA����Ƃ����g�̐���L����u���v�ł����āA�O���Ȃ�u���v�Ƃ������A�����Łu���v�֒�������A�����Ő����A������ꂽ�u���v�́A�Ώی���ł���l�I�������~�g���āA�S�̓I�������l���������̂ƂȂ�B�����]���������āA���́A�^��(�܂���)�R�g�^�}�ւƏ�����ׂ��͂��炭�B���ꂪ�l���C�̔��̂́A�u����(���Ƃ���)�̍�(����)���鍑���^��(�܂���)�����肱���v�̈ӂł��낤�Ǝv����B
�@
���ɂ����Ƃɂ��Y������u���v�ɂ��Ȃ��K�͂��p���A���������B���ꂪ�A�p���ĊJ�������ӂ��i�����̊l���ɂȂ���Ƃ������̎��Ԃ́A���������ǂ��������A�u�����N�[�V�̒�����ސ����Ă���������킩��₷�����낤�B
�@
���ہA�g�̂Ƃ����u���v�Łu���v�ւƂ������Â��A�u���v�ɂ����̋K�́E�@�����o�I�ɔ����K�p�������Ƃ����u���v���@�ɂ��\�������ʂ������Ƃ��A�u���v�́A�Ώۑ��݂ł���d�͂�s���ߐ��Ȃ镨���I���݂̓������������A�܂�~�g����āu�����v�́u���v�Ƃ��ĊJ�����ꂽ���R�̑��݂ƂȂ�B����܂ł̂悻�悻�����͂Ȃ��Ȃ�A�u���v�͓����̔閧���J������Ɏ���B��������ސ�����ƁA�ꕶ�y��ɓ�̖ڂ��J��E�Ԃ��E�����Ƃ����s�ׂ́A�����ł��������Ɖ���̘_���̂��ƁA���̖{���ɒ��������Ƃł������͂����B����Ŕo����u�Ђ˂�v�Ƃ������A�Ђ˂�����̖ڂ킹��s�ׂ́A��͂�u�Q��E�P��E���킷�v�Ȃǂɗމ������u�E�E�E��v�Ƃ����ߓ����ŌĂ�Ă������낤�B
�@
�܂��A�����Ƃ������A���̈Ӗ�����Ƃ���̂ЂƂɂ́u�A�̂����̂����r�܂ʂ��̐l�̂������Q�o�߂̉������߁v�Ƒ��̂ɂ���悤�ɁA�a�̂̋ʑ|�킫�ɓ�����͂��炫���������̂ł͂Ȃ��낤���B����A���������ʂƂ������ۂ��������ƂŐ��E��\�����R�ɂƂǂ߂āA���i���j�ɂ����ĕ��i���j���̂��̂��J���Ă������ƈӎv����ꕶ�̓�̖ڂ̎��R�z���Ȋւ����́A���傤�ǘa�̂�o�~�̒�^�̂Ȃ��ŒB�������z�����ɂ����Ă���B���m�h�̗�������ގ��g�̕\����r����������p�̍�Ǝ��_����ς��ꍇ�A�ꕶ�Ƙa�́E�o�~�Ƃɂ͂��炢�Ă���@�́A�����Ŏ��グ������{�@�̋��ɐ����Ă��邱�Ƃ�����������B�����ʼnʂ����ꂽ����E�͍����̘_����z���͂ł͒ǂ����Ȃ��A��فi���������₵�j���ɂ��ӂꂽ���̂Ђ��߂��������E�ł������ɂ������Ȃ��B
�@�@�@
�@�@����
�@���Ƃ������ꐸ�_�̂��̂������́A�Q�肠�킹�ēꕶ��ɓY�킹����{�̓�̂��Ƃ����̂ł���B��j�E�L�j��т��ĕς��Ȃ����̐��_�́A���E���̏ۂ����A���E���ɑ����āA���݂ɐ��E�ƌW�茋�ڂ��Ƃ��Ă���B�����������Ƃ̂͂��炫���ꕶ�̂��̔g�����������A�����Ď������������u�āA���܍݂�Ђ牼�������肾���Ă����B�����Ă��̌��ꐸ�_�̐��ł���a�́E�o�~�́A�������؎��Ƃ��Ȃ�����A���E��\�ۂ����ۓI�ɒ������ĂĂ��������̔��z�͎���Ă��Ȃ������B�����ƂƂ��Ɏ������܂ꂽ���ۊT�O�́A���߂Ȃǂ̌����ʂł́A����̕��ߌ`�Ԃ�ΏۂƂ��đ����A�T�O�̒蒅�������������悤�Ɍ�����B�������A����͑�߂⏺�a���@�̂Ȃ����Â��̉��߉^�p�Ȃǂɂ݂���悤�ɁA�X�I�ϓ_�ɂ������\�w�ӎ��̂��̂ł����Ȃ������B���̏ꂻ�̏�ŁA�P�ɂ������Ă݂����Ƃ����i���X�}�V�̗��_����݂��^�p�ł������B�{���́A�V�X�e���Ƃ��ċ@�\����T�O�ł͂Ȃ������̂��B����A�킽���������̐S���̊j���Ȃ��a�́E�o�~�ɂ����ĊT�O�͖{���̘_���I�@�\���ʂ������Ƃ͂Ȃ������B
�@����A�A�z�����╧�����_�ɂ��ƂÂ����i���Ƃ��j�v�l�Ƃ������̂��A�����ɕ��E���̂��邪�܂܂̋P����D�������Ă��܂����̂Ȃ̂��A����́A�l���C���u���������ʍ��v�Ǝ��o���A�^�����u�䚠�ɂ̂�㉁i�����j������������v�ƔF�߂Ă������Ƃ�������炩�Ȃ悤�ɁA���ۂƂ����ߑ�T�O�̂Ȃ���������ɂ����Ă��A�悭�d��ꎩ�o����Ă��������ł������B
�@�ЂƂ��ь������ۂ���Ă��܂��ƁA��فi���������₵�j���ɂ��ӂꂽ���E�����E�͌���Ă��Ȃ��B�u���v�̗s���̎ז����Ăɂ����Ȃ�Ȃ��ϔO�̔�����}�����ނ��߂ɁA��j�ȗ��ꖜ�]�N�ɂ킽���̕���̍s�ׂ����Y�킹�Â��Ċl�����Ă����ꕶ�́u���v�̌��B����́A���܂�����[�w�̋����I���ʎ��I�ȋL���Ƃ��Ă��葱���Ă���B���̌�A���炩���Q��Ղ������Ă���́A�����Ă̔S�y�ɑ��闿���Ƃ�����́u���v�։�����P��Y�킹�A�����ɂ܂�鑡���̂̈�U�J�~�ɂ����ꂽ���̂�������҂��ǂނƂ����菇�̓��݂����ɂ��݂���悤�ɁA�Ӗ����e�����A�܂��Ɂu���v�Ƃ��Đ������邩�ǂ����ɔ�d���u����A�u���v�ɂ��u���v�֎Q�^����Ƃ����a�̂╨���W�����Ă����B�����ɊT�O�Ƃ����ϔO�̓���]�n�͂��܂�Ȃ��������낤�B
�@��̌ÕM�́A��������A���������r���Ђ낰�A�V���畨�����Ƃ߁A�����āA�݂Â����]���Č��іڂ������Ă͂܂��قǂ��A���݂ɒn�ւƋ�Ԃ��Ȃ��čs���Ėڂ𗣂��Ԃ��Ȃ����ʑ��l�ȓW�J���݂��Ă���B�a�̂̓��e����łȂ��A���L���ꂽ���������̎p�ɂ���ꐸ�_�̂͂��炫�̌^���݂��B�ꂵ�Ă���B
�@�������Đ�j�֖ڂ�]����ƁA�g���������ɑ�\�����ꕶ��ɕ�����Â��Ă�����̖ڂ̂��̎��R�Ȉ�������B����́A���A�^�Ƃ�������l���敪�̂��ƁA��I�Ɂu���v�֗^���Â��Ă������ꐸ�_�̑c�`�̎p�ł��낤���Ǝv����B���ۉ��̃v���Z�X���o���ɁA-���������āA�f�U�C���Ƃ��ĊϔO��\�������G�╶�l�ł͂Ȃ��A���n���ꂪ���E�Ƃ�����肠���݂�l�A���̈��̖ڂ����̂܂܂����Ƃ�ꂽ���̂��낤�B-
�u�܂���������͗y����j�̉̂̎p�ł͂Ȃ����B���������ʂ��̗́A�t�B�W�J�Ƃ��Ă̘a�́E�A�̂ɂ�������̂��B�v����������A���ߕԂ����̂Ƃ��A�u���v�̎��_�������u���v�Ɓu����v�Ƃ���فi���������₵�j���o�����̂Ȃ��ɏo��킹�Ă����͂Â��B
�@�������u�x��������B�Ԃ����ށB�v�Ƃ����s�ׂ́A���g�ɂ����Ă͌�����p�̒����Ȃ���Ƃł���B
���ŋ߂܂Ő����̑�������Ă����Ƃ�������̌���(�����傤)�����́A�����ň����Ă���ꕶ��ɓY�킹����̈Ӗ�����Ƃ���Ƃ́A�܂������W���Ȃ��B�ꕶ���͒P�Ȃ郁�b�Z�[�W�̊o���ł���A����ȏ�̕��ՓI�ȃV�X�e���Ƃ��Ă̕����̈Ӗ��͂����Ă��Ȃ��B����́A���������ȑO���炠�����Ƃ����Ǖ��I�ȕ����W�c�̓��������ɂ������邱�Ƃ��B���̑��݂�S�ے肷����̂ł͂Ȃ����A�����Ă��̕������V�X�e��������Ă����Ƃ��Ă��A���������ʂ��Ƃɓ����������ꐸ�_�ɏƂ炵���ꍇ�A�u㉁i�����j������������v���Ƃ��ւ�ɂ���S����������炩�Ȃ悤�ɁA��{�I�ɒ��ی����ɂ��㉁i�����j�������̐���͊��ނׂ��Ƃ����K�͂��͂��炢���͂��ŁA��͂肱�̗̕����ƌĂԂׂ��ł͂Ȃ��ƍl����B�����̓��L�́A�Ǝ������ƊȒP�ȕ��@��n�삵�āA�L�q���Ă������������������A����ɋ߂��B������������ړI�ƋǕ��p�@�̗�O�ł����Ȃ����낤�B
���u�x��������B�����Ē��ߕԂ��B�v���̍s�ׂ��Ӗ�����Ƃ���̂��̂́A�m�Ԃɂ������E���ȁE����̐ꎚ�̂͂��炫�Ɠ������̂ł���B�����ł����u������v���Ƃ́A���Ȏ咣�̈Ӗ��ł͂Ȃ��B���ɐG�����ꖞ���������ɂȂ��������Ђ����������邱�Ƃŋp���Ď��ȕ\�o���痣��邱�Ƃ��ł���̂��B�����������ŁA���ɒ��ߕԂ���鎋�_�́A���͂⎩�Ȃ̂��̂ł͂Ȃ��S���I���������Ǝ��̐挱�I�`���Ƃ����ׂ����̂�������������l���C�������u���ƍK���v�Ƃ��������悤�̂Ȃ��u���̎��_�v�ƂȂ��ĕԂ��Ă���B���^�̕��ƁA�����Ă͂��߂ɂ����֓����������҂Ƃ���̉����ʂ����Ē��ߕԂ��A�Ԃ����Ƃ����o�������N�����Ă���̂��B����͂����ւ�ɖL���ŕs�v�c�Ȃ͂��炫���B�s�v�c�����āA���̂ւ�̗��_���͂͂������Ȃ��B�����֓��ݍ��ޖ₢�����͋�����ĂȂ����G�����B���̂ւ�含���N���b�V���������̎��A��������������Ƃ����J���g�̐������̘_���Ƃ͍D�ΏƂ��Ȃ��B�J���g�̗����Ƃ������ی����̂܂��ɑł��̂߂����ich���������̖{���͂����ł���-�Ƃ͂܂�ň�������o���萶�����邻�̕s�v�c�̏o�����B�����邱�ƂŊm���ɏo�����[�w�̋����I�ȋL���̌`��������B�����Ă��̌��`���A�`���܂邲�ƕ��E�����̂Ɍ�点�悤�Ƃ��Ă����̂��W�u���̌�����p�ł���A�܂��A���ނ��Ƃ��J��Ԃ����݁A�u���v�̎��_�����N����܂łЂ����瓥�ݐ邱�ƂŁA�͂��߂��͂��߂镑��������B�u�`����v���ƂŐg�̂̍����Ђ炫�u���v�ɔ����������[�w�̋����I�ȋL���̐挱�I�`���Əo��B�F���i��������j�l�[�~���O�̈Ӗ��������ɂ���B�����Ă܂������̉����ɗL�j�Ɛ�j�Ԃɂ���[���Ɉ�{�̋��������킽����Ƃ��鍡��́u���v�ɂ���Ƃ��ʒu�Â�����B
�@��E�q�̕����ɂ���̌Œ艻�ƑΏۉ�������āA���E���ɑ����Ċւ茋�ڂ��Ƃ��Ă������̐S���X���́A��j�ꕶ�̊�ɔ��킹����̔Q��R�Ɏn�܂�B�����Ĉꖜ�N���o�߂��A�₪�Ė퐶�Ƃ������オ�A�O�����ꐸ�_�����̐��ݏo�������ێv�l�ɂ�鍇���I���Y�V�X�e���������炵���B����̓��^���ł���퐶�y����̓y�t��ł���A���_�Ƃł������B�����Ă̓ꕶ�́A����܂ł̌o�ϊ�ՂƎЉ�\���ɂ������ȕω����������A���܂܂Ő����ɖ������Ȃ���A�����ɕ����̂��邢�͎��Ȃ��ւ点�A���^���E���P������ɓK���Ă�����̐�������͎��Ȃ��Ă��܂����B�������A���̉Ή����y��܂ł��肾�����ꕶ���_�́A�����Ő₦�Ă��܂����킯�ł͂Ȃ��B�퐶�ȍ~�̒��ی����ɂȂ锕���G��E���y�͂�������ꂽ���͎҂̂��̂ɂƂǂ܂������A�命���̏����͏����̗w�▜�t�W�����āA���̌�̍Ôn�y���炤��������悤�ɁA�L�^�ɂ͎c��Ȃ��A�����Âɂ��̂̂��ЙB�ւ�g�̌|�p�ւƌ������Ă����ł��낤�B�ꕶ�ȗ��A�����G�������������Ă����S���ƌ��������ʐ��_�������Ȃ���E�E�E�B
�@ ���E���ϔO�ɗ��Ƃ����ɁA����̂܂܂Ɍ��čs�����Ƃ���ԓx�́A��j�E�L�j��ʂ������̂ł���B����ȐS�������ݏo�����d�g�݁A���u�Ƃ������̂��A�ϔO���ے�̂��߁A�C���[�W�\���̈Ӑ}�I�Ȕj��Ƃ��āA��j���ꐸ�_���Ƃ��Ă����e������s�ׂł���B�����Ă܂��ϔO�����R�̂��Ƃ�����ɔP��グ�āA���ւƂ������A���Ȃ킿�S�y�ւƊւ�A�Ō�ɉ��ō��Ďd�グ��ꕶ��̐�����@���̂ł������B����Ȑ�j�̍H�v�ɑ���A���肾���ꂽ�����ЂƂ̂��̂��u���������ʑ��u�Ƃ��Ă̂Ђ牼���v�ł���B�₪�Ă���͔m�Ԃ̐ꎚ�ɂ܂łȂ����Ă����B�ꎚ�͐����̑��̘_�����_����������y���邱�Ƃɂ���āA���E���ɂ��Ȃ���Ă��鎋�_�ւ̈ړ��𑣂��B�����ł͕��̂���߂����������H�v�ɂ݂��Ă�����j���ꐸ�_�̓������ӂ����эۗ������Ă������ƂƂȂ����B
�@�Ђ牼���Ƃ������݂ɋ�����{�̓���l�����Ă���́A���f�B�A�������Ă̔S�y���玆�ɂ����A�ꕶ��DNA�͘a�́E�A�́E����E�A��E�o�~�łӂ����іڊo�߁A���炩���邱�ƂɂȂ����B��j����̓y�킪�����E���^�Ŕ��ʂ����悤�ɁA57577�Ƃ�����{�ތ^�P�����㎞��̋K�͂̂��ƁA�����̂Ȃ��Ɏ��R�����߂��Ă����B���̐S���X���́A���f�B�A���y�[�p�[����f�W�^�����f�B�A�ɕω����������ɂ����āA2sh�̂悤�ɁA��l�̌^�̑�ʃJ�L�R���ۂ̂Ȃ��ɂ��M���m�邱�Ƃ��ł����B
�@
�@ ������Ƃ킸�A�K�͂̂��Ƃɂ����鎩�R�̖��́A�ǂ̌��ꕶ�����ɂ����낤�B�������A���̌��ꋤ���̑S�̂��A�ꖜ�N�ȏ�ɂ��j��A�T�O�����̂����ʂƂ����K�͂����o���A���܂ȂِS���̊j�ɁA���̋K�͂������������Ă���Ƃ�����́A�ɂ�����ꂽ���������̌��ꕶ�����ȊO�ɂ͎����̒m���Ă��邩����F���ł���B�Ñ㒆���ł́A�A�z�F���̐�ΐ��ɂ�鎩�R�ƋK�̖͂�肪����B���̌��������ۉ�����ĕ��l�ɂȂ������̂��u������Ɏ{���ꂽ�S�C�����b�W�i�g�E�e�c�j���ł���B��������ǂݎ��鎩�R�ƋK�͂Ƃ́A���ׂĂ��V���Ƃ������ی������x�z���Ă���Ƃ����⍓����ȃ��b�Z�[�W�ł��낤�B����ɑ��Đ����ł́A���̐��E�ƌ����ɁA�_�E���B���`���_����D����蒊�ۉ������[���|�C���g�̍\�����_�A���Ȃ킿���l�b�T���X�Ƃ����l�ԉ���^���������炵���`�ʕ\���ɂ����鎩�R�̖�肪����B�ނ炪���̎��R�ƈ��������ɂ������̂������A���i���U�̂��̔��݂̈Ӗ����鐦�S�Œ�m��Ȃ��j�q���Y�����E�ł���B
�@���̃j�q���Y���̒�����ڎw�����j�[�`�F�́A�K���A�D�̓z��Ɏ��R�̖��𓊉e���Ă���B���A���̎��R�Ƃ́A-����������-�Ƃ����K�͂��琶�܂�鎩�R�A����Ƃ�������̂��ʂɎ�e���A�������琶�N����S�̓I�������^���Ă���铮�I�_�C�i�~�b�N���ɗ^��Ƃ��������Ȏ��R�ɂ́A�قlj������̂�����B��q�������\���A�����ŊT�O�_�����\�����鐢�E�̔ނ炪�K�͂̂��Ƃł́A�j�q���Y������̒E�p���͂���Ă����瑆���Â��悤�Ƃ��A���������ʂ��Ƃł��̊�������ۏ��ꂽ���R�̊ݕӂɂ́A�����ē��B�ł����Ȃ��B���[���b�p�Ƃ����K���A�D�̓z��ɂ͏�ɑP���̔ފ݂̂��̂܂��ފ݂ɂ��鎩�R�Ȃ̂ł����B
�@
�㏑��
�@���������㐸�_�ɘ_�������A���̎O�̖@�̊��S�ȉ𖾂́A�t�B�W�J�ƃ��^�t�B�W�J�ɁA�Ƃ�ł��Ȃ��v���������炷���̂Ɨ\�z�����B���������ӂ��Ñ㐸�_�̓Ǝ��_���̑O�ɂ́A��`�q�H�w��F���H�w�̌������ʂ���u���݂͏��ł���v�ƒZ�����ꂪ���ȁA���܂̂킽���������̏��ƃ��A���Ƃ̊W�́A�͂��߂̑����ڂ���̍č\�z�𔗂���ق��Ȃ��Ȃ��Ȃ邾�낤�B������Ӗ��ŁA�Ì�����_�Ԍ�����킽���������̖��������㌾�ꐸ�_�Ƃ������̂́A��̎R�ł���B�������A���j�I�ɂ͂����̖@�͂܂��������R�̂��ƂƂ��āA�v���ł��Ȃ�ł��Ȃ����ӎ��̂��ƂɁA�킽���������̕��i�̕��Ɋ�������Ă������̂��B�܂��A����ɐ[���v���̐��ʂ́A���`�Ȃǂɂ�鐧�ւƔ�`�ɂ���Č��ɂ͂��ꂸ�Ɉ��ɂ̂ݓ`�����Ă�����̂�����͂����B���Ƃ��ƕ��ɂ͂��炭���_�͊T�O�������ނ䂦�ɁA���Չ������_���I��������Ȃ��B�g�̂�}��ɂ��Ȃ���Ύ����ł��Ȃ����i�������Ă���B���̂��ߔ�`�ƂȂ�X���͂�ނȂ��Ƃ��낾���A�����������ɂ͔�`�䂦�ɁA���O�ɂ��₦�Ă��܂������̂��������낤�B������ɂ���A�܌��̂����悤�ɁA���܌Ñ�̘_����q�˂āA���ɂ��Ȃ��@�����o�I�Ɍ��������Ƃ��K�v�ł���B���ꂪ���̂܂��R�Ȋw��Љ�Ȋw�̊v���ƂȂ��Ă��܂����炢�ɁA�Ñ㐸�_�̓Ǝ��_�����Ă��鐢�E�ɂ́A���R�Ȋw���E�������킵�Ă��������̉\������߂��Ă���B
�@�T�O���Ȃ����Đ��鐢�E�Ƃ������̂́A�z���̎Y���ł��A�M�̑Ώۂł��Ȃ��A���܂̂킽�������������{��ŕ�炷���肻�̐S���̍���u���Ă��鐢�E�ł���B���̐S���́A�������Č��݂̍��x�ɓ��B���ꂽ���R�Ȋw���̂�O��������ے肷����̂ł͂Ȃ����낤�B�����������܂߂āA���ɂ��v�����痣��A�����̌��ꐸ�_�Ƀi���X�}�V�����܂ˎv�l�̊댯���A���ɂ��̍��ŊT�O�v�l�����邱�Ƃ̍\���I���ׂ���Ƃ���B���̌X��������邽�߂ɂ��A��j�E�L�j�ɒʒႷ����Ƃ������ꐸ�_�̂͂��炫�����݉����A���̓Ǝ��@���肪����Ƃ��āA����Ȃ���ɂ��v����[�߂Ă������Ƃ��厖���B�����ɂ��̘_�̖{���̖ړI������B���ꂪ�\�ƂȂ�A���̌��ꐸ�_�����Ƃ̍��ق����ȏ�ɖ��m�ɔc���ł��悤�B�����ŁA�����ƌ@�艺�����䂽���Ȏ��Ȏ��g�̎��_����A��ꐸ�_�̒����ƒZ�����\���I�Ɏ���������ŁA���O�̌����������ւ���̓I�ɑΏ�������፷��������Ă����͂����B���ǂ̉�������������A������̋��ɉ��������c�́u���E�V�����̌����v�_����́A�|��T�O�Ƃ������̂́A���ɕ����ׂ��Ƃ��ɁA�T�O�ȏ�̂���ʈӖ��Â�������Ă��܂��Ƃ����T�O�p�@��̍\���I���ׂ����邱�Ƃ����o�ł��Ă��Ȃ��������Ƃ��킩��B�����ɂ�������A��ꌾ�ꐸ�_�̎v�����痣�ꂢ�����Ȃ����������ȗ��̓N�w�̂������Ă������E�_�������Ă���B���������ʍ��ɂ����āA�T�O�v�l�����Ă����ꍇ�ɂ́A�����ŗp���钊�ۊT�O�����Č��ꐸ�_�ɂ��T�O�̖|��Ɠ��l���ƍ��o����Ƃ���ɁA�˂ɗ��Ƃ���������ł���̂ł���B
�@
���{�l�́A���ۓI���ՂɊւ���v�Ҕ\�͂����B�����ɁA������ՓI�K�͂̂��Ƃɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ٗ�ł������Ƃ��A���{��́A���ӎ��̂����ɂ��̂�������{�l�̘_���I�E�Ȋw�I�Ȏv�Ҕ\�͂̔��B��W���Ă���Ƃ������Ƃ͂悭�w�E�����Ƃ���ł���B�����̔ᔻ�͂܂������������Ǝv���B���������ۓI���Ղō\������鐢�E�������B��̑��݂ł��葱����Ƃ���Ȃ�Ƃ��������������E�E�E�B���{��̎v���̂��肩�����C���h�E���āE�����Ƃ��̃x�N�g���̕�����������Ă��邱�Ƃ��l�����Ƃ��A�u�����̘a��������Ďv�z��\������N�w�͂��ɔ��B���Ȃ������B���̍ő�̌����͓��{��ɂ����ẮA���ۖ����̍\���@���m�����Ă��Ȃ���������ł���-�������v�B�Ƃ����ᔻ�́A�������ĕ��̓Ǝ����ւ̎^���̈��Ƃ��ĕ������Ă���B������ɂ��Ă��������Ƃ��āA�����ɉȊw����ł��낤�ƁA�킽���������͕��ɂ��Ȃ�������[���`�J���͗N���Ă��Ȃ��B����ȕ�ꐸ�_���j�ɂ��āA���m�h�║���Ƃ���������p�����B�������n����A�ꖜ�N�̓ꕶ�̐����Ȃ���悤�́A�a�́E�o�~�Ȃǂ��肪����ɂ��Ă��ꂩ��T�������ׂ��ۑ�ł���B
�@�Ñ�̘_����q�˂āA���ɂ͂��炭�̖@�̉�͂ƊJ�����ł���A���܂��͂��̓I����r�����Ă��܂������݂̉��ĕ������������鏔�������̎������A�����ɂ܂������邱�Ƃ��ł������ł���B�܂����肳��͂��߂�����̓��{��̕s�v�c�Ȏd�g�݂̉𖾁B�����āA���̌��ꐸ�_�ƃp�������ȊW�ɂ��錾�������ʍ��ɂ�����t�B�W�J���Ȃ킿�A�킽�������̐g�̂�A�g���������ɑ�\�����u���v�̉𖾁B�����̉�͍�Ƃ́A�ӊO�ɂ�����̎��R�Ȋw�⌾��w�̐�[�e�[�}�Əd�Ȃ��Ă���B�����l����ЂƂ����������Ȃ��Ă���悤�ł���B
�@�����܂ŁA���Ƀ��t�ł͂��������A�g�����������ɂƂ�A��Ɍ�����p�̈ꐧ��ґ��̎��_���疳��������ƕ�������Ƃ̊ԂɈ�{�̋����˂��킽���ׂ��A���҂ɒʒႵ�Ă���Ƃ���������ɂ͂��炭���ꐸ�_�̘_���Ƃ������̂��A�����Ă��̎v���̊j�ƂȂ��Ă����{�̘_�����O�̖@�ɍi�肱��ł����B�w����A�|�p�_����E���Ă��܂����ς̂��邱�̘_�q�́A���ۂ̖{����ɂƂ肩����O�̉��ݍH���ł͂��邪�A�܂��܂��܂�����̃`�J���s���ɂ��s����_�����������A�ߑR�Ƃ���Ȃ������命���ɂ̂ڂ邩�Ƃ�������B���Ɋe��啪��̕��X�ɂ́A�ɂ��ƂÂ����ƒf�̂����������s�����Ȃ������������Ă��܂����͂��ŁA�����͂��̏�������Ă��l�т�����
�@�@���J��@�L�@
YU HASEGAWA
�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@ �@2010.06.14�@
�@�@�@�C���X�V�@2010.08.05
�@�@�@�C���X�V�@2010.09.17
�@
�Q�Ƙ_��/��ΐ^��
�����l�@�u����(�^�})�͍�(�^�})�Ȃ�B��g��(�L�n��)�͋�(�L�n�}��)�ɂĐl�̐��܂ꂵ���Ȃ���ӂ�U(�J�M��)��y(�n���J)�ɂ����Ă�����Ȃ�v
/�@�{���钷�����m�[�g�ƃu���O�@�C�F���E���e���@/�@�u�Ñw���{��̗Z���\���v�ؑ��I�q���@/�@�Ռo�E�q����`
�NjL
���@�ꕶ���āA�����₩�ɔg�ł����������̗D��Ȑ��`�Ԃ́A�ȑO������{�Ǝ��̂��̂��Ƃ����Ă����B
�i���g���A��N�����A�ʌ��Ō��E���{�l�Êw�����̕��w���m�@�e�n�@�O�v���ɂ�������ۂɁA�����ł��̌����Ċm�F�ł����B���N�����⒆���嗤�ł��ŋ߂̔��@�����͐�����A������ӂ܂���ƁA��͂�Ǝ����͊m���Ȃ��̂��낤�j�E�٘_�ł́A���t�W�ɍ��Ղ��c������������̕�ꐸ�_�ɂ��Ǝ��_�����u���v�Ɓu���v�̗��ʂɂ킽���ăp�������ɂ͂��炫�A����ɂ܂Ŏ����Ă���Ƃ������Ƃ��e�[�}�ɂ��Ă���A�����ŌÌ�Ǝ��̃��^�t�B�W�J�ƃt�B�W�J�̃��W�b�N�𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă����B�����œ������_����͓��R�̌��ʂł͂��邪�A�ŐV�̍l�Êw���ʂł����́u�R�g�^�}�v�ɑΉ�����g���������̓Ǝ��`�Ԃ��m�F�����Ƃ������Ƃ͐l���C�̌��������ʍ��̃A�W�A�̂Ȃ��ł̌��ꐸ�_�́u���v�ɂ͂��炭�Ǝ��_�����̎��o���A�����F��(utakura)�̐��_���������Ƃ���Ȃ�A�͂邩��j����́u��v�ɂ܂œK�p�ł���Ƃ������Ƃؖʂ���ۏ��Ă��ꂽ�悤�Ȃ��̂ł���A�S�����B
���@�Ƃ���ŁA��͂���{�Ǝ��̌`�Ԃł���Ƃ����Ă�����̂ɁA�g��̋N�������u�Ƃ�N��i�Ă�ނ���j�v�Ƃ��������̓Ǝ��`�Ԃ�����B�_�`�̉�����������Ƌ{�̎l�������̉����ȂǓ`���I�_�Е��t�̉�����A�܂������Ɛg�߂ȂƂ���ł���l�Ԃ�K���̉����ɂ܂Ō����邱�Ƃ��ł���B
�@���́u�Ƃ�N��i�Ă�ނ���j�v�́A�W�u���̂܂��������ĂȂ����@�ł͂��邪�A���܂܂ʼnE�ɂ݂Ă����A�g���������ɂ͂��炭��ꐸ�_�́u�������v�ɔ����i�����̋��̘_�����A���̉����̌`�Ԃɂ܂Ŕ������Ă���Ⴞ�Ǝv����B���ꂪ�A�����ł����炩�ɂ�����u�R�g�^�}�v�̃^�}�J�M���Ƃ������ɂ̃^�}�́u�C�m�`�v�������e��Ƃ��āA���̂��O�������A���̓���t���ɂ��ė��[�ɔz�����������̉����ɂȂ����̂ł͂Ȃ��낤���B����������̕�ꐸ�_�̂͂��炫���g��̌���������ƂȂ��Ĉȗ��A���ꂪ�����̔g�ł����ƂȂ�ɂ́A���̂ɂ�������a�̂̔��B�ɍ��킹�A�Z�p�Ǝ��o�̗��ʂŁA���z�̊v�V�Z�p�̏K���������A���������ɑ��Ă̘a���l���Ƃ��āA��ꐸ�_�̂͂��炫�̎��o��Α��I�ɉ\�Ƃ������������̔g�̓�����҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤�B�����Ă��܂��A�ЂƂтƂ́u�^�}�V�C�v�̑厖�Ȑ��_�̂��ǂ���ł���`���I�_�Е��t�̉�����A�l�̎��ɗՂ�ŁA�u�~�^�}�v�𑒑������l�Ԃ̉����������Ă���B
���@����ɁA�Ǝ��̌`�Ԃł���Ƃ����Ă���L���Ȃ��̂ɁA�u���ʁv������B���̂̕ό`�������̓Ɠ��̂������������āA���y�L�ɂ́A���Ƒ��z���d�Ȃ荇�����`�Ƃ̋L�q������A�܂��A���ɂȂ�������̂��Ƃ��A�َ��̌`�ł���Ƃ��A�Ƃ������̃��j�[�N�ȕs�v�c�Ȍ`�Ԃ��Ȃɂ��̌`�ɂ��Ƃ��Ă݂悤�Ƃ��邱�Ƃ������B�v����ɂ����̈�ʐ��́A���ʂ͂Ȃɂ��̌`�ۂ�^�������̂ł���A�����ɐ_���ȈӖ���t�^�������̂ł���Ƃ���B�������A����́A���������ʂƂ������̍��̕�ꐸ�_�ɗ���������Ȃ��Ƃ��납�琶�������ԐM�A���邢�́A�����ɂ����Ȃ��B���Â�ɂ��Ă����������ʂƂ������ɂ��Ȃ���{���_�́A�T�O���A�\�ۉ��A�ے��������Ƃ���Ő������A���E������̂܂܁A���I�ȁu���v�Ƃ��Ď�e���悤�Ƃ��Ă����B�����ł̓C���[�W�ɁA���E�����Ƃ����݁A�����^����������������s�ׂƂ������͍̂�ׂƂ��Ă����Ƃ��G���߂���Ƃ��낾�B�Î��L�\�L�ł́A�u�ȋʁv�ƂȂ��Ă���B���������ǐ^���̊����l�́u����(�^�})�͍�(�^�})�Ȃ�B��g��(�L�n��)�͋�(�L�n�}��)�ɂĐl�̐��܂ꂵ���Ȃ���ӂ�U(�J�M��)��y(�n���J)�ɂ����Ă�����Ȃ�v���Q�l�ɂ���ƁA�^�}�Ƃ������S�����ȊU(�J�M��)�ɂ��鋅�̂������ėy(�n���J)�ɂ����Ă����������A���̊U���Ă͗m�Ƃ����݁A�C�}�͏�ɖ��R�ł���B����������䂦�ɂ������āA�ʂ̉i�������ۏ����Ƃ�����ꐸ�_�̃p���h�b�N�X���A��������̂ɂ��Ȃ��ŁA���̂𖢑R�Ƃ����܂܂̂��́u�Ȃ����܁v�̂������ɂȂ����߂��̂ł͂Ȃ��낤���B��x�N�w�ł����u�����̊U������Ƃ��閳����̖@�g�v�Ƃ������͂�s�������Đg�����̎��Ȃ��ϔO�ł͂Ȃ��A�u���܁v�̗]�����̂����A��ΊϔO�̋��̂Ƃ͂����A�u���������ʁv���̍��̓Ǝ��̓��I�ȉi�����̃J�^�`�ɂȂ����Ƃ����ׂ����B
�����@��āA���̂�����̂��Ƃ������E�����Ă݂����B
�u�F���i��������j�v�́A�����������u�̑S�Ăɋ����I���������A���ɁA�����������̎��_���ċN���I�B���̒n������A���{���̓�̍\���𖾂ɒ��ށB
�@�����ŊJ���ꂽ���̌����i�̒n������̓W�]�́A�����́u���ѐ}�����v�̔閧���B�܂��A���{�|�p�j�㎊���ٌ̈`�̌���A���Ԃ́u���q�Ԑ}�����v�����ĔނƓ�����ɐ������m�Ԃ́u���ɕa�Ŗ��͖͌���������v�̋�ɉB���ꂽ�閧���B���̎��]��u�Łv�Ƃ����������ꎚ�̐ꎚ���킽�������̖����֎c�����Ƃ���̏d��ȃ��b�Z�[�W���𖾂��Ă����͂Â��B
----------------------
�@�@�@���ѐ}�����l
----------------------
�Ƃ���ŁA�����́u���ѐ}�����v�ɂ́A��̎��_�ƁA����Ɋ�Â���̂�����̓����Ƃ��Η��������Ȃ��瓯���ɑ��݂��Ă���B���́A�`�ʕ\�����|�Ƃ���R����Ƃ̎��_�Ƃ��̂�����̓����ł���A���́A����Ɛ����ɂ�����ے��������A�\���`�ʂ��������ɁA�p���Đ��E����e���Ă�����Ƃ��鎋�_�Ƃ��̓����ł���B����͌�Ō����Ƃ���̌Ì��i�t���R�g�j�̊��͂��͂��炢�Ă��鎋�_�ł���B���̓�̎��_�Ɠ�̂�����̓����Ƃ������܂�A�͂��߂āu���ѐ}�����v�͎R�����z�����R���Ƃ��ē��{�G��j�㎊���̍�i�ƂȂ蓾�Ă���̂ł���B�������Č��݂̂킽�������͖��ӎ����ɂ��̑Η��������Ƃ�A�����_���n�肾�����ʉ��̌����Ȃ��ٔ��̃h���}�ɁA���܂����āA����p���ē��{�̌����i�����߂��Ă��邢�܂����炱���A������Ȃ��S�Ђ������Ă���̂ł���B�����������̍ō������̋Z�ʂ��������R����Ɠ������A�ЂƂ�̐��n��ƂƂ��ĕ\���`�ʂ̕M���������Ŏ~�ߓ��邾�낤���H�����ċt�ɁA�\��������Ì��i�t���R�g�j�ɐg���䂾�˂Ă������Ƃ��ł��邾�낤���H���̑S���������������̂�������ЂƂ�̐S�g�ł����Ƃ߁A�����ɓ������邱�Ƃ́A�G�`���̖{�\�Ƃ��ĕs�\�ɋ߂����Ƃł͂Ȃ��낤���B
���Ƃ��ƁA�����͈ȉ��ł����Ƃ���̕`�ʂ�{���Ƃ���u��������v�ɂ��ƂÂ������_����������Ƃł���B�ނɂ́A��M���炢�̎R����̓`���I���������E���邱�Ƃ́A�����I�ɕs�\�ł��������A���̎��������E�̈Ӑ}�����o���K�v���Ȃ������B�\���ɂ����铙���̂����Ȃ��T�����_�͓Ǝ��̂��̂Ƃ��Ă��A�\�����̂��̂̂�����܂ł��^���A���������E���悤�Ƃ͍l���Ă��Ȃ������͂����B����́A�݂Â���u��M�ܑ�v�����F���Ă������Ƃ�����A�܂��u���ѐ}�����v�O��̍�i��L�^�����ǂ�A�����炩�ł��낤�B
�\�����z�����\���Ƃ��āu���ѐ}�����v�����̏\���ɖ������ꂽ����ɓ��B����ɂ́A���炩�̗��R�ŎR���`�ʂƂ��Ė����̌�ɁA�i�Ƃ�����A���o���҂w�i�Ƃ��������˂Ȃ����̕��u���ꂽ���₤�����A�p���āA����J���A�����ցA�킽����������A�����鎖�ۂ��Ăэ��݁A�����Ƃ炵�����Ă����͂��炫�Ƃ��č�p���Ă���j�����ł悵�Ƃ����_�Ȃ����ЂƂ̎��o�I�����ɂ���i�E�c�j����҂K�v���������B��͂�A�����ɋ����I�Ȗ����̑��݂̊֗^�A�����ЂƂ̎��_-�u�t���R�g�Ƃ��Ă̑�ꌾ��v�ɂ�鎋�_���������҂̊֗^��ݒ肷��̂��Ó��ł���B�i�����ł́A�㐢�ɉ������Ɏd���Ē������Ƃ������ӋZ�p�̖��͏��O���Ă���j�B
��������͑z���ł����Ȃ����A�����։�݂�����i�E�c�j�̎��_�́A�`�ʂ��|�Ƃ����Ƃ̂��̂ł͂Ȃ��������낤�B���Ԃ�f�p�Ȏ��_�A�����Â邱�ƂŃg�|�X�Ƃ��邱�Ƃɒ����������Ȃ��E�l�I�Ȏ��_�ɁA���Y�D���̐_�̂܂Ȃ������h�������ʂ̂��̂ł��낤�Ǝv����B
�]���̔��p��]�Łu���ѐ}�����v�̂��̊�ՓI�ȍ�i�̕�����������O�O�ɒǂ����Ƃ߂悤�Ƃ��A�t���R�g�̊J�����̌����i�A�̕\���`�ʂ��^�u�[�Ƃ��������������̎��_�A����ɐl���C�̂����u���������ʍ��v�̋C�����S�����A�܂�̏ے��ۉ��ɂ��`�ʂ����ւāA���Ȃ����ƂŁA�������ĕ��Ǝ��ɖL���Ɋւ�낤�Ƃ����l�����̋C�����ւ�A�����ɗ������y�Ȃ�����A��������A������l�̍�Ƃ����O�������Ă����Ȃ���A���{���̌����i���_�Ԍ����Ă���Ă��邠�̍�i�̖{���́A��A���̗ڂƂ��āA����������镪�͂����݂Â��Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�������A�u���ѐ}�����v���A�������M�̖����̍�i�𑼂̒N�����A�č\���������̂��Ƃ��Ă����邢�́A�u�����v�Ƃ�����Ǝ��̂����݂̂킽���������̋��\���Ƃ��Ă��A����Ƃ��A���̍�i�̉��l�͏��������Ȃ��Ȃ����낤�B
�������炪�{�_�̖{�|�ƂȂ�B
�܂��A��̓I�ɁA�����\�N�́u���J�쓙���W�v�ɂ������Î҂ƁA�ϋq�̊��z�A�����Ă���܂ł̎��҂̊��z���E���o���Ă݂悤�B
�u�u���Â����v���邢�́u����炩���v���A�s�v�c�Ȑ_�鐫�ƂȂ��āA�����ɂ����킸�������܂�Ă��܂��v
�u�\�o�̏������`�[�t�ɂ����ł��낤���̌��i�ɁA�����̂悫�����҂ł��������x�����Q�������Ƃ�A���q�������Ȃ��Ă��܂��������̓����̔߈����݂Ƃ߂�v
�u��u�̑̌����i���ɂƂǂ߂��悤�ȁA�Â܂�Ԃ������i�́A�ނ̔ӔN�̐�ΓI�Ȗ��̋��n���B�����ɁA���x�Ɠ���́u��сE�H���v�̐��_��������v
�u���{�I�ŖL���ȏ������Ă��邱�̏��ѐ}�����́A��a�G�`���̃��`�[�t�ł��������тƁA�����̖q殂̋Z�@�Ƃ������т������ʁA�������n�̖͕�̈�ł͂Ȃ����S�Ɏ��Ȃ̉敗�Ɏ�荞�ނ��Ƃɐ������Ă���B�v
�u�����̑O�ɗ��ƁA���т��������������ۂɗ���Ă���悤�Ɍ����A���̂ڂ����̂��������ߊ��Ƒ�_�ȗ]���ɂ���A�ɂ��ݏo�����������Ă��܂��B�v
�������A�ق�Ƃ��ɕ��}�����ƁA���ѐ}�����͓�����҂̎�ɂȂ���̂Ȃ̂��B�N�����^��Ɏv���قǁA�����ԍ�i�Q�̂Ȃ��Łu���ѐ}�����v�����͍�i�̈�A�̗���̂Ȃ��ɁA�ٗl�Ɉ�E���Ă��܂��Ă���B���{�̑S�|�p�j�̂Ȃ��ł���E���Ă����i�ł��邪�E�E�E�B���������{��Ȃ̂����}�Ȃ̂��킩���Ă��Ȃ��B�����G�����G�����s�����B�����Ăǂ��炪�E�ǂō��ǂȂ̂��B�a���̌p���ڂƍ\���̂Ȃ��̏��̕s���R�Ȑ���B�����̐�R�̈Ӗ��A�����Ȃ������w�i�����̂܂ܕ��u�����悤�ɂ݂���S�̂��������̈�ہB�����͂ǂ��Ȃ̂��B�{���ɓ����̐^�M�Ȃ̂��낤���B�����Ŏ�Î҂́A���̓��ꐫ���������W���̌����߂ɁA����ŋ߂݂������u�������ѐ}�����v�Ɓu�w���}�����v��p�ӂ����B�u�������ѐ}�����v�́A�u���ѐ}�����v�Ƃ�������ł���B�ǂ��������剺�̂��ꂩ���u���ѐ}�����v�ɐ^���č쐬�����炵���B����A�u�w���}�����v�̂ق��́A�ꉞ�A������Ƃ���Ă���B�m���ɉ�ʂ̋̂Ƃ肩���A�[�ł��܂�w�̂ڂ����ƁA���̏d�Ȃ���̂��肩���́A���̌�́u���ѐ}�����v�̏��̂����炢���A��Ԃ̂Ƃ肩���Ɍq�����Ă����悤�Ɍ�����B�����ĂȂɂ��i�i������B�������A�w���}�����̂ق��͍��L�ɋL�������A�̖��ɂ��Ȃ��Ă���O�ւ̞w�����r�a�̂��撆�ɂ���i�����̔\�M�ƁE�߉q�M���i���̂��E�̂Ԃ����j�̊��|�Ƃ����j�A��i�Ƃ��Ă̊�������ۂ��Ă���B
�@�͂��R
��ӂ�������� ��ǂƂւ�
�@�@�@�@�@ �O�ւ̞w���� �H�����ӂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���@�t
��
���ŁA���ڂ��ׂ��́A ���́u�w���}�����v�ɂ����ẮA���̉撆�̉̂̎O�ւ̞w���Ƃ������Ƃ��͂Ԃ��A�����āA���̞w�̌��𐅖n�ŕ\�������Ƃ��B�����Ԃ����ȃR���{���[�V�����\���ɂȂ��Ă���B���łɎO�ւ̞w�����r�l���C�̉̂������Ă����B
�Û�
�@�L訐l�� �@�@�ᓙ��
���ɂ��ւ� �@���肯�ނЂƂ� �@�������Ƃ�
��a�T�O���� �@�}���܌� �@
�݂�̂Ђ�� �@���������肯��
�g��V
�@�ߋ��l�V �@��s��
�䂭���͂� �@�����ɂ��ЂƂ� �@������˂�
���\�� �@�O�a�V�O���� �@
����Ԃꂽ�Ă� �@�݂�̂Ђ�� �@
���g�V
�@�R���� �@�����V
�����Ђ��� �@��܂��������� �@�܂��ނ���
�؎u�T�q���� �@�O�ᗎ�� �@
�����̂��܂� �@�݂䂫�ӂ肭�� �@
�����V
�@�O���і� �@�_����
�܂��ނ��� �@�Ђ�����܂� �@������˂�
�q���V���R �@���ᗬ �@
���܂������ �@����䂫�Ȃ��� �@
�E�E�E�E�E�E�J�L�J�P�@�ȉ��͖�����
�����ѐ}�̕`�@�ɂ��ā@�傽�鏼��`���ɂ������Ă͘m�M���p�����������Ă���Ƃ̎w�E�����҂��炠��B�܂��A���̎�@�́A��ɖv���`�i�֊s����p���Ȃ��j�Ɲ��n�i�͂ڂ��j�Ƃ����Ċ��M�i�M���C��t�����@�j�ł���B
����ɖn�́u�ɂ��݁v��u�ڂ����v�̋Z�@�Ɨ]���ō\������Ă���B
���Ƃ������������ŋɗ͕\���`�ʂ��������A����`���ɂ������Ă̓�����ʏ�̕`�ʂɂ����M�ł͂Ȃ��A�m�M��p�����B���Ƃ������ە`�ʂ��������������̂��B�����āA���̑傫���͍�҂��g�̂Ƃ�����̐��ł�������Ă����ɂӂ��킵���X�P�[���ł���B�����ŁA�̂Ƃ������ŁA�S�g�Ŋi�����A�n�ƕM�Ƃ����u���v�ŁA���Ƃ������ւ������������B���̂Ȃ��̓��{�I�Ȗ������ƁA�����ɂ����鑶�ݎ҂̉i�����A�L�������e�[�}�Ƃ��Ȃ���B����ȍ�Ɖ�����ݒ肵�Ă݂�B
���@�@���̂Ȃ��̓ꕶ�̂悤�ȃ��t�Ŗ��\��Ȗn����ŋɗ͕\���`�ʂ�r���Ă���B�������ɁA�R�����`�ʂ��ꂽ��ǂ����낤�B�䖳�����B
���@�@�ڂ����E�ɂ��݂ɂ�閶�ʼni�����@������������킵�Ă���B
���@�@���̌܁E�Z�{�̌Q��̌J��Ԃɂ��䂽�����B���̂��̉��̋�ԂƓ��I�ȊJ���߂̏d�Ȃ�ɂ������������̂��B
���@�@���̖��͂��A���肳�ꂽ�����Ƃ������ɂł͂Ȃ��A��Î҂Ɗϋq�̊����̎d�����獀�ڏo��������B��������ƁA�܂�A���̉��G���̂͊��S�ȕ`�ʂ����ʁi�����Ŗ����ɂ݂���j���炱���A�u���b�N�{�b�N�X�ƂȂ�A�l�X�̎��_��U���Ă��邱�Ƃ����m�ɂȂ��Ă���B����ɁA���̏��ѐ}���オ�ǂ�Ȋ��҂����߂Ă݂Ă���̂��A�����͂���B
�N���C�A���g�̗v����y�U�ɂ��āA�`�ʂ����ʁA�����������ʂƂ����@���Č����邽�߂̍H�v�B���ꂪ��̂ƂȂ鏼�̓����ł���B���̂��߂̈��̕��ւƂȂ������тł���B
���ꂪ�A���̈Ӗ���Y�����邩�̂悤�ɁA���ւĕ`�ʂɂ͓K���Ȃ��m�M�Řa�����C��A���˂����A�܂�œꕶ�̓�ڂ̂悤�Ȗn�̐Ֆڂł���B�B
������A����́A�E�E�E�B
����a�G�̓`�����Ђ����Ƃ���Ă��̏��́A���Ƃ�������̂��ƂŁA�܂��A���̓���ے肵�A���ۉ���j��i��������j�������ʂ����Ă���B���������āA���̏��͕`�ʂ��ꂽ���ł͂Ȃ��A�`�ʂ����ۂ��鏼�ł���B�`���I�l���}�̂��̏��̗�͂��̂���p�^�[���G�Ƃ͂ǂ������{���_������Ă��������B�Ӗ����̂Ȃ����̎l�ܖ{�̌Q�ꂪ���̂Ȃ��ɗ��ꗣ��ɗ����Ă���B���݂��̌Q��͊W����悤�ł��āA�Ȃ��悤�ł�����A�����ȊW���B���̌Q�ꎩ�̂͂��ׂċ�ւЂ炢���O�p���̌`�Ԃł���A���Z�W�ɂ�鉓�߂��ӎ�����Ď�O�͔Z�n�̂͂������Ֆڂ��A�L�������킳���A��C�ɂ��̂ɂ��ꂽ���̂ł��邱�Ƃ���Ă���B����ɁA�O�p���̂��ꂼ��̏��т�����̎p�ɂ���������B��O�̏��͂ǂ���r���A��a�G�̕l���}�ɂ���悤�ȏ��̗D���_�����̃C���[�W�����ۂ��Ă���悤���B�킽������������ʂɈ�������āA��������������̂̎��_�����ۂ��Ȃ��B�����ł́A���͂��҂͂������Ȗ��ł͂Ȃ��B���������㐸�_�����W�b�N�t�B�[���h�Ƃ��Ȃ���A�O�����ł̕`�ʂ��^�u�[�Ƃ����ꕶ�̂��̂���������ϊ��������ދH�ȗ�ł͂Ȃ��낤���B�����āA����ȏ�ɈӖ�������̂́A�������������𖢑R�Ƃ��邱�ƂŁA�������ĉi������������Ƃ����p���h�b�N�X�ɂ킽���������A�C�}��������Ȃ�������䂫�����Ă���Ƃ��������ł���B
�Q�Q�Q�Q�ȏ㖢�����B
�i����ɂÂ��{�_��2010 .12�� �ɒE�e�\��j
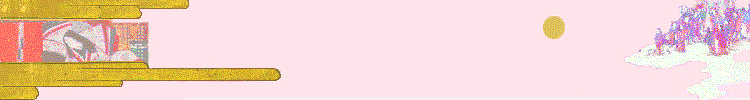
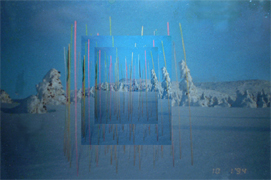
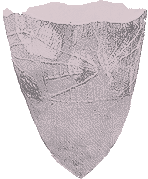 �@�@�@�@
�@
�@�@�@�@
�@ �@�@
�@�@