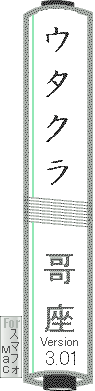
言挙げせぬ国の
|
|
|
|
ウタクラ 目録
|
| |
遥かな先史より、わたくしたちには大陸でいう空間や時間は欠落している。時間や文法など普遍化された概念やそこではたらく論理法則は、すべて抽象座標軸を前提とした大陸思考からの借物である。代って昔も今もわたくしたちの物のみかたには或る共通の基本軸が存在する。それは「つらぬく棒のごときもの」としか喩えようがなく、抽象をきらい普遍化できない特徴をもっている。ここでは、この地軸がてらし出すサダマリを言と物の双方にわたり事例をあげて検証した。
いま、この基本軸にそって歴史的パラダイムシフトが起きかけている。それは単に、科学・政治・経済上のことだけではない。近代の基準にしてきた大陸の普遍的思想から、わたくしたちの内なるものの見方や感じ方への枠組みそのものの見直しである。そこで「物」や「言」との古くてあたらしい関係が結び直されようとしている。これまで漢字文化を受容して以来、直訳大陸文化から仮名、真名併用という現代文字文化につながった「言」をめぐる文字文化変遷が第一回目の直訳大陸文化からの内的パラダイムシフトであったとすれば、今次二回目は現代美術や舞踏といったごくありふれた日常の創作現場からはじまった「物」をめぐるパラダイムシフトである。それは、欧米抽象思考による物質化された対象物と、わたくしたちの「物」への感受性とのハザマで美術家や舞踏家の不連続感が臨界を迎へたことによる。今回の「物」をめぐり列島独自の時空間の枠組みに直に触れようとするこのムーブメントは、近代主義の超克といったレベルにとどまらず、311を機に、従来思考の基底からの問い直しも含め、遥か無文字時代の心性の核にまでシフトし得る可能性がある。
本論
はじめに
ここで論じる「物と物質 - 或る思考実験」とは、表題をみるかぎり、哲学か、物理学のようであり、内容も重いものではないかと敬遠されそうである。しかし、ほんとうのところは、そんな理屈ばったものではなく、現代人ならだれでもふと感じてしまう「絵や彫刻やダンス」の意味とは、それはまた「短歌や俳句、詩」をつくることとはどこか違うのだろうか。そしてその根底にある「ことば」とか「もの」とはいったいなになのか。そんな単純素朴な疑問から発した自問自答にちかい推論である。しかし、一+一=二の意味とその証明には少々回り道した定義立てと方程式が必要なように、あまりに単純なところが難しく、そんな説明に手間取っているうちに少々ヘビーなものになってしまった。ともかく「この列島で表現するとはいったいどういう意味をもっているのだろうか。哥座(うたくら)冒頭で掲げたように、もしもほんとうに、わたくしたちが、いまもって大陸でいうところの時間や空間、そして主観とか客観とか、そうした基本的で普遍的な概念が成立する自立的座標系をもっていないのだとしたら、理性や悟性にもとづくとされてきた学問の系譜や感性を媒介にした主体としてのわたくしたちの表現活動はどうやって可能となってくるのか。しかし、古来より優れた和歌や立派な物語、水墨画、庭園芸術、能狂言の伝統もあるではないか。現在も造形芸術や舞台芸術、短歌や現代小説や国際的に高く評価される文芸・芸術の和洋両面にわたる表現活動は盛んである。ことさら座標系の違いなど持ち出さずとも、そこで感じたままをことばにし、造形し、あるいは、そんな描写表現された作品を素直にうけとめればいいのではないか。まして自然科学や社会科学という学問の成果ぬきに日常の暮らしは考えることさえできないはずだ」ところが、どうも通り一遍のそんなことではすまない事情が、この列島の「ことば」と「もの」にまつわることがらにありそうなのである。
そこでまづ、すこし長くなるけれど、小林秀雄の「本居宣長」から古事記成立に関する部分引用からはじめる。「漢字の渡来以来、日本人は「言傅へ」と「書傅へ」との間に、訓讀という橋を架して往来せざるを得なかったのだが、この経験の不自然な性質については・・・記紀の時代には、訓讀といえば、それは外国語の特殊な学習法であり、当時の知識人は、この極めて知的な手段による新知識の獲得に多忙であった。これにかまけていたから訓讀という橋を渡ってみてはじめて、彼我の言語構造を隔てる断絶が、はっきりして来たという裏面の経験は容易に意識に上らなかった。その代り、この不安が一たん意識されると、自国のことばの伝統的な姿が鋭く目覚めたに違いなく、この意識が天武天皇の修史の着想の中核をなすものであった(天皇の哀しみには、感傷も懐古趣味もありはしなかっただろう。本質的に歌人の感受性から発していた)。當時の知識人の先端を行くと言ってもいい、この尖鋭な国語意識が世上に行われ、俗耳にも親しい、古くからの「言傅へ」と出会ひ、これと共鳴するという事がなかったならば古事記の撰録は行われはしなかった。」「天皇の削偽定實(僞りを削り實(まこと)を定める)といふ歴史認識は、国語による表現の問題に逢着せざるをえなかったのである。・・・そこで太安万侶は、漢字による国語表記の未だ誰も手がけなかった大規模な実験に踏み込んだ。」
この小林秀雄の文章を参考にすると、唐国の漢字文化にたいしての「古事記」撰録とは、あらためて、わたくしたちの「言の地平」に起った、やむにやまれない国語表現の見直しであったことがわかる。それは即ち、政治的な権力統合の神話的意味合いよりも、もちろんそれらと切り離すことはできないにせよ、「言傅へ」で培ってきたわたくしたちの言語精神文化が、唐文化の表記文字を受容したことから訓讀という「書傅へ」文化へと変わってしまい、普段にある言語生活とのギャップ感が増大。このままではわたくしたちのアイデンティティーは失われてしまう。ひとびとの暮らしぶりにも鋭敏であったそんな当時の知識人の危機感から「もの・こと・こころ」への素朴で過激な問い直しに撰録作業の意味の重心が置かれてきた。そうであれば、それら一連の作業とは、わたくしたちの心性の核への内的必然性から起こったパラダイムシフトであったと看做すことができよう。そこで、その「言」をそのまま「物」へと置き換えてみる。すると、戦後の現代美術の先端を行く作業とは、美術ジャンルを越えた、有史以来のわたくしたちの「物の地平」における第二期の内なるパラダイムシフトを起こしているという事実が顕かとなってくる。
飛鳥いらい、わたくしたちは、仏教絵画や、仏像彫刻といわれるもの、そして、唐絵の摂取からはじまって大和絵、山水、水墨画など今日美術といわれるおおくのすぐれた作品や枯山水などをうみだしてきた。そこで、明治になってから大正、昭和初期までの芸術をめぐる環境に小林の古事記成立時のことばをかさね合わせてみると「彼我との空間把握の間にある断絶を、読み替えという橋を架して往来せざるを得なかったのだが、古代は中国や印度・・・明治以降は欧米の抽象座標上の空間造形芸術の摂取に多忙であった。しかし、それは外国語の特殊な学習法と同様の事態でありながら、これまでそれにかまけて、この経験の不自然な性質について、その意味を根本的に問うことはなされてこなかった」のである。せいぜい唐絵を大和絵に、西欧画を日本的洋画へと変様させたくらいであり、もともと表象を忌避してきた先史無文字時代精神に立ち返って、そこから描写とは、この列島で表現するとはどういう意味をもつのかと徹底して自覚的に問いかけることは描写らしい表現が弥生絵に認められてから自分の知る限りにおいて、二千数百年もなかったようだ。その問いかけが始まったのは戦後の吉原治良率いる具体運動を経たモノ派の登場を待たなければならなかった。(弥生以前の縄文における製作物はこの後半であつかったが、大陸系列の表現描写や造型感覚で捉え切ることはできない。)
戦前におけるダダなど反芸術運動も、あくまで欧米芸術運動に基準をおいた限りで受け止められてきたのであり、イメージ表現そのものをみずからの心性のありようから問いかけるには至らなかった。その後、敗戦を契機に欧米のアンフォルメル以降の芸術解体運動の影響のもと、洋画や、そのアンチテーゼとしての日本画を含めた表現そのもののレベルにおける問い直しがようやくにして、はじまってくる。同時に、彼我の空間構造との隔たりのあまりのおおきさ
- それは言語構造を隔てる断絶と同じレベルである - に気付くことになる。この問い直しには、二重の意味が含まれていた。ひとつは、第一次、第二次の大戦の破局を経験した欧州自身の、みづからの近代主義を超克しようとした芸術運動である。それはルネッサンス以降、人間本意主義で進行してきた作品成立過程における一連のプロセスとその関係へのラディカルな問い直しとなった。そこで結果としての作品から制作プロセス自体をも作品とみなされるようになる。その視点は戦後日本の前衛美術家も評論家も即座に輸入した。もうひとつの視点は、ひとたび焦土と化したこの列島で唐絵の摂取以来、うたがうことを知らなかった絵画表現、仏像彫刻などの立体表現を成立させてきた座標系そのものへの問い直しであった。それはすなわち、わたくしたち独自の空間と時間へのやはり過激な見直しにリンクしていかざるをえなかった。あくまで欧米文脈による表現への問い直しをきっかけとしたが、造型概念自体にまでおよぶ表象表現の深層構造にまで降りていったこうした問い直しは、すくなくとも物制作とのかかわりにおいては、この列島の有史以来はじめてではなかっただろうか。
抽象座標上にものごとを再現描写する大陸系表象意識に代わる視点の探求。この過激な問いかけは「対象論理を超えた主客未分化のあるがままの世界の輝き出し」を基本に据えた李禹煥をはじめ、「ものはモデルをもたず、一般化されたらおしまいであり、したがって制作することはできず放置によってながめるほかない」という菅木志雄。また関根伸夫等、おおくの「モノ派」といわれる作家たちの実作作業の基本視点となってきた。かれらの作業視点は、飛鳥以来、天平、桃山文化といえども、あるいは、逆行してみても、弥生絵や古墳壁画以来、この列島の芸術作品といわれてきたものは、例外なくその基盤そのものが、大陸中国や朝鮮半島の、明治以降は欧米の直訳ものか、翻訳ものであり、そこにおいて成立してきた表現は、模倣と、その変容でしかなかったのではないかという過激な気付きに支えられている。
ことに、菅における創作実践者としてのひらめきは、再現性にその本質をもつ大陸の抽象座標系思考の限界性と、同時に列島独自の時空の構造とを直に照射し、彼のことばにおいても逐一、物質と物との彼我の違いが言表化されたものになっており、自身も不思議な気持ちで長年にわたって彼の作品とカタカナ書きが多くまじった、なにげでありながら独特の文体で書き込まれた作品カタログコメントに魅惑されつづけてきたひとりである。そんな彼らの、イメージ表現そのものの可否を問うにいたった視点の発見
- それは「言傅へ」から「書傅へ」表現文化へと変わっていく不安のなか「古事記」撰録に至った視点と同じものである。つまり無文字時代言語精神の視座をふたたび立ち位置として自覚したところからうまれた観方である
- その視点の再発見によりいままさにポストもの派やその他の逆流からうまれた大小の渦をも巻き込んで、さらにおおきな流れとなって「物」にかかわる内的で本格的なパラダイムシフトが起きはじめている。三、一一以降、列島が放射性物質に大量汚染されるというあわただしく困難な日常の裏側にあって、そんな歴史的大事件の基層で、このパラダイムシフトは、しずかに確かなできごととして、今後とも未来のわたくしたちの地軸を形成していくはずである。この事態は現代美術世界の空間問題としてありながら、また「物」の地平に持ち込まれた壮大な実験であるだろう。近い将来「物」に関する古くてあたらしいこの視点の再生は、芸術としての一ジャンルの問題にとどまらず、わたくしたちの言語精神に由来する基本的な存在論的問い直しとして普遍的諸科学の成立基盤さえ相対化していくのではないだろうか。
しかし、これらの動向が(*一)「物」におけるパラダイムシフトを起こしているということを、実作者以外は、いまだ明確に自覚できてはいない。その原因は、先にいったように、この運動は欧米と連動した二重の層を成して発生しており、その二層間で屈折する反射光にかく乱されて、その動向自体が見えやすいものとはいえないからだ。また、特殊な美術界、しかも混迷する現代美術という狭い世帯にいまだとどまった現象であるせいかもしれない。あるいは、彫刻・絵画・映像というジャンルにおいては、趣味判断レベルの意識といえども、ひとたび自我に刷り込まれると、無意識裡に価値化されて、それを払拭することが難しくなる。その点に、それは、「漢意(からごころ)は除き難し」と同様に、あるいはそれ以上に、いちどまとわりついた表象感覚からは自由になりにくいということに帰着する問題なのかもしれない。
ともあれ、すぐれた評論家もいたはずの、当時のあの画期的な「具体運動」でさえも、欧米とパラレルにおこっている抽象表現主義の視点にのみ集約され、その本質は覆われて、運動はたんなる近代主義を超克しようとする欧米と呼応した美術動向のひとつとして片付けられて終息してしまった。また、現在の美術評論世界においても、たとえば自身も敬愛するすぐれた論客のひとり、千葉成夫にあっては「この列島に美術というものは未だない」と言い切る論拠をもち得ながら、モノ派を核としたその後の一連の芸術思潮をポイエーシス(制作)からプラークシス(実践)への動きとみて、従来の欧米座標の物の見方、規範からもうひとつ抜け出せないでいる。具体的作品にそった、かれの誠実な見方が間違っているというのではなく、そこから整理された結論は、そうであるに違いないけれども、実は、その整理の視点は外部からのみたてにすぎなく、その視点のその先で、実作者の方は、自己の身体を軸にできている分だけ、より核心をついた独自の時空間の場をすでにひらき、美術をこえた「物」の地平におけるパラダイムシフトまで喚起していることが作品から直に感じ取れる。そこでつい、ジャンルをこへて、もう一歩踏みこんだ視点からの立論がほしいと、ないものねだりをしてしまうのは決してわたくしひとりではないはずだ。彼の「逸脱する美術」や「類としての美術」「未生の美術」などの用語をみても、また彼以外においても「閉じられた円環の彼方へ」「悪い場所」等々、わたくしたちの空間や時間にたいする切り口のキーワードだけをみても、その生硬な表現が、翻訳概念主体の美術評論世界にあっての視座の限界点なのかと感じざるをえないところである。しかし、問題は、そこでこの内的パラダイムシフトのトレンドが、たんなる近代主義の超克としての運動だと従来どおりに捉えられてしまうと、その潮流の行方はかすんでしまうことだ。そうなると、わたくしたちは、ふたたび外の視点へと引きづりだされるか、その反動としての神秘主義の視座にのみ込まれてしまうほかはなくなり、それこそ椹木がいう「悪い場」として、これまでたびたび繰り返されてきた「閉じられた円環」のパラダイムに堕ちてしまう危険性がある。しかし「閉じられた円環」は外から規定されるほどに内殻を硬く閉ざしてしまうのである。怖ろしくてもいつかみずから内へ飛び込めばその内側とはじつは開いた外側のことであることがわかるであろう
第一章 人麻呂の誇りとアポリアの存在
かの筆頭詩人、人麻呂は、わたくしたちの物のみかたにもともと備わっている否定相の存在に触れて、そのあり様を「言挙げせぬ」ところではたらく物の耀きとして、高い誇りをもって詠いあげている。しかしその後とりわけ戦後は、この否定相の背後に見え隠れしている、すなわちここで作業仮説のキーワードとしている「この列島独自の基本軸」にあたるものは、その存在自体やわたしたちの物のみかたや考え方に及ぼすその積極的な役割や意味が正面からとりあげられることはあまりなかった。むしろどこか避けてきたきらいがある。そしてここで「不理・非象」といっている「言挙げをせず・個人的な表象表現を避ける」その否定相のはたらきこそが、わたくしたちの論理的思考の発展を阻害してきた原因であるとして、その一面のみをもって、その背景に想定されてしかるべき、あるいは、すくなくとも検討されてみてしかるべき地軸としての独自座標の存在とそこにはたらく基本力学も共に全否定されてきた。その傾向が今日まで続いてきている。そのわけは、明治維新や先の大戦をはさんであらゆる価値が逆転したという思想環境にあるというより、この座標自体がもとより抱え込んでいるアポリアなるもの
- そのものとしては対象存在として普遍化できず、論理化も可視化もできない - という独自否定相を伴ったその内部構造の晦渋さに、それを主題とする困難さが常に付きまとい、戦後のみならず、古来よりその時代の気分の物指をあてがって解釈する他なく、あるいは戦前のようにご都合主義に流されてしまった。こうした表層的な解釈に終始せざるをえない扱いにくさがアポリアとして、わたくしたちにもともとそなわっているこの座標系の解析を阻んでいる。
その困難さは小林秀雄のつぎの解釈からもうかがえる。『「言揚げ」はよく議論するという意味に取られているが、「言揚げず」を特に「言にあげてつらふ」と解する理由はあるまい。よく意識された言語表現の意味に解してよいと思ふ』と。なお、「言揚げ」の一般的な解釈は「声をあげて言い立てること」「大言壮語」などを指し、なすべきでないときにすれば、大きな災いを招くとして慎まれた。実際そんな用例で使用されてはいる。
しかし、人麻呂が誇りをもっていう「言揚げせぬ」というこのキーワードはけっして小林がいうような表層的な意識や言表者に帰属するたんなる言いまわしや感情表現の問題で片付けることはできない。もっと深く、物と言とに関わる言語構造の根本問題がそこに潜伏しているはづだ。その左証のひとつが、インド哲学者、中村元の次のことばだ。それは、ここの小論とは正反対の観点から述べられたものではあるけれど、ここに「言挙げせぬ」ことのアポリアが孕む構造が簡潔にまとめられている。『「日本人の非論理的性格は、おのずから論理的整合性のある首尾一貫した思惟作用がはたらかぬようにさせている傾向がある。すでに古代において柿本人麿は「葦原の水穂の国は神ながら言挙げせぬ国」であると詠じている。そこにおいては、普遍的な理法を、個別的な事例をまとめるものとして構成するという思惟がはたらかない。』と。アジア各国の言語精神を対比しつつ、仏教論理の受容時の言語構造に詳しい彼ならではの指摘である。そこで「言挙げせぬ」ことを非論理的性格をもったキーワードとして否定的に受け止めているものの、この分析は、反面、この言辞が、列島言語構造の根本問題を孕んでいることをあきらかにしている。
さらに、ここでこの小論の仮説にもとづき「言挙げ」をこの列島の言語規範から逸脱したことばと物のサダマリに敵対する人間側の行為と解するならば、すなわち「言挙げ」を言や物を列島の地軸から外れた仮想の吾という人間側の主催する座標上へと置き換えたできごとであると見るならば、吾や分節化された対象物やイメージ、それらを統覚する主体、論理のはたらきは、みな仮象であることになり、そこに基づく行為は神威に敵対して、ことばや物に直に触れることから離れてしまう暴走だとみなされる。その先に待受けているものは、現存最古の用例である古事記中巻のヤマトタケルの慢心による言挙げのごとくに悲劇を招来する。
これは、どこか他できいた話に似ている。そう、わたくしたちにもなじみの天上界から人類に災いの火をもたらしたとされるギリシャ神話のプロメテウスのことだ。もし、この小論でのさきほどの読み替えが許されるならば、わたくしたちの「言挙げせぬ」というアポリアは、ハイデッガーが近代技術思想の問題を古代ギリシャ語で読み替えてそこに西欧ニヒリズムからの脱却をもとめようとするテクネー解釈や、そしてその背後に存在している古代ギリシャのコスモス世界が抱えるア・プリオリな構造
- そこでゼノンの数理的なパラドックスとギリシャ悲劇がおしえるアポリア - にまで通底していく問題であるようにおもわれる。
また、人麻呂の韻文がわたくしたちのこころうちに直に訴えかけてくる詩的真実というものがある。それは列島の最大詩人の歌のフレーズ中のこのことばの調べには、抽象化をタブーとする規範のもとに、描写とイメージ化というものを忌避しつづけてきた先史時代言語精神に源をもつ、それこそ原始的な熱き誇りにみちたおもひが集約され、その靭きこゑが聴き取れるという事実である。そのこゑには別掲で詳細した先史時代言語精神のつくりだしてきた尖底土器の器表面を描写表現を再現する支持体とはせずに、描写を明確に避けつづけて這わせたあの縄の眼の制作視点と同種の靭さだ。あの一万年にもおよぶ縄文期の縄の眼の否定の相をもった反復の刻印。あのいともあやしきさだまり方をみせる「イキホヒ」や自在な「フリ」。
それはまた、後述する草間彌生が統合失調という心身を賭けて生き抜くために紡ぐしかなかった「水玉の天文学的な集積が繋ぐ白い虚無の網によって、自らも他者も、宇宙のすべてをオブリタレイト(消去)する」と宣言したあの無辺に反復する虚無の網の「サマ」とも同種の靭さである。そしてこのフリ・サマの靭さをもち来たらせているもの、それこそが詩人として、思想家として、人麻呂に「言揚げせぬ」といわしめた高き誇りのあのアポリアの正体なのではないだろうか。
わたくしたちは、古来より吾や他者や存在事物、そしてあらゆる物言にたいして、それをそこで再現し、うつしだし「仮象する座標を設定しない。」あらゆることばやものごとを「擬似スクリーンに再現描写しない。」「イメージ化せず」、「言挙げせぬ」。そう言い切る否定の意思の靭さと自由を「物のサマ」「言のフリ」として徴シてきた。
-
対象化して普遍化したイメージ表現をせず - その代わりに具体的なこゑや物が連鎖し重なり定まりいくイキホヒある徴シ - その「物のサマ」「言のフリ」を哥座では列島独自の「形相・エイドス」と言い換えているが
- その「形相」が定まりを得て純一化されるそのとき、その形相を地軸として物言の美しき叛乱が始まる-
こうして「物」を表現せずにあるがまま直に輝かしめてきた。特集で詳細しているように列島における「物」「言」「身」の各言語は表現未然の中間言語として具体的な排列の純一化を果たしたそのとき、言表の内側へ表現内容を取り込まない。各言語排列自らが地軸となり、言辞の外側その周縁の無辺無窮のひろがりへ「物事」が継起するよう直に「物」自体が語りだすようにはたらくのである。そこが人麻が誇りとして高く歌い上げた列島言語の最大の特徴である。コンセプトを排して「物」に「物」を附けていく先史縄文の器の制作方法。そしてあの土偶の身体部分の切断やさらに視線の切断としての仮面の構造もまた「切れ字」と同様のはたらき方をして形相としての「物」と「言」の排列式の純化を促して内を外へ裏返し、その外側の無辺で無窮の「物」の世界を輝かしめるための仕組みである。他方、大陸言語精神のおしえるところのように、いったんものごとを座標上に再現して囲い込んでしまうと、言のカガヤキは失せて「いま・ここ」の物のいのちは死んでしまう。
その事態と対照化するため手許のレクラム版からRainer Maria Rilkeの詩の一節を任意に書き抜いてみた。
”Das sind die Stunden, da ich mich finde. Dunkel wellen die Wiesen
im Winde,allen Birken schimmert die Rinde,・・・・・・”
私が 私に出会う そのとき(以下…夕風になびく美しい草原と白樺の描写…)
内容は、白樺の燐光が象徴するような北部ドイツの憂鬱な暗さのなか、自然と詩人との一体化の様の一シーンである。その際に、統覚観察者ichと眺められ客体となった経験主体michとの自我の関係構造は、その場その時における現象としての物事にはたらく理と経験内容とともに切り取られ、あらゆる存在者の舞台としての座標上に一連の関係式として表現され、保持される。そしてこれらジーニアスの創造したコンテンツは随意にイメージとして再現され私たちを感動させる。
ところがそこが大陸系の物事を再現描写する世界とわたくしたちとが決定的に異なるところであると人麻呂は鋭く指摘する。ものごとを再現するフィルターをもってしては活きたままものごとを輝かせることはできない。わたくしたちは存在と時間という抽象概念や定義された一般概念や論理といったもの。そしてそこから構成される世界の表象等々、さらに仮構された自我存在を再現する作業をいっさい忌避することで、ありのままの物事と直に向き合ってきた。そこでこそ物事は過不足なく活きて輝く。しかしこれはどうしたことだ。先進国といわれる唐土は彼らの高度文化をささえる座標へすべての物を一度プロットし、分割再現してその直接的な生命を奪ってしまっているではないか。そこはわれわれとはえらく違うではないか。どちらがいいか答える必要もないくらい自分たちのものの受け止め方のほうがものを損なわずに良いに決まっている。こうした彼の矜持は先史いらいブレることのなかったこの列島にそなわる言語精神の基本軸の存在の自覚に基づいたものである。バーチャル世界を忌避したリアル世界では何の隠れたる意(ココロ)も理(コトワリ)もなく、直に「言」のフリ、「物」のサマというものが露となる・・・。

「オモテ(面)」 哥座
Covent
Garden London
それは現代にもアカラサマにみてとれるフリである。「お母さん」というタイトルで見せた舞踏家・大野一雄の晩年の公演がそうであった。舞台袖からあらわれ、掌にした一条の短縄でくり返し、音立てて中宙を切り裂くスーツ姿のままの舞台の大野。かれは、自らの表現も、他者も、宇宙のすべてを直に叩き尽くしてあるきまわる。その激しさ。母をおもひ振り下ろす縄の「イキホヒ」。それらは対象化して普遍化し得ない心のはたらきが直に顕われ「フリ」そのものと化した大野であり、わたくしたちの姿である。クラシックバレーやモダンダンスと舞踏は根本的に違うなにものかである。舞踏は、身体を時空間のなかに構成し、そこにおける美をもとめない。ニジンスキーの永遠性へと飛翔せんとする身体やべジャールの構成する時空間という枠組みは、そこで音をたてて、叩き壊されている。代わって、大野の「フリ」は指のさき一本一本が、みづからの肉体の実体化をウナガシゆく。イメージを排し、物化を果たしゆく・・・。そのとき、身体が地軸と成りゆく周縁には、無辺で無窮のただ反復し連鎖していく「物」の原野がひろがっていた。直後に同じ舞台上で開催された吉本隆明を主賓とするシンポジウムでの、そこで交わされたことばは、さきほどの微光をいまだ残した物のしじまにあっては影のうすいものとならざるを得なかった。
しかし、実際の表層意識では、古来よりことばとものの視座を、天竺・中華・欧米の抽象座標にナリスマシして暮らしてきたわたくしたちは、こんにちにいたる大陸とこの列島間の彼我の視座の違いからくる学問・芸術・生活全般にわたる、あらゆる誤解や勘違い、そこからくる所在なさや悲喜劇の中に在る。
- こうした彼我の言語構造間の断絶の深い闇にのみ込まれて身動きがとれなくなってしまうとき、社会システムは硬直化して一種の統合失調を引き起こす。
- こうした齟齬から生じた象徴的で重篤な事態のひとつがこのたびの列島三度目となる世界史的な核物質による放射能汚染であるとの見方も可能だ。
三、一一以降は、国際的原子力シンジケートの論理にくみこまれた産学官が、あらゆる意識、無意識の裡に理(ことわり)を駆使して、その本質を隠蔽してこようとするだろう。けれども、明治にその構築がはじまった近代自然科学や政治、経済、そして学産体制までその大半のナリスマシの枠組み自体が機能硬直化をきたしていたのはあきらかで、最後にリアルなメルトダウンを迎えたということだから、それはチェルノブイリ化していたソビエトというシステムがリアルなチェルノブイリをきっかけに崩壊してロシアになったように、列島の仮構の巨大テクノロジーをささえてきたやはり仮構のナリスマシ社会システムも崩壊するしかない。
これらを意志のちからで隠蔽しようとしてもかなわないはずだ。わたくしたちはもっと構造的な崩壊に直面しているのだから。今後は、それに比例した社会的統合失調の諸症例も増大するにちがいなく、これら病理への有効な処方箋はこのアポリアを正面に据えて、その解決と大陸の抽象座標系思考との差異の自覚からの社会システムの再構築なしにはもとめ得ないだろう。芭蕉の陸奥は、智恵子抄のそらは、賢治のイーハトーブは、普段着でのなにげな時候のあいさつことばは・・・。半永久的に終決のつかない今回の事件をおもうとあらためて覚える哀しさ、それがヒトやものにそなわっている自然なこころ裡であって・・・。しかしその一方で「言挙げせぬ」ことの原野で物のカガヤキを受け止めてきたのが列島の真と美の在り様である。それは近代の感性よりもっと深部の出来事として在り、その構造は
今後とも微動だにしないというのも事実である。
論旨がズレてきたので、主題へもどすと、ここであらたな問題が三つ発生している。【第一の問題】は、わたくしたちにそなわる独自の文脈をそこに載せて読み取る座標系が明確に顕かにならなければ、じぶんたちの足許の心性の核の自覚は育ちにくいだろうという問題である。それはいうにおよばす、そこに根ざした芸術、科学の自発的な動向が未来過去にわたってあったとしても、見ることもできず、かろうじてみえたとしても、ただしく評価できないことになる。その結果、抽象座標系に載せた欧米視点による読み替えがおこなわれ、その評価が定着して、真美に蓋をしてしまうこととなる。たとえば岡本太郎が発見した火炎式土器の美を彼は近代フランスのアンフォルメル=抽象表現主義の造形視点から評価したが、その後そのすぐれた発見をわたくしたち独自の地軸へ読みかえて、そこに想定される列島独自の空間と時間を措定し、そこにはたらく力学を確定し、さらにその視点をフィードバックして、現代空間を検証するような
- これはこの列島文化における基本的な作業として要請されてしかるべきだとおもわれるが - そんな仕事はだれか、あるいは、どこかの研究所ではしてきているのだろうか。いまのところ、私は、この哥座(うたくら)以外でその例を知らない。
また、同時代的に、現代の思想と密接に関わる現代芸術の最前線において、戦後、この列島独自の基本軸にはじめて触れた「具体運動」や「舞踏」は、きわめて一部の美術評論家をのぞき、いまなおその評価は不十分のままである。この運動が提起した、わたくしたちに固有の地軸が存在し、そこに独特の空間力学がはたらいているということを確認できることから発生する問題は、芸術界にとどまらず戦後思想界をゆるがすほどのひろがりをもっていたはずだが・・・。
(ただし、「インスタレーション」や「シュールレアリズム」また「(肉体の)オブジェ化」などの概念を切り口に戦後前衛芸術を積極的に評価してきた澁澤龍彦をはじめとする旧世代評論家のキーワードでは、この列島独自の地軸に根ざしたムーブメントが欧米芸術の文脈に読み替えられてしまう。そうなると火炎式土器の岡本太郎の解釈にみられるように、その真美の本質はかえって隠蔽されてしまう。その傾向はいまもってつづいているが、真美の判断基準となるはずの彼我のよって立つ二つの座標系の違いは類推やメタファーでは橋渡しがきかないほどに、まったく百八十度異なっているのである。ここをあいまいにしてはならない。)
ちなみにこの国の現代美術や舞踏を評論する際に、欧米古典美学理論からはじまって現象学や哲学、欧米言語学の視点を導入して批評するのが一般的になっている。そうなると彼我の二つの座標系の違いに基づいたところの独自性も、たんに普遍的な潮流が存在し、その本流にたいするローカルな現象くらいに受け止められてしまおう。しかしそれはフランス人が「てにをは秘伝書」でもってセザンヌや独逸現代美術とか欧米モダンダンスを分析評価しそれでもって教育にもあたることとか、芭蕉を評価するハイデッガーがドイツロマンティシズムを去来抄など俳諧理論書でもって分析するとかを想像してもらえればわかることだが、ようするに、アートシーンの主流をなす欧米言語精神にナリスマシ、その視線で系の異なる自己のアイデンティティーを位置づけてしまう奇妙な現象のひとつである。実際にフィヒテ研究家でハイデッガーの哲学で芭蕉を理論体系づけた俳人もいらっしゃる。こうした一種の勘違いを明治以降百五十年いや飛鳥以降千五百年営々とやってきたおめでたい国は世界ひろしといえどそう見つからないだろう。おそらくこうした現象は植民地文化にありがちな宗主国の美学規範が唯一のワンワールドな世界自身であるとの思い込みを大学や美術館やその他もろもろの権力そのものである文化制度から強制されつづけてきた結果なのである。儒学がそうであったように自分で自分のあしもとの言葉から考えるという基本作業を怠りステータスを保障してくれる当該時代の制度と実利的な取引した結果、ナリスマシの思考停止がここちよくなってしまった。かれらのあたまのなかみは植民地そのものなのである。初代文部大臣が公用語を英語にしようとしたり、どの国でも当該国の詩は数学科学の基礎でもあるのに歌俳を無視する輩が学問のすすめを言い出し大学をつくったり、戦前に立派だと尊敬されていた文人が敗戦後は日本はフランス語にしようといいだす国では当然の結果なのかもしれない。
当該芸術と科学思想の両者は、その底辺では同じ言語法則に根ざしたものである。しかしそれが自国の言語文化を離れてしまうとその自覚が薄れて芸術も科学も本筋から逸れた利権の取り引きになってしまう。それはここで改めて言うほどのことでもなくすべての文化圏の出発点となる大前提であり、外部文化を移植する場合はそこをおろそかにしないというのが基本であろう。。
しかし、そんなことに露ほども思い至らぬこの国にあって、それは【第二の問題】をひき起こす。まづ、外からやってきた社会科学思想や科学技術を受容する際に、その思想を自分たち自身の座標系に位置取りできない限りは、もともと抽象座標系に根を持ち得ないわたくしたちにあって、その真の認識と創造的活用はできるはずもない。模倣をくりかえすか、目先の応用に終始するほかないことになる。こうした自己の拠って立っているはずの時空間感覚の欠如したままの現代の社会科学系および自然科学系と称する学問は、目先の利潤を求めるいち業界にすぎないのだといえよう。自分の歩むあしもとが覚束ないまま、未だ大陸系抽象座標に載せた概念思考論理のみが世界統一規格だと盲信し、それらへの批判原理も養生せず、つぎの新ソフトの輸入と日本化と称してカスタマイズに励んで嬉々として自己満足しているその姿は、人麻呂の誇りとくらべてみたとき、あまりになさけなくあさましい姿ではないだろうか。列島のフィジカとメタフィジカとを正当にうつしだす戦後のすぐれた先鋭芸術作品が提示する座標系があるにもかかわらず、それを顧みることの意味にまったく思いが至っていないのだ。たとえ見ようとしても、そこではアポリアが呪縛となって行方を阻んではいるが・・・。ケッキョク真も美もまったく見えなくなっているいまの状態では、基本的な問題などかれらの視界にうかんでこようはずがない。
しかし、ここまではまだローカルな話として、異文化と接触する際にどの文化圏にも多少なりとも起りえる現象だ。問題はそこからである。あとで詳細するように「言傅へ」を旨とする列島言語精神は、縄文の古代より「言」を「物」としてとらえていまに至っている。このすぐれた特質というものは一方、「漢意(からごころ)」が代表するように、大陸の座標系で発展した仮象概念や論理まで実体化した「物」として受けとめて、そこを尺度にものごとを見ようとしてくる。ここが、とくに近代欧米の抽象概念の受容と運用においては、致命的な欠陥となってくる。それが【第三の問題】である。もともと概念とはたえず規定しなおされなければ機能不全に陥ってしまう仮に措定されたものでしかない。批判力とセットで論理化されるのが概念運用における必要条件だろう。当の欧米自身、みずからのうみだした概念は実体ではなく観念であり、時代の抽象座標系へ載せた約束ごとであること。そしてそのつどの時代の進展にあわせた定義付けと、そのための批判力が必要であることを自覚している。ところが、抽象座標系をもたず、時空間もないこの列島では、場当たり的局部の批評はできても、概念・論理を成立させているベース自身から発した基本的な批判力を原理的にもちえていない。
そこで生じる滑稽な事例には事欠かない。たとえば仏教においては中村元が詳しいが、飛鳥以降、鎌倉期までを通じ、仏教論理学の研摩・研鑽は、この列島で運用されるとき、いつしか様式化されたやりとりの儀式の道具としての「物」にまつり上げられてしまった。龍樹の哲学といへども、ここではダルマとしての論理ではなく、「言」すなわち「物」であり「列島地軸としての神」としてまつられてきた。それは大宝律令が原典も紛失し、おぼろなまま平然と千年ちかくもにわたって立法精神も忘れて運用されてきたことや国会を儀式の場と化した昭和憲法の法概念のなしくづしの拡大解釈など、立法という現実世界においてもみられる「概念」の「物」化現象である。外来の思想を原理的批判力のないままに、存在しない概念上のものまで在るとして「物」=「言」思想で運用にあたると、その結果する現象は、よく日本化といってごまかされているが、ようするに、無きものを在るとして、そこに威力さえ認めてしまう呪術世界に陥ってしまうのである。この心性は、えてしてそこで社会経済条件を反映した共同幻想に捉えられたとき、この国の大学研究室やシンクタンクなど
セクト化した - この場合のセクト化もシステムの「物」化現象のひとつにほかならない - 専門機関で再定義され、意識あるいは無意識裡に機関の利に適うパラメーターが設定され、いかにも客観的なデータ解析のようにみせかけられて、そこにあらぬ意味が付加され、幾重にも扮飾されて、まつり上げられたその語がふたたび流通するころには、批判力とは無縁の思考停止のたんなる題目にすぎなくなっている。三、一一であきらかになったことは、電力マフィアの跋扈をゆるしてきた挙句に、国際的合意にもとづいて法制化されていた放射線被曝許容量を年間二十倍にもひきあげて、とくに子供たちの健康リスクに目をつぶって平気な民主主義を詐称するナリスマシ国家が存在しているという事実だ。そこにわたくしたちは暮らしている。そしてそれらにたいする批判原理をもたないどころか、みづから、自然と美と生命の麗しさを壊しながら、その自覚もなく自然科学、社会科学を詐称して立法、行政、司法から医療、金融経済、国際関係全般にわたって、ナリスマシ国家権力を支えつづける数多のナリスマシ機関が存在することである。しかし、これらすべての土壌は彼我の言語精神の差の存在を見極めようとしなかったわたくしたち自身がつくりだしている。
以上の意味からも、この小論で顕かとする彼我の座標系の差異とそこにはたらく力学の差異にわたくしたちは目を背けることはできない。この差異をまず事実として押さえ、わたくしたちの基層をふまえたところから問い直さなければ、なにごともはじまらないだろう。もともと当時の国際教養人でもあった人麻呂の誇りの意味するところの世界は、偏狭なナショナリズムやローカリズムに還元される問題ではまったくない。ましてそこにイデオロギーにもとづいた現代的解釈をくだすことは、幾何学の問題に三角形の色を問うような的外れなことである。先端テクノロジーや高度情報化システム社会が引き起こすおおきな変貌期に直面したいま、これまで受容してきた印・中・欧のテクノロジー文化のもとづく大陸言語精神の基盤というものを、いまいちどそれらの座標系を相対化できる列島独自の視座に立ったうえで検証し直す必要がある。そのためにわたくしたちの抱えるこのアポリアの解決は、このまま放置できない火急の問題として浮上してきているのだ。わたくしたちは、世界史的な同時存在であるからこそ、彼我の言語構造を隔てる断絶とそのはたらきかたの相違を認識し、未来の意味を問いかけていく必要性がある。そうでなければ、従来の儒家・仏家の思想や欧米近代自然・社会科学の学問の後追いをして -
それらはみかけは中立的だが、その根本においてすでに観念的な主客を定立したプラットフォーム上に独善的な分割統治の視座のもとに成立したものであり、それゆえの偏向した世界性という限界を抱え、また実際化された場合、所詮、既存権力の利益システムに組み込まれ、特殊業界のひとつとして圧力団体の利益を代弁してはたらく政治と癒着しつつ、自己保身に走るしかないだろう。 -
エネルギー業界や遺伝子工学。そしていまやあらゆる産業を支えるIT業界の組み込み系やシステムエンジニアやプラグラマーたちのこの国の言語で考えることを放棄した眼差しには、心理学や先端医学まで取り入れて、欧米論理だけを規範にした機能主義によって、工業製品のみならず人間までも空疎なアンドロイド化を最終目的にしようとする未来しか映りこんでいない。-
そんな例えば十六進法カルトたちの盲目的ナリスマシ活動を独自文脈で読み替え、母語による批判を加えることことができないまま放置したのでは、わたくしたちは大陸系の視座にナリスマシただけの永遠のインターナショナリストとして仮構されたグローバル世界を漂流しつづけ、気がつないうちにさらなる悲劇に陥ってしまうことになるだろう。
*「言挙げせぬ」こととは、呪術的観念を超越した縄文時代からの基本的な列島言語規範であったとおもわれる。それをあへてここで「言挙げす」という人麻呂の発言は、逆説の意味をこめたものではなく、遣唐使が赴こうとする「唐」に対して、両言語精神をみていくメタ視点にたった発言としてみれば至極、順当なものである。いま、この列島言語精神の特徴をみていく上で、とくに欧米言語精神との差異を明確にするためにも、系のことなる言語精神文化を同時に掬いとる作業視点が要請されてくる。それは唐国にたいする人麻呂のこの例にみるまでもなく論を俟たない。ただし、メタ視点がうみだす概念は仮象を生みだして「言」の本意を無みしてしまうので、その射程を限る必要がある。
その点、漢字を導入、定着した万葉以降に形成されたはずの「言霊」ということばは、このメタ視点によってうみだされ、固定化された概念ではなかろうか。その証拠は、まづ「言霊」概念のほとんどは遣唐使送別にあたって詠われている点にある。つまりここで「言霊」はあくまで漢国を意識した上で、「言幸くの内容」=「・・・然れども 言挙げぞ吾がする
言幸く (ことさきく) ま幸く (まさきく) ませと つつみなく 幸く(さきく)いまさば 荒磯波 (ありそなみ) ありても見むと 百重波
(ももえなみ) 千重波 (ちへなみ) にしき 言挙げす吾は 言挙げす吾は・・・」という意味内容を概括し、表象した概念として使用されている。人麻呂以前から流通していたであろう「言霊」とは、はじめは説明に便利な通俗概念あるいは作業概念であったものが、しだいに呪術的霊力をもったものとしてひとり歩きし、もともと「言」「物」にそなわっている原初的、存在論的驚きを代弁するに便利なある種の霊力をもった理(ことわり)として、定着していったのではないかとおもわれる。
*神威というこの概念も漢語に影響をうけて成立したのものだろう。意味を内包した抽象概念は、言や物が直に物であるとする受け止め方に混乱を生じさせる。列島言語は、常に上代にあっては漢語からの、明治以降は
- ここで造形美術概念に絡めて説明したが - 欧米からの抽象概念の混入で、そのはたらきかたが、二重構造となってしまっている。そこで列島独自の物と言のはたらきかたが、大陸座標上の概念によって再解釈されてしまうことで真実が覆われてしまうのだ。この事情が、アポリアの解決を一層難しいものにしている。
第二章 実存の根拠
いまでは、E=mc へと還元され得るに至った、森羅万象を四個の座標の幾何学に煎じつめる物理世界においては、わたくしたちも概念上、そこにカウントされそれを利用もしている。しかし別項で触れたように、実際は、その場にこの列島の住人は実存の根拠をおいて来なかったし、これからも真に身を置くことはないだろう。一方、西欧では常にロゴスという伝統的思弁哲学が拠って立ってきた抽象座標系のプラットフォームが先験的に備わっており、そこに根ざしたもののみかたをしてきた。現代にあってもその基本は変わらず、それは「言葉は存在の住処である」とするハイデッガーの言表にも端的に覗い知ることができる。クラシックギリシャのユークリッド幾何以来それら初期自然科学と観念哲学、造形芸術とは、当該時代にあって同じ座標系を共有しながら、常にパラレルに現象してきた。その進捗の果てに現代物理学や社会科学そしてオブジェ指向のかれらの芸術が平行して存在している。しかし、それらが共通に根ざしてきた抽象座標系列世界と、わたくしたちがいまも住み、根をもっている「言挙げせぬ国のフィジカとメタフィジカ」世界(別載)とはここで採りあげる事例をみるかぎり、あきらかに系統がちがう世界である。
へと還元され得るに至った、森羅万象を四個の座標の幾何学に煎じつめる物理世界においては、わたくしたちも概念上、そこにカウントされそれを利用もしている。しかし別項で触れたように、実際は、その場にこの列島の住人は実存の根拠をおいて来なかったし、これからも真に身を置くことはないだろう。一方、西欧では常にロゴスという伝統的思弁哲学が拠って立ってきた抽象座標系のプラットフォームが先験的に備わっており、そこに根ざしたもののみかたをしてきた。現代にあってもその基本は変わらず、それは「言葉は存在の住処である」とするハイデッガーの言表にも端的に覗い知ることができる。クラシックギリシャのユークリッド幾何以来それら初期自然科学と観念哲学、造形芸術とは、当該時代にあって同じ座標系を共有しながら、常にパラレルに現象してきた。その進捗の果てに現代物理学や社会科学そしてオブジェ指向のかれらの芸術が平行して存在している。しかし、それらが共通に根ざしてきた抽象座標系列世界と、わたくしたちがいまも住み、根をもっている「言挙げせぬ国のフィジカとメタフィジカ」世界(別載)とはここで採りあげる事例をみるかぎり、あきらかに系統がちがう世界である。
第三章 時間と空間をもどく
この否否定相をそなえた独自座標が顕かとする世界は、概念の本質や物質の求心性、内包性がそこで無化して、反復する無名性の世界がひろがる時間も空間も欠落した世界である。通常ならば、その内で、論理的な演算にかけるために、ものごとを関数化して位置付けるはずの、時空をはじめとした枠組みとしての各抽象座標系は、列島の独自否定相のもと、それまでの各座標系の個別領域の涯で、内が外へと裏返される。それは「てにをは」に代表される主体が「詞」や概念としての客体へ関わることで主客融合の場が生成されるのだと言い換えてもいい。また物事の立ち位置からみた場合、旧来座標系の事物がまったく系と相の異なった座標系に置きなおされる事態であり、それを指して”もどき”であると云ってもいい。つまり、そこには普遍的な座標に代わって、あくまで個別的で具体的な「物」や「言」として、列島独自の形相(エイドス)からなる排列が形成される。その純一な形相こそが列島固有の座標軸に他ならず、そこからその周縁に「見る」から「見ゆ」という視座転換が起こると同時にそこで物事がありのままに連鎖展開してくるのである。
もうここに至っては座標というイメージにはほど遠いが、物事を取り込む座標ではなく自らが物化して、それを機縁に、そこからその外延に未分節な物や言が継起していくその当の場という意味である。そこには物の順序が定まるはたらきはあっても、物を対象化してそれら物質間の力学法則がはたらくような時間や空間は見当たらない。
そんな分節化未然の、ただ反復する無名性の世界がひろがっているばかりの初源的な場に還元されると「言」は、抽象的座標軸に代わる歌や句の一首一句一音そのものが、また、「物」にあっては、先史縄文の器自体や表象を忌避して、そこに物付けした縄の眼そのものが、そこで定まりを得て具足化する。同時に、みづからを軸として、そのさらなる周縁に無辺・無窮の場を生起させ物事の在り様とその位置とが明らかにサダマってくる。ips細胞のように未来も過去もつねにいまここから可逆的にあたらしく始まりを始めることができるのである。
そのあたりの事情は、現代美術の「もの派」の作品や舞踏の身体にも共通してみられる特徴である。その際みずからを「舞踏はいのちがけで立ち尽くす死体だ」と云った土方巽のことばには、時空をもどいて、地軸と化した身体の在りようと、そこでひらかれる列島独自の無辺で無窮の地平に物がひしめくありさまがみごと集約されて云いとられている。
第四章 「見る」から「見ゆ」という世界へ
また、おどろくべきことに、先史に由来するわたくしたちのほとんどのことばは、現代語においてさえも、たとえば「月」ひとつ例にとってみても、ほかの印・欧・中の言語文化圏の固有ブラウザによって抽象化された座標にうつしだされてくる世界とは、まるで様相の異なるはたらきかたをする。常識では、わたくしたちの「月」も中国の月も漢字概念としてそこに対応した意味と表象を担い、当のあの夜空にかがやく月を指し示すものであり、また、「MOON」とも同義であり、対象存在として、オブジェクトとしての月の指示代名詞だとうけとめられている。
しかし、この列島にあっての事情は著しく異なる。それは1970年7月、京都国立近代美術館における菅木志雄の作品「無限状況」の館内踊り場の窓枠に斜めにさしわたし小窓が閉まらないようにしたツッカイ棒のはたらき方と似ている。もともと美術館は空間の求心力を活かして、ひたすら作品へ集約するように、閉ざされた場になっているが、「無限状況」では、ツッカイ棒自体は何も表象せずに、館の内と外との関係を解体する。そこで建築物としての物理空間と作品提示という制度空間はもどかれる。それまでの近代座標軸に基づいてきた視点は、ツッカイ棒という物の現実態(列島独自のエイドス-形相)そのものを軸としたあらたな視座へと転換され、周縁には無辺の空間、無窮の時間というわたくしたち独自の場がひらいてくる。つまり、ここでは従来の時空間座標は具体的な棒切れで裏返しにされて無化されてしまっている。
その棒という物のはたらき方と同様に「ツ・キ」という「言」は、一音一語の舌触りあるこゑとして実体化されたとき、ここでいっている「不理・非象・無辺・無窮」という否定相をもった形相として座標軸の役割をはたす。こゑとなった「ツ・キ」という言それ自体はそれ自体として概念としての抽象座標に浮かぶ月の対象存在をもどき、意味を内包せず表象せずに(不理・非象として)「ツ・キ」としてただ言であり物である。座標上に再現されて意味を内包する「月」や「Moon」ではない。(函数構造を備えた中間言語としての日本語を参照)
概念としてはたらかない物として在る言は、そこでみずからを絶対軸とした独自の時空間を形成する。この場合の絶対とは、本質を喚起しない言は物として其れ以外のものではなく、逆からいえば他所から規定されもしないという意味における次章で宣長いう「其外ニ何モ無事ゾ」という「物」としての絶対である。なんらかの神秘性や永遠性を付加した絶対ではない。つねにいまここの一回性としてある「物」の絶対をいう。-
この物化した言を地軸として内と外、あれとこれ、吾と他者というすべての境界性が無化された無辺無窮という時空間が生起する。そのフィールドに月を月として、同時に、周縁のものごとをともに、関係性まで含めて、物をあるがままの在るべき位置にふたたび直に具足化して返してくるのである。この無辺で無窮という従来時空の失せた場では「見る」から「見ゆ」へ、物を「対象的に思考する」から物を「おもふ」へとわたくしたちの身体視点もそっくり掬ひとられたかたちで、視座の転換が生じている。
この事態はまた、別頁「A・S・О」にすこしくわしく説明した。大陸系の概念箱をもどいた「A・S・О」は、「物」の展開図であるとともに「言」の展開図でもある。この「A・S・О」作業の数年後、熊野で出会った「花の窟
」のかけ縄もまた、「A・S・О」と同じ構造とはたらきをもつ固有の地軸として、遥か先史に由来するであろうその縄そのものの中間言語としての在りかたが、言挙げせぬこの列島固有のフィジカとメタフィジカの根拠となり、いまにまで至っている。
これらの視座にはたらく力学は、日常の道具存在としてのことばの使用からいったん離れて、表記された漢字仮名交じり文と(できれば歌会や句会のような非日常の場で披講されたアヤをそなえたこゑの上り下りの体験の場として)そこで実体化されたこゑに聴き入っていけば、列島言語のはたらきの特徴が聴き分けやすくなる。こうして「書傅へ」ではなく「言傅へ」をその旨とするわたくしたちの言語の性格があきらかとなればそのとき、漢字に代表される抽象系座標と、まったく正反対に位置する「物」「言」それ自身を実体化して中間言語としての地軸とした(そのことで物を再現構成しないでありのままその輝きを受容できる)座標系との、この二つの座標系の切り替えがおこなわれるので軽い眩暈をおぼえるかも知れない。
(ここでいっている差異とは、ある中国思想研究家が云っているビジュアル処理と日本語言語処理の左脳と右脳の違いのことではない。ここでは一般観念としての時間と空間そのものがそこにあるかないかという両極に対峙した座標系の違いを指す)
この経験が示すところでは、また菅の作品にはたらく世界とのかかわりの論理 - 「もの」が在るから「極限的に在る」(人工的な制約を離れたところでどうしようもなく在る)への置き換えと放置を通じて世界と関わるという制作論理
- を「言」へと援用敷衍すれば、わたくしたちの言語精神の座標系にあってはすべての古言がそして日常の生活用語も含めて、ほとんどのことばは、「物」と同様に「人工的な制約を離れたところで(言の場合は意味性として在る言語からどうしようもなく在る状態、こゑをともなって物化したことばの状態。)」そこでは「言」と成った「ことば」は内容に対応する対象をダイレクトに指示しない。中間表現言語としてたんに「言」である。
- この「ことば」が内容に対応する対象をダイレクトに指示しないという哥座説は、とても合理一辺倒の現代人には理解してもらえそうもない。そこでいまだに輸入言語学説がまかり通っている現在にあって、列島独自言語精神に立脚した視点から思考することにおいて、戦前戦後を通じて、おおきなブレもなく、いまあらたに注目されている国語学者・時枝誠記氏の言語過程説に倣い、戦前の昭和の十年代にたちかえった地点から、この事態をサポートしてみたい。だいたい以下のようになるだろう『ソシュールの古典的学説ならばこの「月」が特定の「月」に限定されて用いられたと考えるだろう。しかし、言語過程説でいえば「月」は限定的には使用され得ない。言語表現とは限定されたものを非限定的に表すものだからである。「月」の具体性を決するのは、この「月」なる語それ自身にあるのではなくて、周縁との関わり自体に存している。具体的には、話者と聴き手の立ち位置が決定してくる』
言語構成説に対峙させた言語過程説は時枝氏自身も危惧していたように、表象や概念という基本用語使用において、構成説の用語をそのまま継承し、それ故の混乱をきたしているとおもう。しかしそれは時代限界による不徹底であって、それよりも「列島言語の核心に関して、源氏、和歌一貫して、その表現の位相には現代人の常識に逆らってつねに忌詞につながるような否定のモメントが介在している」というようなところなど随所にこの列島言語精神への秘密の通路が用意されている。ジブン的には思考が袋小路にはいったときなどに著作を通し幾度か助けてもらった。
ついでだが、時枝氏が源氏物語で指摘するように、こうした列島言語の最大の特徴は「ことばは内容に対応する対象をダイレクトに表現しない」というところにある。この力学が最大限に強調され意識化され日常的なレベルにまで言語主体側に引き寄せられた用法が「忌詞」である。(ところが、忌詞の忌みされるそのわけは、その詞に不浄さが内容として存在するからではないのである。多分一般学説はその点を取り違えているとおもわれるが、あらためていうと、「忌みの本意は詞の持つ意味内容にあるのではなく、この国の形相言語としての中間表現のはたらき自体に備わっている否定相にある。具体的には詞の概念化作用自体に存するのである。」この辺のことは大陸言語と列島言語の思考ベクトルが逆になっていることから押さえなければならず、いまだに欧米化の視点で普遍化することをその本質としている明治以降の既存学問システムでは国語学であろうと原理的に思考不能に陥るはずである。
列島言語に備わっているはたらきという意味では、*「あいうえお」・・・から「ん」まですべての「言」と成った列島言語というものは、一音であろうと二音・三音であろうと、詞であろうと辞であろうと一組となったことば自体がそのつどの一回性なるコトとして概念やイメージを受容し引用符としてはたらくかぎり、すべてが潜在的な「忌詞」といえるのではなかろうか。さらに、ダイレクトに物事を指し示すことを忌避する列島言語のその特異な運動性こそが、別掲したように、**音訓併読や漢字仮名
併用現象をうみだす根拠となってきた。また、のちに芭蕉が「四十七文字すべてが切れ字となりうる」と看破したあるがままの世界をあるがままに顕かにしてくる言語装置としての
- 芸術の域まで昇華した力学法則。おそらく参禅をきっかけに、てにをはや、用言の活用形態のみならず、連歌の切れ字と押へ字、留めの無化のはたらきを深く省察することにより、
- すなわち俳諧における四十七文字の一字一音のすべてが切れ字のちからに満ちているという蕉風切れ字の再発見につながってきた。
同時にこのまなざしを「物」世界に転じてみると、「列島言語は内容に対応する対象を ダイレクトに表現しない」という中間言語としての「言」のこの力学は一万年もの長期に亘り基本的には表象イメージをかたくなに忌避してきた縄文の器の「物」の中間言語としての力学から現代美術のやはり中間言語としての空間力学にまでパラレルにはたらいてきている事が見てとれる。そして、それらはわたくしたちの法・経済社会空間の核心まで形成する基本力学になっているのだ。列島言語は表現を旨とする古代印・欧・中の言語とはいかに正反対に位置する言語系であるかということにあらためて驚かされるのである。-
かくして物化して「言」となったことばは、対象をダイレクトに指示せず、意味を内包しない。詞にそなわる概念機能や指示機能そして表象機能は列島独自の言語函数のなかで引数として処理される。そこにおける「言」は主客のみならず、詞辞や体用言まで未分化の地平で意味性から離れてたんに「物」となる。つまり、菅でいう人工的な制約を離れたところで極限的に在る状態になっている。そこで菅の用語に倣えば「放置」によってはじめてトータルなリアリティーとしての世界とかかわり合いが可能となる事態が生じてくる。(皮肉なことに私の仕事はバーチャルリアリティーシステムの開発企画制作である。裸眼でホログラム以上の大規模臨場感のBR開発に成功している。伝統芸能・芸術のアーカイブプロジェクトに最適である)しかしこの列島では先史より物を対象化してバーチャルなすなわち人口座標へと再現投影しないのである。はじめにヒトが言の機縁となり、あるいは反対に言がヒトの機縁となり、そのこゑと成ったことばは、まず従来の時空座標をモドキ、それに代わり具体的な物としての言が地軸と成る。その周縁に、時間と空間そして世界という抽象概念=観念に代わる列島独自の無辺の連鎖空間、無窮の反復からなる場が生みだされ、そのトータルなリアリティーのただなかに「つ・き」なら月、「み・ず」なら水がみずみずしい実感をともなった存在として確定されてくるのだ。
この構造に日本語が(*二)「あいまい」とされる理由もあるだろう。しかし、その場こそが、わたくしたち言語精神のもっともダイナミックな力学が躍動する場となっている。そこで、欧米座標から目を転じて、ありのままに物事を輝かしめているこの国の言語の、とくに和歌連歌の定まり方をよくみていけば、この国の原語は実際には大陸系の観念言語よりもはるかに深く存在に根ざした厳密な函数構造をもったはたらき方を示している言語であり、そこに確固たる法則が存在すると認めざるを得なくなるだろう。抽象化された時空座標に去来する吾や他者や表象や論理をこの函数で括り、無化した涯にこの列島独自の時間と空間の野性的フィールドに解き放つ。その窮まりどころのない場にはたらく具体的な力学は、これまでわたくしたちの言語に胎蔵されていた秘密を一挙に顕かにしてくる。わたくしたちが見ようと意志すればするほどに表と裏が入れ替わってしまい、忽ちに気配だけ残して失せてしまっていたとらえどころのなかった物と言の秘密が「放置」の涯で「***見ゆ」というかたちで開示されてくる。
***この場合、シナ美学の影響をうけて幾分観照的になりすぎたきらいのある歌の「ナガムル」よりも、万葉の野生的で素朴な問いかけにたいする歓喜の気持ちの入った「見ゆ」という開示のしかたのほうが、より原初的な宇宙の深みを示してくるとおもわれる。こうした問いかけに常にたち返へろうとしたのが芭蕉であった。
*「あいうえお五十音図」は、インド・ヨーロッパ語族であるサンスクリットの音韻の学、悉曇学の並び順をほぼ踏襲しているものだといわれている。言語を対象として音素を捨象化して抽象化し、理論構成づけた五十音図作成の方法からしても、その作業は列島言語精神のはたらき方とは逆行したものであり、印欧語族の思考方法から図説化されたものであることは想像できる。ただし、印欧語族特有のその合理化された図表の抽象性はそのままでは、この国のひとびとになじみにくかっただろう。だからその要請に応えて、日本風に情緒的にアレンジして並び換えられたものが「いろは歌」なのだ。当時、明覚を筆頭に印欧原語を学び、インターナショナルな視点をもった僧侶たちの合理的思考によって列島言語音は整理され、抽象的音素の観点から組み立て直された。そのとき、列島言語には印欧語族精神の反映があったとみなすべきである。平安中期は、和歌などいかにも日本特有の文化が独自に発達してきたようにみえるけれど、実はそこで使用され基本となっている言語や発想にはかなり印度・ヨーロッパ語族の合理的言語精神が反映されていたのである。あの先史の心根をひきついできた万葉期の野性的な感情は、平安に移行して、ソフィストケイトされたというよりも、おもに天竺学という大陸の合理的普遍精神によって整理され切り捨てられて、精神的にはトーンダウンした感覚ならびにその感覚に対応した存在が多かったはずだ。いまでいう世のデジタル化によって数値化し効果が不明なアナログ部分が不合理として切り捨てられてきたようなものだ。
なお、五十音図へと至ったこれらの経過は十二音階上にも敷衍してみていくことができる。平安期はいざしらず、明治以降の十二音階化した音の学によってわたくしたちは、インド・ヨーロッパ語族の絶対音階により自分たちの原音を整理してきた。そのさい掬いきれない原始音ーそれは沖合いの波頭をよ切る鋭利な音、そして春の清水の立てるさざなみの音、竹林をわたるささやきの音など、抽象化せず言挙げせぬことであらゆる具体世界を受容しようとしてきたわたくしたちの心性に根ざす、いま以上に親しまれていたはずの列島固有の豊かな音があったはずであり、その行方が気掛かりとなる。(こうした危機観を反映してか、いまの一部の動きとしては、鉄パイプで大小の自然石を突いてランダムに音だしをしたり、ゴムと木片を擦り合わせ、あるいは枯れ竹で空を切るなど、生の音の出来事自体を目的としたモノ派系統の無構成の小音楽会に立ち会う機会があることもある。ジブンでも時たま高円寺の音楽スタジオを借り、楽器はつかわず持ち込んだ自然石どうしを叩くなどして原始音との出会いを試みることがある。)
**「音訓併読」と「漢字仮名併用」現象は、意味を内包せずイメージ化を忌避するという列島言語精神から必然されてきた特異なる言語現象のひとつである。イメージを忌避することで存在事物をありのままに輝かしめようとする列島言語のベクトルは、概念的に物事を論理つけようとしてはたらく大陸思考のベクトルとその方向がまるで逆向きになっている。そこを押さえたうえで、列島言語をあらためてながめ直してみると、その精神は大陸言語精神の成果物である思想やものの考え方にいたるまでありのままに受容せんと働いていることがわかる。列島言語のそのはたらき方が健全であればあるほどに大陸言語のイメージも表象化された文字もその概念的な観念も、みずからの言語精神とそのはたらき方が矛盾するにもかかわらずそのまま受容しようとしてくる。その結果が、世界でも稀な平安以降の「音訓併読」と「漢字仮名併用」明治以降の「漢字仮名カタカナ併用」の言語現象となって顕われているのだ。欧米言語音を写したカタカナ文字として、呉音や唐音を写す漢の字として、それらは列島言語化されたひらかなの海へ浮かんでいる。ところがその浮島は列島言語本体とは関わり深いようでいて、ジツはなんにも関係がないのだ。そこは赤鬼・青鬼の棲む鬼が島なのである。あるときは、列島言語の権威付けを担う機能を果たして、役人や権力側の注釈引用に便利な観念体系としての出島となり、またあるときは、いそがしい私たち現代人必携の注釈に便利なフランス風心理学モデルの島である。個人や集団のレベルを問わず、わたくしたちの無意識的不安に応えてイメージや象徴交換をしてくれる場。つまりは、コンビニエンスに現存在の根拠を保障してくれる浮島なのである。しかし本質的にはいつまでたってもそこは鬼が島であり内地ではない。いつか征伐される運命にある。そこにそれ以上の理屈はない。
以上の事情を逆からいってみれば、「音訓併読と漢字仮名併用現象というものが、わたくしたち列島言語にそなわっている次の力学法則を明確にしてくれているのだ。つまり、「言」としての列島言語は意味を内包せず、物をダイレクトに指示もせず、表象化も忌避してしまう函数(意味や物や表象イメージを引数として”てにをは”という辞に函(つつ)むことで、概念を保持せずに変数の一種として参照する)言語なのである。大陸系言語概念とそのはたらき方が根本的に異なる。だからこそ併読併用現象が生じてくる。そのわけは、物事を分節化し概念として論理計算する所謂統覚を所有する言語精神では、外部を内部へ消化するか、あるいは、世界原理によって淘汰されていくかのどちらかしか選択肢を持たない。しかしながらわたくしたちの列島言語は、現実的局面でIchのように現実を統覚する主体を仮構しない。しかも函数内に参照移入することで仮構主体が生み出す原理の違った抽象概念や表象といった言語現象までをも同居させて平気なのである。ここではコギト思考をする近代的合理思考人の常識はまったく通用しない」とにかく列島言語は、概念が意味を保持してその関係論理を表現していこうとする大陸系自然言語ではない。直接表現をしない中間言語になっているのである。それ自体はダイレクトな意味を内包せず、「ヒト」や「モノ」にいったん預けて、そのプロセスを介して聴き手に受領してもらわないと意味をうみださない言語である。
和歌や俳諧のあの短いことばの内包する意味はほとんどたわいないとおもえるほど単純で、構成的にも幼稚にも見えよう。しかし、あの三十一文字がオブジェクト指向言語でいうコンパイルされて「言」や「物」のレベルで視座転換し意味が生みだされたとき、自らの視点や微塵の存在さえ掬い取られてどんな長編小説もかなわないスケールの大きな宇宙が開かれてくる。この比喩はいくぶん乱暴だとしても哥座はこの問題を言語精神とパラレルな関係にあるはずの「物」の空間においてもとりあげようとしている。具体的には現代美術空間と先史空間において、ものごとのダイレクトな表現を忌避するこの言語精神がそこへと一貫してはたらきつづけていることを証明する作業として、まずはそこまでの道筋をつくりたい。
第五章 「其外ニ何モ無事ゾ」(ソノホカ二ナニモナキコトゾ)といふ世界
ここでいっている「世界」とか、「極限的に在る」、「放置」という用語からは、混乱を招く観念的なあいまいさを払拭仕切れない。抽象概念は、できるだけ使用を避けたいが、大陸と列島との「物」にはたらく力学と「言」にはたらく論理との彼我の差を直接比較考察するためにあえて、混迷を極める現代美術の最前線にあり、ひとり抜きんでた感で活躍中の菅木志雄の独自美術用語をそのまま使ってみた。なお、小論では「列島の物と言には、その両者を同時に、その一段底からすくい取る地軸としての視座が存在」し、その否定相をともなう具体的な視点の在り様を示そうと試みている。「言と成ったことばは、内容に対応した外界の対象物をダイレクトに指示しない。」ということは、列島言語は抽象座標上の主客関係のなかで意味づけられ機能を担ったことばではなく、また意味を内包する概念ではないから対象物を指示しないということである。「言」は意味を内包せず直に「物」なのである。その当の「物」を対象化しようにもここで云う「不理・非象・無辺・無窮」という否定相が「物」の言語対象化に必要な座標設定を忌避、排除してしまう。
さらにこのあたりを詳細すると、大陸系の言語であれば、当該名詞あるいは概念は、すべて当該対象の意味本質を内包している。Moonであれば、Sunとは違う本質規定を持っている。そんな本質規定性をもたせて、対象物をダイレクトに指示することばを名詞と呼んでいる。そんな対応関係と、それら概念間の関係の論理づけを可能としているのが、かれらの大陸系言語プラットフォームである。構文においても時制においても、大陸の言語体系はそこに対応した現実世界を再現、構成するためのバーチャルリアリティー(仮想現実)世界となっているのだ。いいかたを替えれば、彼らの言語体系の基盤は、そこへと外界の対象物を再現し、その関係式を描写する一枚のキャンバス地なのである。タブロー(支持体)になっているのである。ところが、常なる一回性としてはたらく列島言語は、表現未然の中間言語として対象物の意味や価値を内包しない。言語の本質をそこに担保する抽象座標を設定しないのである。その代わりに「言」は一回性の縁起として「物」化したとき対象論理を超へた主客未分化の世界へと、あるがままの「物」の輝き出しを継起させていく。「言」は地軸の役割を果たす。そこが列島言語が大陸系言語とまるで異なっているところである。
まったく常識に反する物言いだが、列島のことばは本質をもたないのだ。本質なくして、無媒介に、イークォール、そのまま、たんに、理(ことわり)なく直に、「もの」なのである。宣長云うように「よく思へば、天地(あめつち)はただ天地、男女(めお)はただ男女、火水(ひみず)は火水なのであり其の外ニ何モ無事ゾ。」であり、それ以外ではない。先に「言となったことばは、対象をダイレクトに指示しない」といった意味は、言と物は同一のものであるからこそ、その間には、抽象座標のようにそこへ対象を載せ再現するフィルターもないので、どんな指示のはたらきも、媒介もなくて、ことばは対象物を指さない。ただたんにそのまま、言は物であり、物は言である。それ以外ではないという意味である。大陸では物事に対応したことばや概念は、いったん抽象座標上で、be動詞have動詞のように一時的ではあってもその底流に時間の持続性が保証されてそこで各品詞が機能するようになっている。名詞も動詞も助詞も、時空を可能ならしめる抽象座標上に関係付けられている。そしてこれは微・積分を可能にする数学においても同様である。それら関数演算を可能にしているのは、それを保証する抽象座標の仮設が許され、それが社会的、物理的効力を維持しているかぎりにおいてである。・・・等々これらをいくら説明しても、言語体系の差からくることばとものの彼我とのまったく相反する力学とその結果の世界のありようを理解するには、まづ列島言語を載せた固有の地軸のはたらきをみていかねばならず、そのサダマリかたというものは、有史以来、大陸系言語座標上の視点にナリスマシしてきたわたくしたちの常識とはあまりにかけ離れすぎた感があるだろう。
もともと古事記以前の列島言語は、言がそのまま物であり、体・用の別さえない世界であっただろう。なんとなれば、この列島においては、はるか昔の縄文の器や土偶が示すように、対象のかたちといった仮象をイメージ再現するスクリーンは拒まれてきた。たとえ造形したとしてもその視線を切断するはたらきが強くはたらきつづけてきた。
縄文の器のあのかたちは大陸系のように時空座標を背景にもってそこへ表現された造型物ではない。観念イメージの反映された表現物ではないからである。それ自身が具体的な物として外界の地軸となることで、その周縁に無辺で無窮の独自時空の場が現れ、そのとき、そこからつぎつぎと物が物を呼び出して物の連鎖をかがやかしめる契機としての排列言語になっているのである。それは普段のくらしにあっても地軸の役割を果たしていたはずである。
平城京跡で発掘された曲水庭園の石からはじまり銀閣寺裏手の小山にある優れた石組みまで石組庭園の岩の附け合いの関係も同様の仕組みでつくられている。連句の立て句の「言」のように石は「物」としてはじめの立石から連鎖していく涯は変局を経て不安定のなかの安定として具体的に定まっていく。十五個の岩と借景と白砂文からなる竜安寺石庭を見よ。優れた枯山水の庭園というものは天竺や中華の思想を引数としてこの列島独自の函数で括ってはいるがそのまま受けつけてはいない。観光用パンフレットや凡庸な解釈にあるような風景が再現描写されてなったものではないのである。縄文のあの器の仕組みと同様に純一で具体的な石の排列として表現未然の中間言語となっている。否定の諸相をもつその排列を軸にして、そこからはじめて「物」と「言」とが無窮の涯まで継起連鎖をはじめることができているのである。枯山水とは縄文一万年のその仕組みの平面化である。そこにはたらく「無」や「空」も古代インド・中国に由来しているようでいて、実は縄文から継承された否定の形相から必然されたはたらきなのである。
現代美術や舞踏の制作・行為の身体視点からそのままながめるとき、縄文器の制作姿勢はその器表面を支持体として、そこに対象物を表象し描写しないという忌避へのつよい意志からも読み取れることである。器表面に刻印されつづけてきたあの縄文の縄目とは、器のデザインとして物を捨象・抽象化しそのはてに描写されたものではなく描写表現をつよき意志で否定し物へ具体的にかかわることでもって主客未分化の器の実体化を果たし、表現未然の中間言語としてそこを起点に直に一回性の物の連鎖をカガヤカしめてゐる。あの縄目の形相の純一なる排列が、直に言挙げせぬこの列島固有のフィジカとメタフィジカの根拠となってきているのだ。
それはあの草間彌生が「自らも他者も、宇宙のすべてをオブリタレイト(消去)する」と宣言したあの無辺に反復する否定の網であり、大野一男の「お母さん」の舞台でみせたあのフリカザシ・フリオロス一条の縄のサマなのである。器にみられる縄の目のあの自在なサマやフリに見て取れるイキホヒというものは、言における「て・に・を・は・も」が、観念をあらわさない叙辞としてありながら、そこにこころのはたらきが直に顕われだしてはたらくのと同様に、当時にあっての物と言との本末をあひてらしてかなへ合わせていることが諒解される。
ひとたび大陸の造型概念をはらえば、そのさだまりかたの徴には、まるで昨日のできごとのようにまざまざと彼らのこころのフリや息吹きが今に聴きとれる。そこから古の人々の一挙一投足が手にとるように見え、言問う声が耳に聞こえてくる。まさに「古の手ぶり言問ひ聞き見る如し」なのである。それは、また「言挙げせぬ」ことでかえってトータルな物のリアリティーを輝かしめた和歌、俳諧につながっていった思想である。理(ことわり)は排し、イメージを結ぶ抽象座標も持たない。その事で世界と関わるというこのつよい意思はあの承久の縄文期を一貫していた思想である。その器の反復したつくりかたの基本に一糸の乱れも無い。「物」と「言」が相を違えた同じものの両極であるかぎり、確認できない先史の言においても事態はまったく同じであったはずだ。言は、意味を内包せず、言の体系をスクリーンに映さない。大陸にあるような座標上に仮象を構成することを徹底的に嫌ってきたのである。
用言として分別される動詞や助動詞、形容詞など主体側の叙述機能は、幾多の強権力の発生と各管理機能の細分化に呼応して、主に大陸の抽象座標上で発達してきたものだろう。列島では、はじめに言が物として、物が言として無分別に直に在り、用言はその変様態にすぎなかったと思われる。それを古文法では大陸座標系の言語分別から借用して仮に体言と呼んできたのではなかろうか。
このあたり折口信夫もつぎのように提言している。「用言の語根は体言的の意味あひをもつてゐる・・・即ち歌とうたふとは何れが先に存してをつたかといふ争がもちあがる。自分は名詞語根説を把るから、勿論歌がもとで、うたふは後になつたのであると答へる。」と。
ただし上ッ代を現代と切り離して古代の特色を神秘化したくはない。問題はつねに現在までつながってこその問題であるからだ。古代は、けっして体言世界のユートピアではないし、かれらにあってももちろん細々した日常にあってわれわれと同様に、物事の分節化と無縁であったはずもなく、そこで生じた仮象には常に正対していたはづだ。仮象を固定化する誘惑にさらされていたのは現代人となんらかわらないだろう。そのことは、かれらが、ものごとの分節化や表象イメージ化を知らなかった未開人であったのではなく、表象の引き起こす結果とその意味を熟知していたからで、それはその表象の破壊を前提につくっては壊してきた無数の土偶の存在からだけでも立証できうることだ。イメージ化された像の破壊には当該時代の病気治癒とか再生への願いとかさまざまな特殊な意味が込められていたことは考古学的傍証により想像に難くないが、ここではその内容には立ち入らない。表象物の破壊を貫抜く形式自体を問題にしている。そこにはたらくエイドスすなわち形相というものは列島独自のものとして全て晃かにできる得る。その視点から当時の出土品をみるかぎり、かれらの世界は現代人が勝手にみているような呪術という詞で一色に塗りつぶされる迷妄な世界ではない。現代人の心性と基本的にかわったところはないことがわかってくる。(むしろ呪術という詞は、抽象座標上にあれこれ描いた假象を実体と信じて疑わない現代にあっての多数の自然科学者や社会科学者にこそふさわしい)古代が「もの」と「こと」の真を見抜いていたことにおいては、わたくしたちのいまの暮らしにあっては想像もおよばない緊張感と、つよい意志でもってその視座を支へ、覚醒していた社会であったはずだ。
再現性というものは、その本質が仮象にある。かれらはそうした構造を見抜いていた。だからこそ、先史一万年を通して、再現描写をして表現を定着するスクリーン=抽象座標をする大陸系の度重なる影響をも忌避し続けてこれたのだ。もちろんその真を見抜くといってもそれは個人が意識してどうこうできるものではなく、共同主観の能力をも越えた列島言語精神のア・プリオリな出来事に属することだ。
「言」や「物」を主客構造に基づいた表現のための本質喚起的なものとしない。いともあやしきさだまり方をみせる「イキホヒ」や自在な「フリ」によって、油断すると結ぼうとしてくる吾や対象物という仮象物等の表象や理(コトワリ)を徹底して否定していく。
- それをここでは、自身の現代美術制作作業上の観点から、具体化された「物」の排列から成る座標軸と呼んでいる。そこに開かれる場は、現実を捨象して記号化して載せる抽象座標系とはおおきく異なっている。「物=言」としての具体的な座標軸である。そこに於いて「物」がたんに直に在るものとして継起していくのである。菅木志雄の「もの」が「極限的に在る」人工的な制約を離れたところでどうしようもなく在るという「物」のあり様である。-
この物化した座標軸は、それが白木綿でも、掛け繩でも、岩でも、何でもいいのだが、其れ自身は其れ自身として、意味を内包せずに、またなんらの支持体ともならずに、そのことで周縁に無辺で無窮のひろがりがひらかれ、そこであるがままの物が叛乱継起して来るのだ。先史縄文の器の面にはしる縄目のイキホヒが一万年近く前から直につたえている徴(シルシ)から判断する限り、「物」の恐るべきカガヤキの連鎖を直に受けとめていた。それは、彼らが、仮象というイメージをつよい意思で忌避してきたからこそ、現じてきた世界である。それはまた、「物」や「身体」の実体化を果たして、表現描写をする主体や客体としないことでその周縁に物の世界を明らめようとする現代美術や舞踏の求める本意とも同じである。そこから伝わってくるものは、わたくしたちの心性の根にある厳しき否定の「フリ」、「サマ」である。そこで「物」の輝きを受けとめてきたし、これからもそうしようとするだろう。
これらのことは神秘思想でもなんでもなくて、たんに言語を可能とするプラットフォーム上のことばとものの関係の認識上のことがらに属する。物と言との構造といえば、そこに構造なんてないのだけれど、構造といってもよい問題である。なんどでもいうが、それら時代を隔てた両者が共通してあらわに示しているこの否定の強き意志。そのつよき矜持によって、あるがまま「物」を輝かしめようとしてきたのがこの列島を貫いてきた言語精神である。
この事実は、二十一世紀にあっての現代美術の実作視点とその分析から、十二分に推しはかることができる。こうした観点から一度見てみると、自然科学や社会科学など、欧米の抽象座標軸が加わった明治以降、現在においては、いままでのような他所の言語文化圏に由来する体言・用言の分別からでは、大陸系言語座標系との比較や、彼らの座標系を客観視する作業に不便が生じてきていることがわかる。まして利便を第一とした翻訳上の観点からは、言語間にそれらを俯瞰するメタ視点を仮設するだけで大部分の用はすむが、それでは、人麻呂のあのアポリアの解明の道は閉ざされてしまう。ワンワールドという西欧思弁哲学が抽象座標上に位置付けた前時代的なユートピア的観測点からは、人麻呂のあの誇りの意味が導いてくれる系の異なるわたくしたちの原野や、そこにはたらく心性はせいぜい古代世界の詩的表現上の幻だったことにされてしまうだろう。
そこで小論は、和歌・俳諧の理論や現代美術の成果をふまえ、特集で言う列島独自の函数のはたらきが物化した地軸を生みだし、そこから物の連鎖が始まるということを仮説し、その視点から作業をすすめている。中国語や西欧文法に由来する文法観点からだけでは「言挙げせぬ」ことで物の輝きを受け止めてきたアポリアの解決は不可能である。大陸由来の概念思考に邪魔されると、系統のまったく異なっているわたくしたちの地軸の姿は見えない。そうなれは彼我の言語構造の相対化作業もむずかしくなる。
ことばが単語として、あるいは動詞、形容詞として、仮構された主体側の機能存在の面だけから受け取られがちで言の方位が定めにくくなった現代、(実際、上代特殊仮名遣い甲乙弁別の消息の遠因を成していたとおもわれる函数構造をもつ中間言語としての列島言語は、その構造のみなもとを単音節を基本とする基層言語にもっているとおもわれ、そこでは用言と体言。そして詞と辞さえも未分化の世界であったはずだ。そのあたりは冒頭の特集でひらかなというハイブリッドな言語表示装置が開発された結果”てにをは”と”詞”の分離傾向が上代特殊仮名遣いの甲乙の弁別表記(実際の発音上に区別があったかどうかはここで問わない)機能を急速に弱めていき、その消滅につながったということを逆説的な仮説による証明を試みている。)
こうしてみると、ここまでは作業仮説にしておいた、先史から今日まで対象化できなかったこの否定相をもった「つらぬく棒のごとき」基本軸なるものは確かに存在するのではないか。(・・・わたくしテキにはそう思われる。)と、またしても、わたくしたちのこの力学は、どこまでも「見る」「考える」視点をその動作主体ともどもに、この場合は(・・・テキ)として、モドキぬいて、その果てで折り返し「見ゆ」という場が生成されてくるまで、はたらきかけ続けてこようとする。まるで自白を強いてくるようなこの地軸のはたらきかけは、歌における月・花を求めてやまない西行の放下の姿勢や、源氏物語から日記文学、そしてこの国特有の近現代私小説全般の書きざまにいたるまで、一種のドグラ・マグラ型とまで呼べそうな構造心理となって顕われだしている。それは、「見る」「考える」という主体を仮定し、その主体の道具としてことばを規定したその機能の裏側において、たえず通奏低音としてはたらきかけてくる力学である。それ自身は「見ゆ」というできごととして、そのつどいまここに於いて一回性の主体と客体とが合一したあらたな原野を拓いてくれる。
第六章 極微の視点と周縁の力
これを逆から云うと、抽象的時空座標に代わる無辺・無窮の場がそこに生まれなければ、わたくしたちの言や物はでき事としてのちからを発揮することができないことを意味する。たとえば、私たちは「自然や環境を大切にしたい」という。そこで使用された自然、環境、人間、世界といった抽象概念は、ジャンルや時代によってそのつど定義され、意味内容も異なるが、言語が意味を内包するという概念自体の構造は不変であり、その構造を利用して現代社会科学の重要なキーワードとして流通し、またそれを反映した日常レベルではあいまいなかたちであっても誰もが象徴的符号として使用している。しかし、概念には、わたくしたちの言としてのチカラが欠けている。そこに感動がわいてこない。こころも物もはたらきださないのだ。
なぜなら、菅の「無限状況」でみてきたように、言や物はそれ自身は、表現の意味をいっさい担わず、いまここにおけるそのつどの言と物の実体化を通じて、そこではじめて、抽象時空座標に代わる地軸の役割を果たし、そこに独自の無辺・無窮の場が成ってくる。周縁のきわまりどころのないこのひろがりのなかでこそ言や物は、言となり、物は物として位置を定めることができ、姿を顕してくる。しかもこのでき事は、わたくしたち自身のどんなにちいさな視点をも巻き込んでやってくるのだ。しかし、概念は抽象座標に根ざし、そこで物を捨象して位置取りされ、意味を定義された観念にすぎない。それ自体が実体化した地軸とはなりえない。だからその周縁にあらゆる視点を掬いだすような、わたくしたち独自の場は成立せず、そこにはたらく力学も発動してこないのだ。この決定的な違いは、物事を抽象化された座標=世界に置いてそこに浮かんだものとして、俯瞰して見る抽象視点と、一方ではそのつど具体的で取替え不可能な心身を軸にした極微の視点から発していても、それ自体は意味を内包せず、物と言の実体化を通じてはじめて、無辺・無窮のひろがりの彼方から折り返しやってくる見ゆというかたちで見えくる視点との違いでもある。その対極的な両者の視点が根ざしているプラットフォームである座標には、物の見え方、はたらき方に及ぼすブラウザの決定的な質の差が存在しているのだ。そこで「自然や環境を保護する」という概念のはたらく抽象座標系にうったえるのではなく「山や海であそぼう」と、具体的な言を座標軸にして、わたくしたちの場を呼び込みひらくと、わたくしたちのこころは動き出す。
さらに付け加えるならば、言語精神のこうした特徴が集約され、極度に洗練されて様式化されたものに、和歌における枕詞があり、芭蕉の「切れ字」がある。(季語は言わずもがなであろう。)両者はまったく役割が違うようでいて、その実、ことばの抽象化を阻み、言の具足化を促して、周縁に無辺・無窮の場をひらき、そこに、物事の位置をサダメくるという独自座標軸としてのはたらき方においては同じ機能を担う言語装置である。
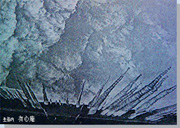
「零次排列」みちのくのそら
第七章 繪をもちいざる國、もちいる國。
そのようなこの列島の言語精神からみると、「・・・こゑのまにまに言(こと)をなして、萬(よろづ)の事を口(く)ち豆(づ)からいひ傳へ・・・比國にのみ繪(かた)をもちいざる(語意考)」-中国や古代インドアーリア系言語が表象をもっぱらとするに比べ、この列島では、もともとイメージ化、表象化を避けてきたところに、最大の特徴がある-という真淵の見解を追い風にした場合、李白の月や、それを真似た蕪村の「月天心」の月も立派な月には違いないが、それは中華鉢へ浮かべた表象、ポンチ絵にすぎないことになる。
とりあえずここでは先史から有史ともに一貫して、物にも言にも等しくはたらきかける否定のモメントをもつわたくしたちのもののみかたの基本軸を、それが実体化を果たしたとき、その周縁に物を正しく物たらしめ、言を正しく言たらしめる場を創りだすことから、中華座標や天竺座標、そして欧米抽象座標との比較を容易にするために、作業仮説を構成するキーワードとして、わたくしたちに備わる唯一で独特の座標軸と呼んでいる。そこからさらに中華座標軸とインド・アーリア語族の抽象座標軸、それにこの列島の地軸である具体座標軸との三本軸の言語体系をズラシ見ながら各言語における「ことば」と「もの」のあり方を具体的に比較検証している。ハイデッガーいうように、己の影を踏み越えてそこから歩みでることはできないのが、言語にそなわっているア・プリオリ性である。それぞれの言語はそのままでは、自己検証することは叶わない。そこで特集「日本語は函数構造をした中間言語である」で欧米言語精神のうみだしたJAVA言語概念と比較して列島独自の中間言語の考え方を提案したように、解明作業をやりやすくするため仮の中間視点を設けながらすすめている。
戦後もおわり、第三の核汚染の脅威にさらされるあらたな時代(昨年来、哥座(うたくら)が懼れていた事態だ)が到来し、もうそろそろいままで封殺していたこの系統の違いを正面切った主題として積極的なものいいをしてもよい時機なのではないか。
第八章 宇宙を正面突破する
その意味で、日本思想の問題点を、「自己不在。主体性の欠如。正統も異端もなく多様な外来思想をプロットする座標軸もなく、原理に対決する覚悟もないために、外来思想をただ空間的に雑居させるにすぎなかった。」という丸山眞男の指弾は、ながく戦後思想界を代表するものの見方であったが、それらは、もっぱらわたくしたち自身の地平に立った批評ではなく、西欧近代座標上から自身を俯瞰的に眺めた見方にすぎなかった。だから、肝心かなめのわたくしたちに備わる否定の相をもった独自の地軸の存在や、それが担う積極的な意味、そしてそこからひらかれる窮めつくせないほどダイナミックな荒野には踏み込めなかったのだ。そのへんが、上空飛行型思考と揶揄される由縁である。
一方、こうした近代主義者の作業に比べると、1959年の草間彌生の「水玉の天文学的な集積が繋ぐ白い虚無の網によって、自らも他者も、宇宙のすべてをオブリタレイト(消去)する」と宣言して、わたくしたちのはるかな深みから独自座標を軸に存在論的問題を提起し続けた彼女のシリーズ作品の方は、西欧造形芸術や近代主義を超え、(上下左右もなく反復し、無辺、無窮で無構成の彼女の作品は、千葉茂夫いうように抽象絵画ではない。空間やタブローへと観念や事物を抽出し、再現、再構成されてなったものではないのだ。)彼女の心身と引き換えに、わたくしたちの根ざしている時間の欠落したただひろがるばかりの地平の存在と危険きわまりない列島独自文脈にそなわった否定の相の存在論理を具体的に展開し、あきらかとすることに成功した稀有な例である。それはひとえに、彼女が自身と宇宙との関係を知におとさず、俯瞰した立場からみることを拒否し、その意味を了解した上で、自身のこの血の通っている痛みある具体的存在をそのままに、そこから、この得体の知れない宇宙をどうどう正面突破するという離れ業をしでかすことができたからに他ならない。この列島におけるはるかな深みからの革命的で正鵠を得た仕事を成してきたといえる。
第九章 列島独自の芸術・物理空間
ここでいったん、これまでの論旨を補足してレジュメにしてみると
一、「芸術・思想空間と物理空間はともに同じ座標系のもとでは、同じ言語OSのコマンドの支配を受ける。」それはちょうど、同じ太陽風に吹かれると地球の両極点に現れるオーロラは同時刻に相似形をなしているようなものである。欧米、中国、印度、この列島にあってもその事情はまったく同じである。それぞれの国で、当該言語OSのはたらくプラットフォーム上で、両ジャンルはパラレルな発展と進化をみせてきた。
二、「わたくしたちには普遍化された時間と空間座標は、昔も今も存在していない。代わって、否定のモメントをもつわたくしたちの物のみかたの基本軸が存在する。」それはアポリアな問題を孕んではいるが、物そのものを地軸としてそこではじめてひらく列島独自の
- ここで作業仮説のための用語として仮設定した「不理・非象・無辺・無窮」という - 「否定の相」をもった座標軸の存在である。その座標上で物と言の両面にわたる並列関係としてこの列島固有の芸術と物理が展開されてきた。抽象化された座標系の許ではじめて有効になるはずの自然・社会諸科学や、造形芸術、時間芸術としての音楽は、わたくしたちにとっては、ほんとうは無いものである。受容はしてきても、それらはわたくしたちの周縁にある物事のひとつとして受け止められてきたにすぎない。ただし列島における言語は「物」を対象化して普遍化した概念を構築したりイメージを再現するなどの表現をしない代わりに以下四、におけるように表現未然の中間言語として具体的な「物」「言」と関わり、その関わりのなかで「物」「言」の排列を定めていく。その排列が純一化したものがここで列島固有の否定相をもつ座標軸とよんでいるものである。
三、「科学・思想空間、芸術空間が拠って立つ基盤である抽象プラットフォーム自体を受け容れてこなかったので、それらを前提とする主観や客観、時間や空間など定義され意味を内包する基本概念やそこから構成されるいかなる論理も自己のものとしては存在し得ない。」かえって、この列島の先人たちは、みずから意志して、抽象化、普遍化を仮構のものとして退けて、表現未然としての中間言語のはたらきで物と言の実体化を果たそうとする。
四、「列島における「物」「言」「身」の各言語は「物」を対象化して普遍化した概念を構築したりイメージを再現するなどの表現をしない。表現を忌避し表現未然の中間言語として具体的な「物」「言」と関わり、その関わりのなかで「物」「言」の排列を純化させようとするばかりである。つまり世界をみづからの内へ表現として取り込むのではなく自らの言語をまず物化しそれを機縁として、その周縁のひろがりへ「物・事」を直に継起させようとはたらく。」
それを座標軸代わりにしたときにそこで生じる「無辺で無窮」の独自フィールドの麗しさと、そこにはたらく物の力学 (「不理・非象」とここで云っているところ)のことわりを排してイメージ化を呼び込まないこと
- そこで惹きだされるチカラのはかり知れなさとを誇りとしてきた。そのチカラをこの国独自のことばのくらしや芸術、そして物の製作に活かしてきている。これらの心性の核は別項でも確認済みだが、先史縄文早期から現代にわたっても変わるところがない。
五、「いまもこの列島の現代芸術の主流は、抽象された座標のもとで、そこにイリュージョンとしての造形空間を創ることではなく、また概念そのものをなぞるコンセプチュアルアートでもなく、列島特有の時間と空間の秘密とかかわりつづけることで、物そのものがひらく窮まるところを知らない具体的で独自なる場を開拓し、そこにはたらく力学に真美を求め続けている」

ネイティブ・アメリカンや、私たち列島
の基層言語*)は分節化を嫌ひつねに物
を一連の全体として、そこで言葉を手が
かりに物に聴き入ろうとする。一方、近
代人は世界を分節化しコンテキストとす
ることをもって知と称するが、それでは
ネイティブなことばの活きた力学は理解
できない。文化人類学や比較言語学の知
にはかんじんな物の命が抜け落ちている。
1990 有
*)このあたりをさらに踏み込んでみる。前章では、同一の言語文化圏であるかぎり、いかなる国のいかなる時代においても、「物」と「言」は位相を違えたおなじものの両局面である。という基本原則について触れた。そのことは当該芸術空間と物理空間とは、ともに同じ言語精神の許ではひとつの基本座標を共有しているという意味に言い換えることができる。そこでこの原則をさらに応用することで以下の冒険が可能となる。Aという言語精神座標系において、北の極にはたらきかける言語法則を精査確定することで、一方の南の極にはたらく物の時空間の法則が策定できる。そのはたらき方の波形は実際に南の極の波形を策定したはたらき方と重なるはずである。
それは系のことなるβ言語座標系においても妥当する原則である。その文化圏が過去に無文字文化であったとしても-それはこの列島の事情についてのことであるが、当時作成された「物」が遺って在る限り、その「物」を精査し、そこにはたらく法を確定すれば、古代の文字なく、手懸かりがないと思われていたそのネイティブな言語までも、その当該時代に遡ってそこにはたらく法則を形式論理的に余すところなく再現可能である。いままで、こうした試みがされてこなかった最大の原因は、同一の言語文化圏であるかぎり、「物」と「言」とは、位相を違えたおなじものの両局面であるというあらゆる言語精神文化にも共通の視点を言語解析の基本原則にまで育て得なかったところにある。次の原因は、サンスクリットと古代ギリシャ語との比較言語学を列島言語分析の外部規範にしたところから来ている。すなわち、明治以降のわたくしたちは、この列島言語系とはまるで異なった欧米サンスクリット系の言語学の視点を導入したために、そこにそなわる概念思考という古代印欧語独特の観念的限界性を、ものの見方にかかえ込んでしまった。そこに由来したものである。
ここであらためて注意しておくべきはABC系言語圏にはたらく法則をもってして、αβγ系言語圏の「物」や「言」を確定することはできないという事実である。南北アメリカ大陸のネイティブ種族言語を、200年の歴史しかもたない西欧言語学で分析しても翻訳的な外形上の意味以上には、内容的な成果を期待できないという意味である。両文化圏をそれぞれ内的に活き活きと理解できない限り、両者間には誤解しか生まれないだろう。この列島でみられる学問・芸術混乱の大半の原因も、天竺・中華・欧州の大陸言語系と列島言語系列はまったく異なる言語系であるにかかわらず、無理に一方の系にしか通用しないカテゴリー規範を列島の「言」と「物」へと導入し、ツジツマあわせのハリボテ体系を間に合わせで繕ってきたところにある。(それは多分に、そこにおける物の法則(自然科学法則)が共通であるようにおもえるところから、系を違えた二つの文化圏を束ねるワンワールドがあると夢想し、錯覚するところから生じた誤解なのである。)舞踏や現代美術などのアートシーンや俳句短歌といった古典文学を体験してみればすぐに了解できるところだが、明治以降の大学でいまだに信じられて思考基盤になっている「わたしたちから離れたところに、ワンワールドとして共通の時間や空間が存在する。あるいは、わたくしたちはそんな普遍的当為空間へと向かっている」との思いは、まったくの錯誤である。欧米系言語空間で育ってきた人に、歌・俳句のような言語空間や舞踏空間の具体的現実化はサロン的な文化交流は別として、まったく不可能である。モノ派のような現代美術空間も列島でいうあるがままに生かそうとする空間創造は文法体系の類似した日本語・朝鮮語であればなんとか可能だが、中国の現代美術や欧米芸術ではできない。当然にその逆もまた真である。言語系を違えればまったく似て非なる世界であるからだ。そもそも似る必要などないし、芸術の名の下に固有文化を他国へ押し付けることもまたおかしい話だ。ビジネスや生活レベルの翻訳でコミュニケーションが可能なので、つい人は同じで言語が違うだけだと錯覚し、ワンワールドなる世界を夢想してしまう。この錯誤から抜け出せる時期は、名所旧跡として観光地化した比叡山や高野山の天竺・唐の学問がそうであったように、この列島の明治以降の欧米大学システムが完璧に解体されモニュメント的な役割を振られたそのあと、さらに半世紀ほどはかかるだろう。
これらの事態を芸術空間と言語空間において、もうひとつ具体的な例のなかにみていきたい。千葉成夫いうところの、いま現代美術で流通している「ポイエーシス(作品創作)からプラークティス(実践)へ」という概念がそれにあたる。この構造は内容的には、戦前の時枝誠記が、ソシュール批判を踏まえて、言語が内容を保持しているとする欧米寄りの言語構成観にたった言語論」から「言語の主体的表現過程それ自体を問題とする言語過程説」を提唱したことに対応するものだ。
しかし、この事態はまず美術空間については、欧米自体が前時代の近代知の残滓を一掃しようとする芸術学問の革新動向であり、つぎにわたくしたちにとっては欧米造形概念にたいする列島独自文脈の自覚のプロセスである。こうした両義的状況においてモノ派、ポストモノ派の双方にもともと欧米の社会人類学や言語学の流れのなかで現象学的に記述された用語であるプラークティス概念が適用されると、いままで強調してきたように言語的には大陸系とまったく系が異なる列島の言語空間は混乱し、当然その独自「物」空間自体の展開も阻止されてしまうだろう。そしてまたもや欧米言語精神のアンフォルメルの文脈に置換され、よそよそしいオブジェクト空間へと引き戻されてしまう。それを危惧する。
一方で、時枝誠記の言語過程説は、列島独自の言語をそのはたらき自体の方法から把握しようとして多大な成果をおさめながら、表象など基本概念は、乗り越えるべきかんじんの旧来言語構成観から借用しているために、欧米言語学の大枠から完全に抜け出せているとは思えない。もっともソシュール批判のための論であって、欧米言語学そのものと対峙せんとしたものではなかった。そこに情報不足の戦中という状況の限界があったと思われる。
結局、両者の動向はともに欧米視点を越えていこうとして成果を出しているにもかかわらず、いま一歩そのエッセンスが時代限界のなかに留まってしまっているようにみえる。その理由をすべて状況のせいにはできないはずだ。それは「物」と「言」とは、位相を違えたおなじものの両局面であるという視点のもと、欧米言語精神との決定的な相違の自覚と対決の姿勢が不足していたからであろう。たぶんに時枝国語学と同時代の西田哲学にもみられるように欧米の「物」の法則体系(近代自然科学法則)は列島言語精神とは相を違えているとおもわれていたにもかかわらず、不可侵のものとして、そこへ各論を準拠させてしまう他なかったことが来たした結果なのだ。それは人麻呂など少数は例外として、飛鳥以来わたくしたち列島の外部、この海の彼方にワンワールドにつながる世界共通の動かしがたい絶対規範が存在し、「言」による法則も「物」による空間則もそこに拠ったものであるはずだとする一種の根強い列島ゆえのコンプレックスからきた強迫観念あるいは、信仰がもたらした時代限界なのである。
第十章 近代科学空間の本質
ところで、ここまで、同じ座標系のもとでは、芸術空間と物理空間は、どんな言語体系のどんな時代にあろうとも、等位の関係にあるという仮説のもと、「列島独自の芸術空間と物理空間としての言と物も、ともに同じ座標を共有し、そこで同じ力学のもとパラレルな関係として、窮まりどころのない周縁という列島独自の場を生みだしていること。そしてそこにわたくしたちの心身も含めた物事すべてが定まって具足してくる」ということを、この列島の生活レベルのことばも含めた事例にみてきた。そこですくなくともその仮説のアウトラインは確認できたはずだ。
ここで、もうひとたびこの列島の独自座標から、わたくしたちの極微の視点と周縁の力学のもとに、西欧近代空間の位置の定まり方を西欧近代美術空間を軸にして「見ゆ」というかたちで追ってみる。まず、そこには、奥行きや左右へのひろがり、またパースペクティブな(透視図的遠近法の)視点設定とにわたり、時代時代の抽象座標を二次元支持体あるいは三次元の場へと移し変えて、そこで物事を再現視しようとするイリュージョンを本質とした西欧近代の造形空間が透けて見えてくる。(
- ここでいうこれらの再現性の概念とは、歴史的にみてもイエスキリストのRe-surrectio(Re-surrection)復活というキリスト教神学の中核概念を構成していることがわかろう。しかも、現代科学成立の柱として科学的再現性Re-producibilityにも等しくはたらきかけている原理なのである。-
)
同じ座標系のもと、同じ言語OSのコマンドの支配を受けるのであれば、この西欧造形空間とパラレルな関係にあるはずの近代自然科学空間や社会科学空間の本質も、また近代造形空間と同じものであるはずだ。
- その自立的正当性がどれほど実験における再現性や、方法論的実証性に保障されてゆるぎないものにみえようが、また近代に至ってその成果の影響が地球規模になっていようと、そこにわたくしたちはいまもなお幻惑されつづけてはいるが、
- こうした先入観さえ拭うことができれば、 この近代自然・社会科学空間の本質もまた、西欧芸術空間とおなじ抽象座標を共有したところに由来する等位の関係にあり、その場で事物を再構成して再現視しようとするイリュージョンに基づいたものであるという推論が、常識に逆らったもの云いになりはするけれど、先ほども見た神学と科学が成立する共通プラットフォーム上の再現性の概念でも見たとおり、否定することはできずに成立するのである。
その場合でも依然として、自然科学や社会科学こそ中立の立場から普遍真理を求める客観性の学問で・・・その根底にイリュージョンや幻想性が存在するはずもないという見解はもっともらしいし、いまも多くの人が信じる常識であり、そこからの反論はなくなることはないだろう。
しかし、抽象プラットフォームのもたらす欧米の主観・客観対立の構造の設定自体が、すでに偏向した世界観の証である。さらにそこにおける客観性とは、たとえば測定に持ち出すモノサシ自体の定義とその妥当性はもちろんのこと、その適用においても、基準点やデータの取り方のあらかじめの取り決めなしにいかなる測定値は無効だ。また、処理段階においてもパラメーターの設定次第で、データ解析の方向性が決定されてしまうのだから、つねにそれらの背景にある社会や時代の意識的、無意識的要請を無視しては成立しえないことになる。つまり自然・社会諸科学の客観性とは、リアル世界のほんの一部分を目的なり共同幻想にそって捨象・抽象し、任意にきりとった括弧附きの限定的客観にすぎないのだといえることになる。もちろんこうしたことは、あらためていうほどのこともなく、現在の欧米においても周知のことがらとなっているはずだ。むしろ、欧米に準拠したわたくしたちのナリスマシの視点こそが、抽象座標へうかんだ仮象を実体と信じて疑わない呪術世界へと、堕ちこんでしまっている。
翻って、ひとたび時空の欠落したこの列島の無辺で無窮の立ち位置から見えてくるものがあるとすれば、それは、西欧造形空間も科学空間もその本質は同じものであり、プラットフォームを共有した両者ともに、そこに浮かぶ美しく、しかし、はかない虚構の姿である。
その後、近代物理空間がニュートン力学から現代物理空間へ、相対性原理や量子力学時代へとかわっていくにつれ、近代西欧芸術空間の対象も所与の外界から自己意識という内界まで拡がり、従来の、パースペクティブ性と古典的空間三次元性は廃棄されていったが、外界と内界を抽象座標系へ再現し、再構築しようとするその本質に変わりはない。その点をくりかえすと、欧米のオブジェ指向の現代芸術空間と進化とどまることなき現代物理空間(それに基づく情報空間も含めて)とは、いまも、パラレルに発展していく関係として抽象プラットフォーム上にある。当然そこに根ざしたところの本質は両者が共有しているものと想定できる。
クラシック時代においても現代においても欧米芸術空間と、科学空間との相互関係の構図、そして両者が根ざすところから規定される本質そのものにも変わりは無い。両者の違いは、そのイリュージョンの再現を美術・音楽の芸術空間という文化制度にそって再現するか、あるいは、抽象座標の領域内で相対的な実験による再現性を確保した上で、応用可能な現実態までもっていくかどうかの違いである。
いまでは芸術作品の自立存在はそのアウラとしての概念芸術と、その残存であるオブジェ・アートとに分離解体され、芸術空間と物理空間の区別は判然としなくなってきているけれど・・・。飛躍した例でいえば、この延長上に、テクネチウム、ネプツニウムなどの人工放射性元素やキメラという自然界にはなかった空恐ろしい存在の誕生があるのだろう。しかし、これらもイリュージョンを本質とした抽象座標系から現実空間に投影されて実現された現実態のひとつにはちがいない。すくなくともわたくしには、そう見えてくる。前世紀末の西欧幻想絵画や幻想を主題やタイトルにした音楽作品の氾濫からみても、また、その後のコンセプチュアルアートとオブジェ・アートの両極へ引き裂かれて、もはや両極間にうまれた真空が従来の造形空間の変容にすぎない様式空間で繕うこともできなくなっていた動向からみても、当然、その文脈の行きつく先にはキメラをうみだしてきた現代のこの抽象物理空間があった。
挙句、イリュージョンがそのまま現実態にすりかわってしまったならば、その瞬間からそのイリュージョンを本質として可視的、可聴的再現の提示の役割を担ってきた従来型の欧米芸術空間は、その役割を終了する他はない。芸術空間は、それがこれまでの文化制度のうえで担っていた意味を失ない、それ自体としては成立し得ないことになった。同時にそれはまた、その本質が芸術空間と同様の幻想性に根ざしたものである自然科学空間、社会諸科学、情報空間も、それらが拠って立っている抽象座標系プラットフォームそのものへの問い直しが始まらないことにはもはや本来の価値を失ってしまったことを意味している。
後記
哥座は、箱物としての概念の住処に安住せず、ことばを翼に、概念とその内包する意味という構造を越えて、たまきはる内なるおもひを天翔け、見ることや概念演算による思考形態に代わり得るわたくしたちの「見ゆ」というあり方、「おもひ」のありかたの独自幾何を深めゆきたい。そこに根を置いた視座から、それを梃に、未来の自然・社会科学や芸術のあるべき姿を追求していく。それが学問の使命と信ずるものである。
二0一一年五月二十一日未明
附記
この論の冒頭にかかげた(先史から有史を)- つらぬく棒のごときもの- とは、もちろん「去年今年貫く棒の如きもの」という虚子の問題句を下敷きとしたものだ。この十七文字には、この列島における時の流れる様が、正月というたった一日のそこにはたらく新旧交換のドラマツルギーが、みごとに集約されている。さらに、深読みすれば、普段にあっての時空軸の裏には、いつもは気がつかないが、抽象化できず、表象化もできず、見えず、対象化を許さない、というわたくしたち独自の否定相をもった座標軸が確固として存在し、この表現し難いものはそれが正月ゆえにかろうじて列島の時間性として顕在化して来るのだとして、それを、たとえていうならば「つらぬく一本の棒のごときもの」なんだと、云っているのだ。そこまで虚子が意識していたかどうかはわからないけれども、すくなくとも詩的言語として、虚子の無意識の存在了解のもとに、掬い取られて具体的な「こと」として現成してきたことばであると、私はそう受け止めている。
なお、この小論の目的は、ひとまず歴史的文脈は無視して、先史から有史までの物と言を、それぞれの文化ジャンルを越えたところで、現代美術、和歌、俳諧、身体芸術を、さらに、この国が受容してきた印中思想や欧米自然科学、社会科学を、そんなすべてを、「つらぬく棒の如きもの」という、抽象化できず、表象化できず、対象化を許さない「わたくしたち独自の座標軸」のもとに
- あくまで現代美術の私的実作作業を梃子にしながら - 読みかえていくことにあった。というより、この小論をその本格的作業のための手がかりをつかむ試論として位置づけてきた。ここでその核心にわづかながら触れ得た。そんな感触があったので、この試論をプロット代わりにして、独自方法論による実証性と論理性をそなえた本格的立論の機会が、近いうちにやってくるだろう予感がしている。そこではもうひとつ踏み込んだ視点から、列島独自の否定相のもとでは、「物と言は位相を違えたおなじものの両局面である」ということを顕かにできるはずだ。そこではもはや、上位概念で括りながら概括抽象していく従来思考法の適用はできないだろう。・・・いまからそのときがくるのが楽しみである。というのも、列島における先史から有史までをつらぬくこの独自なる否定の相のもとへ、すべての物と言を創造的実作作業という独自検証にかけながら読みかえ、そこで得た結論にそって、従来の学問常識を廃棄していく作業は、質量と光速度との関係式をエネルギーへと還元し、森羅万象の現象をシンプルに説明していった現代理論物理学の作業プロセスに似て、あるいはそれ以上のまったく未知の惑星の系列の異なった純粋数学を解いていくような楽しみがあるからである。
............
この試みの作業過程で、こちらの不勉強や誤解により、美術界や古典文学界、そして考古学の諸先輩方に対して礼を失したところがでている可能性は否定しきれない。そこは、ひとえにこちらの浅学を恥じ入るばかりであり、ひたすらその寛容を希う者であります。
はじめに返る
.................................................................
About
us

.................................................................
注)推奨環境:XPかビスタ。14か17インチ。Explorer 5.5以降。なお、バイオなど一部製品やマックで、縦書きレイアウト他機能不可。
注)オリジナル論文以外の、古典目録に収録されたコンテンツは、韻文空間を探求する哥座(うたくら)が、美学研究用に、基データを縦書き表記変換したものである。内容に一切手は加えてない、本文に直接関係のない 前書など、若干だが、割愛した箇所がある。よって文学資料としての精確度を 求める向きは、 しかるべき専門文学データへ直接当たることをお薦めしたい。
ウタクラ・哥座

