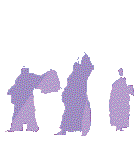�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Í��a�̏W�������@�`�I�єV�M
�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ |
�E�^�N���@�ژ^
|
|
�@ �@�@�u�b�N���� �@�F��Select�@ �@�@�� ���l�̌� �V���v�z �@�@�� ���{�Ƃ��ӕ��� �@�@
|
|
|
|
|
�@�@
���������ʍ���
|
�@�@�@�@�@�@�@�莢�t�V���[�Y�@�u���Ӂv
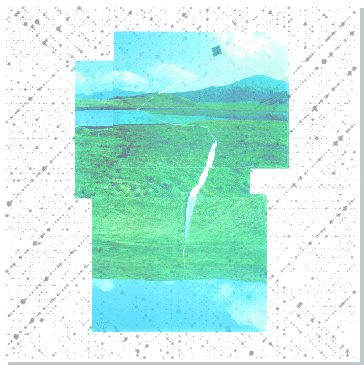
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@A �ES �EO�@�F��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�ӂ��̍��͌����ɂ����A�܂��i�ʂɈӎ��͂��Ă��Ȃ�����ǁA����قǂ܂łɖ|��ʉ����A�܂�IT���ō��ۊԂ��k���ȃR�~���j�P�[�V�������펞�͂�����悤�ɂȂ�������ɂ����āA����ȍ��ۉ����ゾ���炱���Ȃ̂��u�������̂��̂̎~�ߕ�����̂̕\���̎d���͈��ɑ�\�����嗤�̂���Ƃ͂ǂ������{�I�Ɉ���Ă���̂ł͂Ȃ����B�v�ŋ߁A�����������ۉ��Ƃ͋t�s�����Ⴂ�̊��o�₻��ɔ����f�p�ȋ^��̐����@������Ȃ��Ă����B����͌|�p��i�̐��삾���łȂ��A�Ƃ��ɍ��ۊԂŕ���������Ă����K�v������̂�˂��l�߂Đ��삵�Ă����Y�ƕ��ʂł́u���̂Â���v�̌��ꂩ������̎�̈�a���̐����オ��悤�ɂȂ��Ă��Ă���B��ʓI�ɁA���̂̎�e�ƕ\���ɂ܂�銴�o��l�����̑���͖����̗��j��n��A�C�y�����āA�������痈�鐶���K����Y��i�Ȃǂ̊��̍����痈�Ă���̂ł����āA����͐��E�̐����̃��x�����k�����Ă����ɘA��A���Âꂻ�̍����������Ă����Ǝv���Ă����B�܂��A��ꂪ�ȗ�����Ă�����{��́A����\���@���嗤����Ƃ͋t�ł��邪�A����當�@��̈Ⴂ�ɂ�鍷�ي����AAI��|��Z�p�̌���ɂ��߂��������U�������邾�낤�Ƃ܂ʼn]���Ă����B����ɂ��������������������A�݂����璊�ۊT�O�ݏo�������Ƃ̂Ȃ��������{��́A���x��������藣���ꂽ�����B�̌���ł���B�̂ɁE�E�E�B�Ǝ����`�I�Ȍ���i���̊ϓ_�������Ƃ��Đ��E�̎�e�ƕ\���̍��ي�����������Ă������B
�@�����̈�ʐ��́A����̖�����ړI�́A�n�悪�������Ă�����͗��j�i�K�̑���ɊҌ��ł��鍷�ł���A���邢�͕����I�ȑ����̈Ⴂ�ł���A�ǂ̌�����{���I�ɂ͏I�Ǔ����ړI�������̂ł���A������Y��i�Ɍ������Ȃ��R�~���j�P�[�V�����c�[���ł���Ƃ���B�܂茾���Ώۉ����ė��j���W�i�K�ŊςĂ������Ƃ���ߑ㌾��j�ςƂ����ׂ����̂��炫�����ł���B
�@�������F���o�[�V�����X�̖{�_�Ŗ��炩�ɂ���悤�ɁA���̋Ⴂ���̌����������炩�ɂ��Ă����ɂ͂���ɗB���j�ϓI���ω��w�W�����邾���łł͂Ȃ��A���҂̌���ƕ�������Â��Ă��錾��v���b�g�t�H�[���ɂ܂ʼn���K�v������̂��B���̒�������Ă����ƁA���Ҍ��ꂪ��Â��Ă���ʑ���Ԃ͂܂�Ő����̂������\���̊W�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩���Ă����B���܂ł͂��̏ؖ��ɂȂ����������Ɣ��@����Ă��Ă���B���Ҍ����ԊԂɑ��݂��鏃���ɍ\���I�Ȃ��̈Ⴂ�́A���ҊԂɂ͖|��Ȃǂł͉˂��n�����Ƃ̂ł��Ȃ���m�ꂸ�̐[�������݂��A���̑���͂ƂĂ����_�╶�@�_��������������̂ł͂Ȃ����Ƃ��킩���Ă����̂ł���B
�@�F���́A�u���̂̌����̍��قƂ������̂́A�e���ꂪ�����ė��v���b�g�t�H�[���̍��قւƊҌ��ł���B�v�Ƃ�����������������Ɖ����Ƃ��ė��ĂāA����́u���v�ɂ����ẮA���t���甪��W�A���������ĘA�́E�o�~�܂ł��A�܂������ɂ��Ă̂��܂ɓ`����`���̐��ʂ������킹�Čp�������Ă��������A���ꂪ�����ė����Ă����Ǝ��̃v���b�g�t�H�[���̍\���m���Ƃ������߂Ă����B���̏�ő嗤�n�̌���v���b�g�t�H�[���̍\���Ɣ�r�������Ă݂��B�����Ɂu���v�ɂ����ẮA��j�ꕶ���猻����p��i�܂ł̗�����X�ʁX�ɁA��̓I�ɂ݂āu���v�����������ۂ̂��̗Ƒ嗤�̎���Ԃɂ�������W�n�̈Ⴂ��A����ɕ\���̍ۂ̗��҂��������Ă���v���b�g�t�H�[�����炭��_���̈Ⴂ�������A���̍��ق���j�I�ɂ悭�m��ꂽ�A��Ɍ|�p��i�Ȃǂ̋�̗�Əƍ������Ƃ��s���Ă����B���ƂɁu���v�ɂ����Ă݂͂Â���E�C���[�W�́u�莢�t�V���[�Y�v�ɂ݂���q�̂Ǝ�̂Ƃ̌W��荇���ɓI���i�����u���v���u�g�́v�Ƃɂ��v�l����������샌�x���܂ł��̂Ƃ����̏�ƑΘb���Ȃ���̊e���Ƃ����H���Ă����B���̒n�͑����Ƃ̂��̗͂��Ƃ��p�����[�N�V���[�����ăC�^���A�i�|���A�V�`���A�̃G�g�i�܂��G�[�Q�C��ɕ����ԃi�N�T�X�A�T���g���[��A�܂����ߓ��̍����ŃA�����J�嗤�i�o�z������A���̂ق��}���[�⒆�����k���A���N�����ɂ܂ŋy�ԁBN.Y�̍��ۖf�ՃZ���^�[�r���ł̍�Ƃ͂���9.11�̏\��N�O�̂��ƂɂȂ�B���̍ہu�g�v�Ɓu���v�Ƃ���̉�����v���Z�X����u����ɂȂ�Ȃ����v���E���o���A���̂͂��炫����B��̎�|����Ɂu�Ì��v��u�e��_�l�v�����āu�ꕶ�v�A�u������p�v�܂ł̌��ɂ������Ă����̂����݂́u�F���v�ł���B
�@�����Ŕ����ł������́B����͂��܂�ɑ������A�ꌾ�ł܂Ƃ߂�Ȃ�u���ꐸ�_�ɂ́u���v�Ɓu���v�ƂɈ�т��Ă͂��炭�ے�̌`������������قȒn�������݂��A���̂����Ɂu���ƌ��v���W�J���ė���v�Ƃ��������ł���B���̍��W��ł�
- ����͂������W�Ƃ͌ĂׂȂ����̂ł��邪 - ���̒n����ł́A�̏ۂ⒊�ۂ��������ċ�̓I�Ȃ��̂����߂Ă����͊w *��)���͂��炢�Ă���B���̏�ɂ����Ċώ@�҂̎��_�͂��̒ꂩ��d������A����܂ł̊e���ۂƂ̊W���Ƌ��ɗ��Ԃ��ɂ���Ă��܂��B�u���v�����̎�q�ς̕��ʖ��R�Ƃ������ׂ����E�ւƊҌ����ꂽ�Ƃ��A���̏�����L����u���́v�u�ЂƁv�͐��E�̂ǂ��ł��낤�Ə����o���Ȃ���u���v���u���v�֒��ɖ����Ɍp�N�A������͂��炫�Əo����ƂɂȂ�B�����ɂ́u�A�̂����̂����r�܂ʂ��̂ЂƂ̐Q�o�߂͂��������Ȃ����߁v�Ƒ��̂ɂ܂ʼnr�܂�Ă����قǂɓ��{�́u���v�Ɓu���v�Ƃɂ͂��炭���͕����I�Ȉ������ł������B���ہA���̎��o�I�Ŗ��m�ȗ�́A���������ɑ��邱�̗̌��ꐸ�_�̎��o�������炵�����ʂ̌�����p�u���̔h�̍�i�v�Ɓu�����v�ɁA�����Ă܂��������������ЂƂ́u���m���v���ۂł������ޗǂ����ĕ����ւƈڍs���鎞��́A���ɂ������ċN���������ꐸ�_�̎��o���ۂ̂ЂƂł���I�єV�������A�V�X�e���������l�\���̕�����������铂̂ЂƂЂƂ̗e�ɁA�͂�����ƌ��Ď�邱�Ƃ��ł���B�i�������̖{�`�͕\�ӕ����ɂ��A���t�@�x�b�g�̂悤�ȊT�O�\���P�ʂƂ��Ă̕\�������ɂ�������������w�₱�̍��̌���w����E��������Ō�Ɏc���ꂽ�������̕����̌n�ł���B���́u���v���琬������������铂͊����Ƃ����\�ە������_�@�ɂ͂��Ă��邪�A���̊�����^�����ȗ������Ă��������ɐ��������̂ł͂Ȃ��B���������̖{���̊J���̒S����͍����I�ɂȂ��Ĕ������ꂽ�������̓����Ǒ��i
813�`867�j��Ղ̍��t�ɂ��邳�ꂽ�ŌÂ̕������o�y������݂Ă����̓����̊J������O�ꂵ�Ċ����Ƃ����\�ۂ��u�����v���Ă�����@����݂Ă�����ɂȂ���̂ł͂Ȃ������͂��ł���B�P�ɗ����̂��߂ł͂Ȃ��A�u���v�̌������ɓY���ĕ\�ۂ�L��������������������������ɁA����̂܂܂̕��̏o�������~�߂邽�߂Ɏl�\���́u���v�����̂͂��炫�����ɂ��������ĂЂƂЂƂO�s�����A�Ō�ɋI�єV�ɂ���ăV�X�e���A�b�v���ꂽ�̂��l�\��������铂ł���B���̕������͕������̂����̑g�ݍ��킹���W�Â���A��铎��̂��\���`�ʂ��邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��B�\�������T�O��Ӗ������Ȃ����{�I�����̌`���Ƃ��āA���̋�̉^���║���A�����Č�����p�̂��̔h�܂ł����т����̂Ɠ����A���̈�̏���Ȕr�g�ӂ��ނɉ���������Ƃ����`���ƁA�Ƃ��ڂ�����Ė{�����ƍ�����A��������u���v�̘A���Ƃ����o�������n�܂藈�������Ƃ������Ă���̂ł���B�Ȃ��Ȃ���������Ȃ��ł��낤���̎��Ԃ͍��W�n�̖������E�ɂ�����u���ƌ��v�̂�����ł���B�u�ʏ���ʂ��v�Ƃ����钷�̈��������A���]����Ƃ���œ������Ă������̕��̘A���ُؖ@���S�N���̑O�ɂЂƂ茾�����Ă���B
�@��O���̒��۔��p�A�R���Z�v�`���A���A�[�g��C���X�^���[�V������f�W�^���A�[�g����ɂȂ��Ă���{�I�ɂ̓^�u���[�֍Č��`�ʂ��邱�Ƃ�{���Ƃ��鐼���n���p�B�������ʂ��邩�����Łu���̔h�v��u�����v�̍�i�͓o�ꂵ�A���o�I�ɗ̌��ꐸ�_�ɂ��ƂÂ����Ƃ��납���i�����̂ɂ��Ă����B����������畨��i�͈�E�������p�A�����̔��p�ƌĂ�A�̔o�Ɠ��l�ɑ��|�p��������Ă����̂ł���B���̂������Ɂu���̔h�v�ƕ̏̂ŌĂ�Ă����B���́u���̔h�v�̖����蒅�������j�Ɓu����v�Ƃ��������̂Ƃ��Ă̐^�����ƍ��ʂ���Ă����������̌ď̂Ƃ��̒蒅�̗��j�Ƃ͋O����ɂ��Ă���̂ł���B�������ߔN�A���s�����Ǒ���Ŕ��@���ꂽ���t�r���ɏ����ꂽ�����������ɂ��̂̏o�y�́A���������j�����ɂ�镽�����������̂̌������J���Ƃ��̒蒅�Ƃ��������ė]�肠��B���㌾��w�̃A�v���[�`�������Ȃ����̕��������邢�͂��̌�̕���������������Ƃ��������̌n�ƃ��m�����ꂽ���̑̌n�Ƃ́A�ꕶ�ꖜ�N�����ĘA�̘A��ƌ�����p��i����т��铖�u�F���v�́u����͍��x�ɔ������������ꂽ�`������ł���܂��A���Ԍ���ł���i�ڍׂ͚F���[�~�ōu�`�j�v�Ƃ��闧���ʒu�ȊO���痝������邱�Ƃ͏����ɘj���Ă�������Ǝv����B�����ꂱ�̑�_�ȗ\�z�ɔ�����D�ꂽ�v�z���o�Ă����Ƃ��́A�����납��������v�����낤���A�܂����̏o�������҂���B�j
�@���̔h�n���̎��g�̔��p����ɂ����ẮA���ۊO���̒n�ɂ����Ă�����̂͂��炫�ɂ��������ė}�g�ƂƂ��ڂ�����A�����т�����i�����̂ɂł����Ƃ��A���̍�i�ɗ�������������̂ЂƂ����͐l��̑���������L����������Ȃ��炶�Ԃ����v�����Y��Ă��܂��Ă����܂Ȃ����ɏo��A��������ӂ����ь��߂Ȃ����Ƃ����Â��Ă����炵�������ɑ����Ă��Ă��邱�Ƃ���i��ʂ��Ď��g�ɂ��`����Ă���B�����������Ƃ͗�O�����ł͂Ȃ��B���Ƃ��O�q�|�p��i�ł��낤�Ƃ��O���l�����{���ݔ��p��ʂɐG�ꂽ�Ƃ���������̂̋��ʍ��̂ЂƂɏ�����������ƁA�����ȑO���炢���Ă����̂��B���������o����ς�ł����ƁA�����Ԃ̈ʑ��̈Ⴂ�Ƃ������̂��A���̍Ő[���̂Ƃ���ł͗�����n�ɒʒꂵ���͂��炫������悤�Ɋ������Ă���B�܂肻�̂͂��炫�l�́A�B��A���ՑÓ��������Ƃ������Ă���嗤�n�����Ƃ����ʕ������E�ȊO�ɂ����̗��ꐸ�_�̂悤�ɕ\�����Ȃ��\���Ƃ��A�Ώۉ�����O�ꂽ�u���v�̑��݂Ƃ��A�����Ⴆ�Ȃ��炢�܂��������͂����Â��Ă�������ЂƂʂ̌|�p�E�����n���E�����ꂼ��ɋ��L����Ȃ��瑶�݂��A���ҊԂ�ʒꂵ�Ȃ���N���X�I�[�o�[���n�������Ƃ��āA���܂���X�Ɨ��ꑱ���Ă���\�����������Ă���̂ł���B�������A�嗤�n�̃o�[�`�������ꐢ�E�ɂ����Ă͂����ɋy���A������ړ������̌��㐢�E�ɂ����Ă��A���̂܂ɂ��Y�ꋎ��ꕕ��Ă��܂��Ă������E�ł���B
�@���̗̑�ꎍ�l�A�l���C�́A���̗��L�̒n���̑��݂ɐG�ꂻ�̂���l���u���������ʁv�Ƃ���ł͂��炭���̂̂�����Ƃ��āA�����ւ�������ĉr�������Ă���B����ɂ�������炸���̌�A���̓Ǝ��n���́A���̑��ݎ��̂�A�܂��Ă��̐ϋɓI�ȈӖ��������ʂ���Ƃ肠�����邱�Ƃ͏��Ȃ��A�ނ��낻�̑��݂������A�킽���������̕��ՓI�_���v�l��j�Q���ĉȊw�I�v�l����ĂĂ��Ȃ����������ł���Ƌȉ�����Ă����B���̂킯�́A�O���I�ȗ��R�ɂ����̂Ƃ������A���̒n�����̂����Ƃ���������ł���-�Ώۑ��݂ƂȂ蓾���A�������ł��Ȃ�-�Ƃ��������\���̊A�a���ɁA����̑唼�̌���������ł��邩�炾�Ǝv����B�����ł͏ڍׂ��Ȃ����A����́u���v�Ɓu���v�Ƃ̗��ǖʂɂ����Ċ�فi���������₵�j�������Ђ����N�����Ă����B�Ɠ����ɁA���̊��S�����݂����Ă��邻�̍\���̂��܂�̂����݂��ɂ́A�����̕s�C�������������Ă��܂��قǂ��B����͊H�삪�u���ԁv�ňÎ����错�R�Ƃ����s���ɏd�Ȃ�B���̏o���́A����Ƃ����錻�ۂ̂����ɕ��т���\�ۂ�ϔO�◝�i���Ƃ��j����Ȃ�R���e���c�����ʂɊ���A�����Ƃ��ăX�P���g���ȍ\���̂֕ϊ����Ă��܂ӂƂ������̗n�����L�́u�����v�̂͂��炫�ɋ��߂��邾�낤�B�����ɂ����āA���̓��L���`���i�G�C�h�X�j���ꁖ����A�́A���W��ɕ������Č����\���Ă����嗤�n����̂͂��炫�Ƃ͂܂������قȂ����͂��炫�������Ă���B�����������\���I�ɏ���ǂ��Đ������悤�B�܂��u���v�Ɓu���v�Ƃ͕����̐ߖڂ��ƂɁu�����v���͂��炫�Ƃ��錾�ꔟ���̔r����������悤�Ƃ��Ă���B���ɂ���生���Ԃ̔r�Ɖ����āA���������S�̂Ƃ��Ēʂ����ЁA����Ȕr�ƂȂ������̂Ƃ��i��������̍��W��Ő�������ƁA�����P���Ӂ@Das
sind die Stunden da ich mich finden �E�E�E. - �����ł킽�������Əo����̂Ƃ�
- �Ƃ����Ώۉ����ꂽ�q�̂Ɣ��f��̂Ƃ���v������q�Z���̍\�������W������\���������ł����`������ɂ������B����������ł́h�Ăɂ��́h�Ƃ����u���v�̂������ꉹ�ꎚ�ŁA�N�ɂ����l�����P�Ȃ݂̂���A����ȏ�̊����Ȏ�q�Z���̍\�������ʂ������`��������g�����Ȃ����Ƃ��ł���B�j���������̓Ǝ��Ȃ��̎��ԉ����ꂽ�`�����ꂪ���N�ƂȂ�A�������疳���̊U�܂Łu���v�̔×��p�N���n�܂肾���̂ł���B�݂�����g�ӂ̍\�������ʂ������ƁB���̏��������������ꂽ���̂Ƃ��ADas
sind die Stunden �O���̕����͍Č��I�`�ʂƂ͂܂�ňقȂ������@�ŁA���邪�܂܁u���v�̃_�C�i�~�b�N�ȋP����������Ă���B���������n����̌�������̎��Ԃ̊j�S��B�ꌩ���ɑ����������̂́A�钷�́u���̋ʏ��v�������đ��ɂ͖����B���̓Ǝ��`������͂��̕��ƌ��̎v�l�ɂ����āA���ׂĂ̌��ۂ����W��ւƃv���b�g���Ώۉ����Ă����Ő��E���Č��\�����邱�Ƃ������Ďv�l�Ƃ���嗤�n�̌���Ƃ͂����炩�ɂ��������v�l��H�������Ă���B�n����̌`������͂�����Ώۉ������݁A��q�̓�����������{���_�ɂ����Ƃ��h�������̓��̂��́u���́i���j�v�h�ƁA���́h���̏W�ꂽ�o����ǖʂł���u���Ɓi���j���i���j�v�h�̂͂��炪���߂Ă�������n�܂肾���B���̂₤���ł��Ă���Ƃ��������悤���Ȃ��B����́A�܂ÁA�嗤�n�̍��W�T�O�ɗ��炸�A����������ς��ɗ͔p���邽�߂ɁA�ł����邩����m�I���_��Ƃ���`�I�Ȃ��̂Ƃ��āu���v�ɓY���u���v�ɒ��ɂ�����邱�Ƃ���{�Ɂu���́v�̐�������Ă����u�F���i��������j�v�̌o�����炫�����o�ł���B���ɂ�������ƂɁu�Ì��v�Əƍ������A��l�́u�_�v�Ƃ��荇�킹�A�u���v�Ɓu���v�Ƃ̓������������߂�ۂ̍�Ǝ��̂������Ă��ꂽ�u���Ɓv�̒�܂肩���ł���B����ɍŌ�ɟ�̂悤�ɒ��ϔO����A�����ɂ̂������`���`�����킽���������̐挱�I�����ɑ�����@-�@�L��ߑ������̖��Ғœ����ł����Ƃ���̊O�s�̂悤�ȁ@-�@�k�Ȃ̂ł���B���ꂪ�����I�ȏo�����ݏo���f�Ƃ��Ắu���v�ł��蓯���Ɂu���v�Ƃ��ēꕶ�̊e�`������A�́E�A��̕t�������̌`���A�����Ē��̓��̌`���܂ł���т��邱���ł�������Ȃ��̓�����������Ǝ��`���̌`������̐��̂ł��낤�B�ȏ�̂��Ƃ����Ă���ƁA�嗤���W�n����ɂ͑Ó�����u�ݕ������V�X�e���ƌ���̗��ʃV�X�e���Ƃ̔�r�ސ��Ƃ��A��ʐS���w��Љ�w���̉Ȋw�I���@�����p�������́A�����ėB���I�A�ϔO�I�ϓ_��O�q�\�����w����̐�������w����̂������̃A�v���[�`�v���`������ɓK�p���邱�Ƃ݂͂ȓI�͂Â�ł��邱�Ƃ��������Ă���͂����B�ݕ��̗��ʎ��̂����������A�ے�������ސ����Ó�����̂͒��ۍ��W��ł̉��z���Z�ɂ����Ȃ��B�����݂͂Ȃ�������A���֓K�p�����Ƃ����z�ɗ��r�����䂦�̖{���I�Ȏ�_������邱�ƂɂȂ�B���������̕ӂ�̓I�����C���ł͂Ȃ��F���o�[�W����3.03�ȍ~���I�t���C���u���ł��ڍׂȘb�����邱�ƂƂȂ�B�u�m�o�v��u�v�l�v�ɂ����Ă��u����v�ɂ����Ă��嗤�n�̃o�[�`�����Č�����Ƃ͂܂������قȂ����͂��炫����������Ǝ��̌`������Ƃ������̂��킽���������͕��i�̕�炵�̂Ȃ��ł͎��R�Ɏg�����Ȃ��Ă���B��������ӎ�����Ă͂��߂Ă��̌���̓����\���̓��ق��ɋC�t�����ƂɂȂ�B�������A���ۂ�Ώۉ����ĕ��Չ������^�������Ƃ߂Ă��������Ȃ��]���w��ł́A���̗��_��ŏ��z���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ǂ��łĂ��Ă��܂��B�������ɂ���ꂳ���݂�����Ȃ����̕ǂɁA����̎v�z�Ƃɂ�����𖾂̂��ׂĂ̎��݂͂��܂����ĝ��˕Ԃ��ꑱ���Ă���̂��������B����ɗn���̂͂��炫���琶�݂�����g�ӂ��Ƃ炵�o�����Ƃł���̂܂܂̑��ݐ��E�Ƃ̏ƍ����͂��낤�Ƃ��Ă���`������B�����ɑ嗤�n���W�̂͂��炫���炤�݂�����O�����E�̍Č�����{���Ƃ���o�[�`�������z����B���̗��҂̈Ⴂ���u���v�Ɓu���v���ʂɂ킽�閵���̂Ȃ��������猩�����Ē蒅�����Ă������̍�Ƃ́A������n�̕`���Ă����]�����E�ς̌����������܂�A�����Ɂu���v�Ɓu���v�ւ̍Ő[���֓����邱�̈���A�I�����Ⴆ�Ȃ���ΐ�j���猻�セ���Ė����ւƂȂ���u���v�̘A���Ƃ��Ă̂��炽�Ȕg��݂����Ă����͂��ł���B
���܂ł́AE=mc �ւƊҌ����꓾��Ɏ������A�X�����ۂ��l�̍��W�̊w�ɐ����߂镨�����E�ɂ����ẮA�킽�����������T�O��A�����ɃJ�E���g���ꂻ��𗘗p�����Ă���B�������ʍ��ŐG�ꂽ�悤�ɁA���ۂ́A���̏�ɂ��̗̏Z�l�͎����̍����������ė��Ȃ��������A���ꂩ����^�ɐg��u�����Ƃ͂Ȃ����낤�B����u���t�͑��݂̏Z���ł���v�Ƃ���n�C�f�b�K�[�B���̌��\�ɂ݂Ď���̂̓��S�X�Ƃ������ۍ��W�n�ɐ��������Ƃ���̓`���I�����v�ٓN�w�̉����Ɉʒu�Â�����鐢�E�ςł���B�N���V�b�N�M���V���ȗ������ϔO�N�w�A���`�|�p�̐i���ƃp�������Ɍ��ۂ��Ă����ߑ㎩�R�Ȋw��Љ�Ȋw���E�A����炪�������Ă������W�n��ƁA�킽�������������܂��Z�݁A���������Ă��鐢�E�i�ʍ��j�Ƃ͂����炩�Ɍn�������������E�ł���B
�ւƊҌ����꓾��Ɏ������A�X�����ۂ��l�̍��W�̊w�ɐ����߂镨�����E�ɂ����ẮA�킽�����������T�O��A�����ɃJ�E���g���ꂻ��𗘗p�����Ă���B�������ʍ��ŐG�ꂽ�悤�ɁA���ۂ́A���̏�ɂ��̗̏Z�l�͎����̍����������ė��Ȃ��������A���ꂩ����^�ɐg��u�����Ƃ͂Ȃ����낤�B����u���t�͑��݂̏Z���ł���v�Ƃ���n�C�f�b�K�[�B���̌��\�ɂ݂Ď���̂̓��S�X�Ƃ������ۍ��W�n�ɐ��������Ƃ���̓`���I�����v�ٓN�w�̉����Ɉʒu�Â�����鐢�E�ςł���B�N���V�b�N�M���V���ȗ������ϔO�N�w�A���`�|�p�̐i���ƃp�������Ɍ��ۂ��Ă����ߑ㎩�R�Ȋw��Љ�Ȋw���E�A����炪�������Ă������W�n��ƁA�킽�������������܂��Z�݁A���������Ă��鐢�E�i�ʍ��j�Ƃ͂����炩�Ɍn�������������E�ł���B
���������A��O�̊j�����̋��Ђɂ��炳��邠�炽�Ȏ��オ�������A�������낻�낢�܂܂ŕ��E���Ă������̌n���̈Ⴂ�𐳖ʐ������Ƃ��ĐϋɓI�Ȃ��̂��������Ă��悢���@�Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�@���̈Ӗ��ŁA���{�v�z�̖��_���A�u���ȕs�݁B��̐��̌��@�B�������ْ[���Ȃ����l�ȊO���v�z���v���b�g������W�����Ȃ��A�����ɑΌ�����o����Ȃ����߂ɁA�O���v�z��������ԓI�ɎG��������ɂ����Ȃ������B�v�Ƃ����ێR���j�̎w�e�́A�Ȃ������v�z�E���\������̂̌����ł��������A�����́A�����ς�킽�����������g�̒n���ɗ�������]�ł͂Ȃ��A�����ߑ���W�ォ�玩�g����ՓI�ɒ��߂������ɂ����Ȃ������B�̐S���Ȃ߂̂킽���������ɔ����Ǝ��̒n���̑��݂�A���ꂪ�S���ϋɓI�ȈӖ��ɂ͋C�Â��Ȃ������B���̂ւA����s�^�v�l�Ɲ��������R���ł��낤�B����A���������ߑ��`�҂̍�Ƃɔ�ׂ�ƁA1959�N�̑��Ԝ\���́u���ʂ̓V���w�I�ȏW�ς��q�����������̖Ԃɂ���āA��������҂��A�F���̂��ׂĂ��I�u���^���C�g�i�����j����v�Ɛ錾���āA�킽���������̓Ǝ����W�����ɑ��ݘ_�I�����N���������ޏ��̃V���[�Y��i�̕��́A�������`�|�p��ߑ��`���A���̗ɂ�����͂邩�Ȑ[�݂���̊v���I�Ő������d���𐬂��Ă����Ƃ�����B
������A�@�`�������F�@���Ƃ��`������ł���Ƃ��������ł̌������́A���̂܂܁u���v�̐��E�ɓK�p�ł���B�́A�A�́A�o�~���A�u���v�̔����r��ł������A���Ƃ��Ό�����p���m�h�̍�i�Q���A�]�����Ď��_�̑��^�T�O�̂悤�ɁA��̑��̑��^�\���Ƃ��Đ��������̂ł͂Ȃ��B�u���v�̌`������Ƃ��ėƎ��̈�A�̃G�C�h�X�Ƃ��Ă̔����r���̂܂܁u���v������p�Ȃ̂ł���B���Ē��ی|�p��i�̃I�u�W�F�̂悤�ɁA���ۍ��W��ɐ������Ă��鉼�ۂƂ��Ă̕\����i�ł͂Ȃ��A���������Ĕ��p�ł����p�����ł��Ȃ��B���Č|�p�W����������E���A�����n�����قȂ鐢�E�ɂ�����u���v�̔r��Ȃ̂ł���B�嗤�n���`��i�����̃v���b�g�t�H�[���Ƃ��̎����͂����ɂ݂͂�����Ȃ��B������e��邠������W�n�͗��Ԃ��ɂ���ċ�̓I�ȍ�i���͂��߂Ƃ��邠�邪�܂܂̕��̘A������������Ђ낪�閳�ӂŖ����̐��E�ɂȂ��Ă���B���̂����炳�܂ɂ��邢�͊v���I�ɋt�]�������E���������Ȃ����Ƃɂ͂��̗ł�������p��]�����Ă��̐S�ȂƂ���͔��������Ă��܂��A����͉��Ĕ��w�T�O�����p�����O������݂̂��ĂɂƂǂ܂邵���Ȃ����낤�B��j�ꕶ�̈ꖜ�]�N�ɂ킽��u���v�Ƃ��Ă̓ꕶ�y��ɂ������Ă��A������p�́u���v�ɂ͂��炢�Ă���̂Ƃ܂��������Ȃ��`������Ƃ��Ă̐挱�I���͂��炢�Ă��邱�Ƃ��ȉ��ł��Ȃ���A���㉽���I�������Ƃ��Ă�����͌��n�I�Ȏ�p���E�̐��쌴���ł���ꂽ���̂��Ƃ��A�l����������̍�i���Ƃ��������b�e����\���Ďv�l��~�����܂܂ɂȂ邾�낤�B����͊��Ⴂ���͂Ȃ͂������̂��B��p���E�̖��͓ꕶ�ł͂Ȃ�����ɂ����ӂ��킵���B�o�y�i���݂����A��j�́A�\�ۂ◝�ɘf�킳�ꂸ���܂���قNJo�����Ă�������ł���B
�@�a�̔o�~�͌|�p�Ƃ��Ă̈�s���ł͂Ȃ����w�ȂǂƂ����W�����������u���v�Ƃ��Ă̌`������ł���B�`���r����`������u���v�̂͂��炫�ɂ��킸��31������17��������ɒZ���r�j�b�g�ł����Č`���̏��ꐫ���ۏႳ��A���̌���A�~�N������}�N���܂ł̂����鐢�E�̑f�ނ������Ƃ������悭�\�����������Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B����Ɠ����ɁA���̔h�̍�i�͌|�p�Ƃ��Ă̑��^��i�ł͂Ȃ����ۊT�O������A���i�j�ޔ����\�������������u���v�̌`������Ƃ��Ă�͂蔟���r��ɂȂ��Ă���̂ł���B���̂��Ƃ͎��͍�Ǝ��̂͂悭���o���Ă���B����͂�����Ƃ����̍�i�\�肪�悭������Ă���B�֍��L�v�́s�ʑ��t�A���Z���́s�W���t�A���؎u�Y�́s�����t�s���Ԃ̏ꉻ�t�s�E���t�s�S�̂̂����ނ��T�E�U�t�s����w�t�s���ʁt�s���E�x��t�E�E�E���X�B
�@���̂�����A�Ǝ��̌`������̓������悭���킵�Ă��鐛��i�ɂ��Č�������������ߑ���p�ك`�[�t�E�L�����[�^�[�{�]�M�v���́uPlaza
Gallery ���W�ɂ悹��1992�N�v�̒Z���������茳�ɂ������̂ŁA���Ɉ��p�Љ���Ă����������B�u�����ɂ�����܂ŁA�����������ꂪ���̂Ƃ炦��������Ƃɂ��ď\���ɘ_�������ł��낤���B���Ȋ����������݁B����Ζg�Ə|����������m�ɁA�ނ͎��Ă���B��i������A�����ɂ����I�Ȃ����Ŏ���̌�����D��Ȃ��A���̂����Ȃ鐸�_�̉�����z���Ă�܂Ȃ��B��i���̂��̂ɂ͂��ꂾ���̋�Ԃ̍L���肪����A�����͂�������ʂ��ċ���ւƏ����Ă������Ƃ��炠��̂ɁA���̊j�S�͂������������Ȃ��ǂɎ���Ă��邩�̂悤���B���邢�͂��������Ă�������������Ȃ��B���؎u�Y�̍�i�͂Ȃɂ������C�f�A���ȑS�̂̈ꕔ�A�������͂��̉e�ɉ߂����A���邢�͂܂��ނɂƂ��Đ��삷��Ƃ͐Â܂肩���������ʂɂӂƕ��̐����A���̔g��A����Ƃ����̕��ɂ��₮�G�ؗт̂��߂��̂悤�Ȃ��̂��ƁB���C�܂���Ȍ���������邳���Ȃ�A���؎u�Y���̂ЂƂ��A�ЂƂ̔������ȋ�C�A�Ȃ����S�I�ȃG�l���M�[�̉�ŁA��i�Ƃ͍��X�ƕω����Ă�܂Ȃ����̋ǖʂ̂ЂƂɂ����Ȃ��Ƃ������邾�낤�B���؎u�Y�@-�@����ɂ��ā@1992.11.7�@�v�@�{�]�M�v��
�@�`�ʕ\���Ƃ����Ӗ��ł́A���̔����͂��ꎩ�̂ł͂Ȃɂ�����킳���A�\�ۂ��C���[�W�������N���Ȃ��B���ÁA�����ɂ����Ă̊w�҂������u���v�ɉ����Ď��i�j�ށh�Ăɂ��́h�����ꎩ�͈̂Ӗ���ێ������A���Ǝ������قɂ������̂ł���Ɖ��߂��Ă����̂Ɠ����Ӗ��ł���A���̔r��̂Ƃ��ڂ��Ƃ��ł���Ƃ���Ȃ�A���̔h�̍�i���܂��A���̍�i�ɑ������Ƃ��A���̂Ƃ������ۂi�j�ތ`������Ƃ��Ắu���v�̔����r��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��m�F�ł���̂ł���B
�@��A�̂��́u���v�Ɓu���v�̔������������낵���P�������ăv���O���~���O����T�O�ɒu�������Ă����Ȃ���̍\�����L�q�����\�[�X���G���[�Ȃ��u�R���p�C������Ď�q�������Ƃ��Ắu���v���̂��̂ɓǂݎ��ꂽ�Ƃ��A�����ł͂��߂Ă킽���������̂��Ƃ��u���v�Ƃ��ċ�̓I�Ɏ~�ߓ��Đg�̉��ł������̂ƂȂ�v�Ƃ�����B���������̎��Ԃ͏�ɃA���r�o�����g�Ȍ����������Ă���B�����Ƃ��Č�����Ɠ����ɕ��Ƃ��ĕs���ł���Ƃ������������\�ł���B����͂��̔����\��������A�̔r�C���h�E�A�[���A�ꑰ�⒆���Ƃ������嗤�n�_���v�l�̎���ԍ��W�̑��^���_�ɉf�荞�܂Ȃ��Ƃ����A�@�\�I�ȈӖ��ɂ����錩���Ȃ��\�������Ă���B�����ł����u�X�P���g���v�ȓ����\���̂ł���B�Ώۑ��݂Ƃ��Ă̕�����g�����āu���v�Ɛ���A���������N�Ƃ��Ė����́u���v�̘A�����n�܂肾���A�t�ɂ��̊U����h����h�Ƃ����d���Ō����Ă���u���v�ł��邩�炾�B
�@�F���́A�����Ƃ��Ă̊T�O�̏Z���Ɉ��Z�����A���Ƃ𗃂ɁA�T�O�Ƃ��̓����Ӗ��Ƃ����\�����z���āA���܂��͂���Ȃ邨���Ђ�V�Ă��A���邱�Ƃ�T�O���Z�ɂ��v�l�`�Ԃɑ��蓾��킽���������́u����v�Ƃ���������A�u�����Ёv�̂��肩���̓Ǝ���[�߂䂫�����B��0���N�܌������[��
�u���m�点�v
�@���܂܂Łu���v�Ɓu���v�Ƃ̗��ǖʂɂ킽��A�F���͗n���̌��o��Ƃ𑱂��Ă������\�z��葁���u���E���v����������ۂ̍\���̊j�S�����W���Ƃ��邱�Ƃ��ł����B����܂Łu���v�Ɓu���v���ʂɂ킽�铝�ꗝ�_�̌��@�Ƃ������̂��A�̖����ȍ~�Ɍ����Ă݂Ă��Y���w�̃i���X�}�V������绂���������ƂȂ��Ă����̂͂����炩���B���Ƃ��Ύ��R�Ȋw�ɂ�������̓Ǝ��ᔻ�����̌��@�����Ȋw�҂ɂ͌��q�͂Ƃ��������x�́u���v�̃G�l���M�[�̃R���g���[���͌����I�ɖ����ł���B�Љ�Ȋw���`�q�H�w�Ȃǐ�[��w�̊e����ɂ����Ă�������B��������������Z�p�̌����͍��ې�����o�ςƕ��G�ɗ��ݍ����Ă���A����ɑΉ��ł���u���v�Ɓu���v�Ƃɒʂ���ᔻ�������Ȃ���Ύ��R�E�Љ�Ȋw�̂���狐��e�N�m���W�[�͂߂��߂������̈�œƑ����͂��߂邾�낤�B������������������̂悤�ɕ��������ӂƂ���ꕔ���͎҂����͖{���Љ�{�ł���ׂ����̂ӂ����ċ��嗘�����Â邽�߂̗~�]���u�Ɖ����Ă��܂��͂Â��B�����A���q�͊֘A�̊e�Ȋw�҂ƋZ�p�҂݂͂Â���ւ�����v���W�F�N�g�ɂ����āA���ꂪ�ǂ�قǂЂǂ����ʂ������炵���Ƃ��Ă��A����͂ق��̃W�������̖��ł���A���邢�͈��p���ꂽ���̂ł���B�����炵�Ă����ɂ͎��g�͂��������W�������A�݂Â���̗���͐���ł���Ƃ����������Ă����B�R�P�P�͂��̍s�������������̔ߌ��̂ЂƂ��ے����Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�̐^�E���̔���̊�͐�j�ꕶ���猻����p�܂łǂ����Ƃ��Ă݂Ă��A�]�����w�҂������Ă����悤�ȑ嗤�n�̑��`����_���\�����ɋ��߂�����̂ł͂Ȃ��B����́A�́E�o�Ɠ����悤�Ɂu���v�Ɓu���v�̈�̌���`���r����Ȃ���̂ɂȂ��Ă��邩�ǂ����i�I�u�W�F�N�g�w���̃v���O��������ł�����PASS���ʂ��Ă��邩�ǂ����j�i�钷����ł��������ŏ��Ƃ��Ắu���v���ʂƂ��Ắu���v���т��ċʂ��P�����Ă��邩�ǂ����j�ɂ������Ă���̂ł���B���̂������o�[�V�����O�A�Z�O�ȍ~���I�t���C���u���ŏڍׂ��邪�A�́u���v�Ɓu���v�Ɓu�g�́v����͐l�̂m�ɂ���\������ł͂Ȃ���l�̐�������Ƃ��钆�Ԍ���ɂȂ��Ă���̂ł���B�����ɗ^���Ă͂��߂Č����Ԃɐ��肤�邱�Ƃł���Ƃ����Ӗ��ɂ����ẮA���̌`���i�G�C�h�X�j����ł���Ƃ�����B���W��O��Ƃ���Č����ꂪ��ςɋA�����Ȃ���Ђ����炻�̃t�B���^�[��̍Č��`�ʂ̐��m���ɂ��̖{���������Ă��邱�ƂƂ͑ΏƓI�ɁA����͒��Ԍ���Ƃ��Ă��́u���v�Ɓu���v�̔r��̖{���������Ƃ炵�A�܂����Ƃ��ΌW�茋�т����������ʂ��Ă��邩�ǂ����Ƃ����g�ӂ���Ƃ����������Ȍ`���̏���Ȍ��ѕ��ЂƂɁu���v�u���v�Ƃ�������F���̊J�����������Ă���B���i�p�X�j���ʂ�������炠��̂܂܂̕��E�����n�܂�A���ƊO�Ƃ͏Ɖ����������E�͋P����������Ă���B���傤���u�Ԃ̌A�i�����j�̊|����v�̂悤�ɏ���Ȕr���N�ƂȂ��ĊO���A���Ȃ킿�����ł͌F��̎R�ƕ�ɗ��̊C�Ƃ�Z�ʂ�����Ɛ^�̎�q�̗̂Z���Ƃ��Ă̏o�������u���v�̔×��Ƃ��Ă��̔g��͖����̊U�܂Ōp�N�A�����Ă����̂ł���B���i�p�X�j���ʂ�Ȃ��ƊO���ƗZ�ʂ����^�E���̏o�����͋N�����Ă��Ȃ��B�悭�Ă����R���ŏЉ���m�ԋ��̈ꎚ�Ⴂ�̋�̂悤�ɁA�`�ʂƂ��Ă̂������ƁA���ꂢ�����ɏI����Ă��܂��B���݂̍�l�͗��u���v�E�u���v�E�u�g�v�ɂ����Ă܂����������ł���B�y���F��������㕑���␛�؎u�Y�̍�i�ɂ�����Ƃ��i���j�Ƃ������̂�Ǒ̌�������ŁA�嗤�n�Ƀ��[�c�������̕`�ʍ�i�Ɣ�r���Ă݂�Ƃ����B�`�ʂ��ꂽ��i�͍��W��̂������Ƃ������Ɍ��肳�ꂽ����ɂȂ��Ă���͂��ł���B���̊O�ւƁA�Ƃ��i���j�͗���o�����A�L����������ɂƂǂ܂�������A�����֊g����o���Ă����Ȃ��B�i�����ł͌��ꌻ�ۂ��T�O�v�l����Ɣ�T�O�������Ƃɂ����������ނɕ����A������I�u�W�F�N�g�w���̃v���O��������Ŏg���Ă��钆�Ԍ���Ƃ����T�O�����āA���ꌻ�ۉߒ����i�K�ő����Ă���B�����̗p��͂����܂ō�Ɖ����T�O�ł���B�j
�@���������Ƃ�����e�ׂɌ����Ă����Ɨ̐^���̋K�͈͂��̔��̊�Ƃ͂܂�ňقȂ������̂ł��邱�Ƃ��킩���Ă���B�����ł�������m��C���h�A�[���A�ꑰ�̑嗤���̈��Ƃ��ă_�E���B���`�̍�i�������Ă݂悤�B�킽�������̏펯�ɔ����A�̐^�Ɣ��̊���猩���ꍇ�A�V�����g���[�ɑ�\����鉢�Ă̍\����`���w�̖{���͑��`�I���ۍ��W�Ƃ����ϔO�̃t�B���^�[��ʂ��Ċς����E�̎��̉�U�}�ɂȂ��Ă���B���W��ɍČ����ꂽ���̂́A�����Ȃ���̂��A�������̂��̂��̂ł͂��肦�Ȃ��B�����ł��̂̂��̂��͒D���A���̂̒��̋P���͎����Ă��܂��Ă���B���̈Ӗ��œV�˃_�E���B���`�̐l�̂̔������Ƃ������͉̂�U��ɍڂ������̂ɉ��ς��قǂ������������Ȃ̂ł���B���l�b�T���X�̐��̂͒����_�w����J�����ꂽ�l�Ԏ^�̂ł͂Ȃ��B�ނ���Í��̒�������~�ς��Ă���Ă�����́B����́A��͂�\�ۂ⌴���Ƃ����ϔO�ł���_�w����Ȋw��`�ɖ������������炽�Ȃ�Í��̋ł������̂��B���̂��߂�����\�����ϔO�I���ړI���ւ̗��}�}�Ƒ��Ă��܂��Ă���̂ł���B�_�}�T���e�n�i���i�C�I�ނ琼���͗L�j�ȗ��A�������g�����Ə����Ȃ��炽�������L��k���ł��Ȃ��ƌ��݂̐��������o�A�o�����ł��Ȃ��Ђǂ��j�q���Y���̃h�c�{�ɐZ�����Ă���̂��B�Ñ�M���V���̊ϔO�I�R�X���X���W���p�����Ĉȗ��A����ȏh����w�����Ă��܂������т����������ł���B
�@�~���m�̃T���^�E�}���A�E�f���E�O���c�B�G�����C���@�́u�Ō�̔ӎ`�v�̓����}�@������B�����̃C�G�X���_�Ƃ��ĕ������Č��`�ʂ���Ă���͍̂Č����Ɍ|�p�E�Ȋw�̖{�����������ނ�̐��_���W�n�ɂƂ��ĕK�R�̏o�����ł���B������W�̎�������[���_�ɕ��������C�G�X�̍Č����ꂽ���E�ɂ�����߂Ǝ͂��̐S������̋��|�͂����Ŕ��Ǝ��R�Ɛl�ԊJ���ƌ����������A�����_���ۏႷ��Ƃ����������Ń��[���b�p�̐l�Ԏ�`�͋N�������B�܂��A�ߑ�ɓ����Ă��炻�̔��ƉȊw�̉��l���K�͂Ƃ��ėA�����ڐA���Ă����̂��ߑ���{�ł���B���܂����_�E���B���`�̂����ЂƂ̌��삠�́u���i���U�v�̔��݂͗��ꐸ�_�Ƃ͑Ώ̓I�ȍČ����ꂽ���̃V���{���ł���A�����ɒ�Ȃ��̃j�q���Y�����B����č݂�Ƃ������ƂɋC�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�킽�����������ꐸ�_�́u���v�u���v����q�������R�̏�ɂ����āA���邪�܂܂ɋP�����邱�Ƃ��ł���B�嗤�n�̎�v����ɂ͌�������Ȃ��͂��炫����������B�O�������������A�T�O�K���������A�ے������A�`�ʂ��Ȃ����Ƃ��Ăɂ��͂Ƃ��Ӂu���v�̂͂��炫�ɓY�ЂȂ��玩�o�I�ɐ[�������邱�Ƃł��ꂪ�\�ƂȂ��Ă���B�ꌩ�P���ŗc�t�Ɍ����邱�̗���̍\���Ƃ��̋t�ߋZ�߂������̕s�v�c�Ȃ͂��炫���ɂ��ẮA�l���C�ȗ��A�����ꂽ���l�������ǂƂȂ��w�E���Ă������Ƃł͂���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�Ō�̔ӎ`�@�C���̌i�v �B�e:�F��
�@��������F���͗��ꐸ�_�̂��ׂĂ̔閧���o�[�V�����O�A�Z�O�ɌG�Ȃ����f�����邱�Ƃɐ��������B�������A���ׂĂ��I���e����ɂ���Ɓu���E���v�ɒ�����������݂������Ȃ���肩�u���v�̋P���������Ă��܂��B*�j�����ŁA���o�[�W�����ւƍ����߂����B�������A�I�t���C���ł͐V�o�[�W�����̈ꕔ���e�L�X�g�����A���������╨�̋�̓I�ȃp�t�H�[�}���X�Ƃ��č�i��C�u���c�֊������Ă����B���ⓙ�͚F�����w��������MAIL
��0���N�\�\�������
.........................
�@���x�����Ɂu�F���iUta!Kura)�v�̖ڎw���Ƃ���B
�@�����A�v�R�b�����Ē��x�ł������\�L�K����R�[�h���A���ɁA���E���ꌛ�@�Ƃ��Č��z����A �����̂��Ȃ��́A�j�Z���m�ƂȂ�A�n�C�p�[���̂Ȃ��ŗ��ʂ��Ă���o�[�`�����̂��Ȃ����z�����m�Ƃ����B�Ƃ������������邩���m��Ȃ��B ����A���͂�����������͈ꕔ�A�����܂ŗ��Ă��܂��Ă���B�Ȃɂ��Ƃ��A�T�[�o�[���ɏƂ炵���͂���āA���Ή�����A ���A���Ȕ����͂́A�����Ȃ���鍡���B���܂ɂ������č��x�`�h�ɃT�|�[�g���ꂽ���Љ�ł� �A�^�O�Â��ł��Ȃ����̑��ݓx�̓[���ɓ������A�o�[�`�����̌�������������Ă������ƂƂȂ邾�낤�B
�@�F���i��������j�́A�I�t���C���̎������{�Ƃ��Ă���B���܂̓������̊�ł́A����ɂ����u�ɂقЁv�E�u�݁v�Ȃǃ��[�J���ȑ����T�O�ɏœ_�āA�킽���������ŗL�̐g�̎��ɂ��ƂÂ����A�g�߂̐挱�I�C����Ԃ�T������B�������A�L�������킳�Ȃ��u���v�V�Z�p�v�B���̐i���ƕω����x�ɂ����Ȃ���A���A���Ŋl�������Â��ĐV����������ɁA�܂��A�I�����C����ł��u���v�̈Ӗ���s�f�ɖ₢�����A���A���^�C���ɏ��Z�p�̍���ɂ���v�z�͂��Ă��������B
�@�₪�āA���[�J���ȑ����T�O��A���̋Z��A�Ȃɂ��Ȋ��o���V�i�v�X���x���ŏ����邾�낤�B���ׂāA���̐��ɑ��݂��Ă�����̂ŏ��ƂȂ肦�Ȃ����̂͂Ȃ����炾�B�������A���̈�_�A�o�[�`�����ƃ��A���A����������Ώ��Ƌ�́A���邢�͒m�Ƒ��݁B���̍��{�W�������Ñ�̃M���V���ł���x�ł������ł��j�S�e�[�}�ł������悤�ɁA������A��U���Ɍ����ӂ����ѕ����̍ŏd�v�ۑ�ƂȂ��������Ă���ł��낤�B�F���i��������j�́A���̏��Ƌ�̂̊W����{�̖���������ɑk���āi���͂킽���������̐S���́A���܂��ɖ���������̑����������Ă���̂����A���̂��Ƃ��ؖ����j���̖����������Ԃ��茜��ɁA���̊T�O�ɋ��炸�A�ŗL�̕����A�g�̂����ɂ��āA���܂�쐫�I�ɉ𖾂��Ă�������肾�B���̍ہA�A�o���M�����h�ɑR����悤�ɘZ�\�N��Ɋ��ł͂��܂�A���m�h�A�y���F�A�Ȃǂ̗���ɂȂ����Ă������ƂɂȂ������O�����̂��̃Y�o���u��̉^���v�B�����ւ��������ǁA�������ĂĂ݂����B�|�X�g���_���̑�\�I�^���Ƃ��āA���E�֑傫�ȉe����^���Ȃ���A�����Љ�̂Ȃ��ɁA�ӂ����ш��ݍ��܂�Ă��܂����悤�Ɍ�����u��̉^���v�B�����āu���m�h�v���猻�݂ւ̗���B���̋Ȑ܂̒f�w�ʂɁA���𖾂̂悢���������������ł��邾�낤�Ɨ\�����Ă���B���Ԃ��E���E����������e������̔��畽���ɂ����Ă��A�\�L�������Ƃ������g�̏��V����̔g�ɐ���ł��ގ��f�w�ʂ��������Ă���͂����B-�u�����ꉼ�������̍b���̕ʁv���̏����Ƃ͂܂��ɂ��̗�ɂ����邾�낤�B
�@�@�@�@�@�@�@���@�L
�@�ӂ���Ȃ��ݐ[������̎R��O�l�̊C�ȂǁA�g�߂̎��R��W�u���̐g�̂́A���łɗ����ς݂́u��ԁv�̂Ȃ��ɁA�^�����Ƃ��Ȃ������ɑ��݂��Ă���B
�@ �u�F���i��������j�v�ł́A�u���Ɓv�u���́v���������]���Ă��邱�̖��ӎ���Ԃ��Č����A�����ւ̎����������Ă��������B���̕��@�Ƃ��Đ�ÁA�킽���������ŗL�̍l�����A�Ƃ�킯�A���Ƃɓ��݂��Ă���ŗL�̃��S�X�ɐG��Ă����B�Ƃ��Ɏ��̂̉C���ɓ����`�J���́A�����Ă����B�C����Ԃ̍��W���m��ɍۂ��ẮA�킽���������ŗL�̕��̂���̔�����҂Ӗ��ŁA��E���E���̊T�O�g�p�͂ł��邾���T���A���܂����i�Ɏg�p���Ă���Â�����́u���Ƃv��ÓT�́u���Ƃv���̂��{�������Ă���Ӗ���W�����ő�̎�|��ɂ��Ă����B���t�W�͂��߁A�����̉̐�̚F�A�o�~�A���AJ-POP�܂ł̂����u�C���v�́A�Ȃ������̏n���ɂ��A��l���p���ł����g�̋�Ԃ���j�A���R��ԂւƏ�����A�u�킽���������v�̋�ԃV�X�e���̌��^�ƂȂ�A��̓I�Ȍ����ƂȂ��Ă���B���邢�͋t�ɁA�킽�����������g�������a�������Ă���Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ �ǂ�Ȃɂ������Ȍ��ꕶ�����ł��낤�ƁA�W�u�������ŗL�̂��Ƃ����ݏo��������ɂ����A�q�d�̌�������A�^�̊��͂͂������炵�����܂�Ă��Ȃ����Ƃ�m���Ă���B�C���^�[�l�b�g�ȂNJv�V�I���Z�p��}��ɂ������ۉ�����ɂ������āA�O���������z�����Ȃ��玩�������ւ������Ă������Ƃ���@��́A����I�ɑ������Ă���B����Ȏ��ゾ���炱���A�����Ȃ鍑���܂��A�W�u�������̂������Ƃɂ͂��炭���t�̃`�J����@�����o���邱�Ƃ���{�ƂȂ�B�������o�ł��Ȃ��ł��ẮA�O���q�ϓI�Ɍ���፷���͐��܂�Ă��Ȃ����A���������A���̊፷���ɂ��ƂÂ��Ă�����������ׂ����E�ƑΘb����`�J�����N���Ă��Ȃ��B�����Ȃ�ΈႢ��F�ߍ����Ȃ���̐^�ɐ[�܂������ݗ����Ƃ������̂����蓾�Ȃ����ƂɂȂ邩�炾�B�������A���Ă̘_���I�v�l���Ƃ��A���̎��_�փi���X�}�V�A�ꍑ���p�~���ĉp��ɂ��ׂ����ƍl���Ă����̂����̍��̏��㕶����b�ł���B�����܂łЂǂ��Ȃ��Ă��A�钷���w�E����悤�ɂ��̍��̕����̍ő�̖��_�́A�]�ˎ��ォ�炷�łɁA�w�҂ł��낤�ƁA�����ł��낤�ƁA�啔���̂ЂƂтƂ��A�ꍑ��̎����ł��̂��l���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ł���_�ɑ�����B�قƂ�Ǖa�I�Ȃ��̏Ǐ�͒E������������ꂽ�������ɂ����Ă���ɐi�s���A�s����o�������Ȃ��������̈�r�����ǂ����ł���B
�@ ���R�̂��Ƃł͂��邪�A�Ǝ����ꕶ�����̎��̂Ƃ́A�����ɓƎ��̖@���͂��炭�e�����_�����̒��ł���B�����ɁA���̈ꌾ�ꕶ�����̎��_����A�y�͕����ɔ�r�A���f���āA�D�������悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��̂̐��_�����͑��݂ɕs�N�ŃA�E�v���I���Ȏ������B�Ƃ��낪�A���{�ɂ����閾���̌[�։Ƃ́A����̎��̂ł���a�̂��A����x�̂��́A���p�̂��̂��Ƃ��Ă������w�W�������֑ނ��A����ė����v�z�����`���ċ���҂��Ƃ������ƂɎ��܂��Ă���B�����J���̑��l�҂ł������̊�b���{�́A���w�i�T�䗬���`�w�j�◖�w�Ɉˋ��������̂ł����Ȃ������B���́A�R����`�I�ϓ_����A���́A������`�I�ϓ_����A�Ƃ��ɓ��̋���Ҏ��g���A�ꍑ��̎����ɂ��������{�I���o�����������킹�Ă��Ȃ������̂��B���̌Ñ㒆���W�����Ƃ̂��ƂɕҎ[���ꂽ�Î��L�A���t�W�ł����A�O���������������ɍۂ��ẮA�P�ǂ݂ȂǁA�Ì��i�t���R�g�j�����������߂̂��܂��܂ȓw�͍H�v���قǂ����Ă����Ƃ����̂ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]() �@
�@
�@ �R�X�����́A�������̑e�G�Ȑ��_�����܂��p���������Ă��錻�݂̋���E�����@�ւł��낤�B������킸�A�啔���̑g�D�����܂Ȃ��A���ׂĂ̊w��̑O��Ƃ��Ă���ꍑ��ɉ����鎋���Ƃ��������I�グ�ɂ��āA�������̌����D���`�̈������`�����̂܂܂ɁA�|��T�O�ɂ��ƂÂ�����_��W�J���Â��Ă���B����Ȕڋ߂ȗ�ɂ͎������Ȃ����A�ЂƂ́A�����{�̑�\�I���{��`�҂ɂ��u�o����|�p�_�v�ł���B���̓Ɣ�����`����Ă�����̂́A�ꍑ��ł͂Ȃ����ĂƂ����ꌾ�ꕶ�����̎�������݂��|�p�E�w��E�T�O�E�_�����B�ꕁ�ՓI�Ȃ��́A���ۓI�Ȃ��̂ł���A�ǂ̌��ꕶ�����ɂ��K�p�ł���Ƃ����ӖړI�M�����ł���B����͒��ÈȑO�ɋN���������{�̕��y�a�A�i���X�}�V�ۊ����a���҂̓T�^�I�Ǐ�Ƃ����Ă��悩�낤�B�܂��߁X�́A���Č����@�ւ́u�m�v�̍č\����͂��������̂ЂƂ̌��ۂƂ��āA�Y�w�����ł̊e��v���W�F�N�g������ł���A����Ȃ�̌��ʂ�ł���悤���A�������ɁA��[�I�Ȋw�p�����̐��i�ƉȊw�Z�p�̔��W���͂���A���ۋ����͂��������A�������I��Ղ����������[���E���コ���邱�Ƃ͑厖���B���A���̑O�̊w����̕K�v�����Ƃ��āA�ꍑ��ɉ����鎋���̂��ƁA�u�m�v�Ƃ������̂̒��g�̈Ӗ��������ǂ킽���������Ǝ��̂��Ƃɔ���郋�[���ɂ��₢�����Ȃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���̃v���Z�X���Ȃ��āA����A���A��������w�Ȃǂ̊T�O���^�p���Ă����A���j��������悤�ɁA�ꍑ��̖@�ɂ��ƂÂ������̂Ȃ��A�C���[�W���ꂽ�����̊T�O�^�p�͂����K��������������āA�j�]�𗈂��Ă��܂��B�ł������́A�i���X�}�V��������U���Ă܂���ʂ��Ă���A���̏ꂵ�̂��̊ϔO�I�T�O�ꂵ�ẮA���ȓ����I�ɍ����O�ɉ������肵�A�J���g���c�畉���ɁA���p�ȂЂƂтƂ̂������f�킵�����Ă���B�ꍑ��ɂ͂��炢�Ă��鎋�������o�����Ȃ����_�́A���ǂ́A�Ƃ��Ă����|��ϔO�������A�������͂�����A�ϑz���A�\�������������Ƀi�`�X���ɂ܂Ŏ����Ď����������{�̓N�w�j�Ƃ��������h����H�邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@�w��A�|�p�݂̂Ȃ炸�A��ʂ̐������x���ɂ����Ă��A�ꍑ��ɂ͂��炭�@�̎��o���܂��ł��Ă��Ȃ��i���ꂪ���Ƃł���l�ł���j�L�\�Ȗ����̍˔\�����������i���X�}�V����@�ւ̃V�X�e���Ƀ}�C���h�R���g���[������Ă���̂�ڌ�����̂͐h���B������l�̂���Ȏp�ɐG���͔̂߂�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@ �����킢�A�킽���������ɂ͐g�߂ȂƂ���ɃW�u���^�`�̖@�E���S�X���\�S�ɓ����Ă���a�́A�o�~�Ƃ���������{������B���̂Ȃ��ɂ́A�W�u�������ŗL�œ��g��́A���Ăł����Ƃ���̂��̂Ƃ́A�܂���������Ă��邪�A�Ǝ��̊ƁA�����A��{�I�ȃ��S�X�������Ă���B���̎�������{�Ƃ��ĉ��Ď��R�E�Љ�E���Ȋw�E�|�p�̈Ӗ���ᔻ�I�ɍĐێ悵���Ȃ���A���ۉ��ǂ��납�����̐��_�I�Ɨ��������ێ��͂ł��Ȃ����낤�B���L�ɂ킽���������̌��ꕶ�����ɂ��܋��߂��Ă��関���̊w��́A�����ď\�������ł͂Ȃ����A�K�v�����������Ă����B�N���V�b�N�M���V�������ɂ�����w��ɂ́A�܂��A���ׂẴW�������̊�{���Ȃ����y�⎍�Ɠ����Ȃ��̂Ƃ��āA�w�̗������K�{�ł������A�����Ŏ��R�����茵���Ȑ��I�Ș_�����w�ԕK�v���������B���R�킽���������̌���ɂ͂��炭�_���@�̏K���ɂ��A�l�҂݁A�Ҋ�������Ȃ���Α��o���Ƃ�Ȃ��悤�ȁA���i�̍C�ɂ܂݂ꂽ�ʑ��ϔO���P���A�ӎ��I�ȊT�O�\����펯�̈Ӗ����痣�ꂽ�Ƃ���ŏ����v�l���錵���ȏC�����v������Ă���B���Ȏ�����{�����鎩������̌����ȌP�����Ȃ��A���Ă̎����Ɋ�肩�����ăf�X�N���[�N�Ŋw�₪�ł�����A�|�p�����܂��Ƃ̐M�́A�����ȍ~�̊�������V�X�e���̌��E���炤�܂ꂽ���z�ɂ����Ȃ��B���������A�]�����w��A�����Ƃ����g�̌|�p��A���m�h�I�Ȍ�����p����ɂ�������Ă�������o������A���������̎����ł����Ă��܂��Ă���S�g�����̃}�C���h�R���g���[������J�����A�ꍑ��Ƃ������i�̂�����܂��̎����������邱�Ƃ��A�����ɂނÂ������A���Ԃ������邩�������͑̌����Ă������肾�B
�@�u�Ƃɂ����Ɋ��Ӂi�J���S�R���E�����ł͉��ēI���z�j�́A�̂����肪�������ɂȂޗL����v-�钷�B
�����ŁA���g�ɂ��A�l�ɂ��K�p�A�w�����Ă���̂��A�����Ǐ]���̊w���|�p���痣��A�a�́A�o�~��O������Ԃ�݂�����@�ł���B���Ƃ̂��ƂŁA����������w�������A�i���X�}�V�̎����������ɊϔO�I�Ȃ��̂ł��������S�ł��悤�B����́A���������҂Ƃė�O�ł͂Ȃ��B�]���w��̎��_����ꍑ��͂����Ƃ���ő��q�́u���ׁv�E���̌��ʂ����łĂ��Ȃ��B����ۂǂ̓V�˂łȂ�������A���̂Ȃ��Œ@����A��̓I�Ȏ�����Ƃ����Ă����ꍑ��̎����͂Ђ炩��Ȃ��͂����B�������āA��N������A�W�u�����g�̎����̉肪�łĂ��āA�]���̌|�p�E�w��ɂ�����u�m�v�̌��E�ɋ�̓I�ɂ��������߂��点��悤�ɂȂ�͂����B�������A�C���e���Q���`�����Ǝv������ł���l�قǐ��ƂɌ������@����邱�Ƃ��o�債���ق����悢�B����قǁA���j�I�ɂ���x�E�����E���Ă֊��Ă����킽���������̃i���X�}�V���_�̍��͐[���B���ɁA�u�̂����肪�������ɂȂޗL����v�B
�@ �Ȃ��A�����Řa�́E�o�~���Ñ�ւ̂������ꂾ���ŁA�������ɏ^������̂ł��Ȃ����Ƃ�f���Ă����B�����̓��ɂ͂��炭���Ƃ̖@���A�킽���������̐S�g�̐[���Ƃ���ł��܂Ȃ����������A�����Ƃ킽���������̖��������K�肵�Ă����͂��̂��̂�����ł���B�������Ȃ���A�����̉̐l�E�o�l�̑命���́A���������@�����ӎ��̂����ɁA���܂̓��{�̕����⌻����p�̒ꗬ���Ȃ��Ă��邱�ƁA����ɁA�|�p�A���R�A�Љ�Ȋw���܂߂��w��ɂ��A���̎��o�̓K�p���K�v���Ƃ������Ƃɂ͋C�t���Ă��Ȃ��B���邢�͋C�t���Ă����Ƃ��Ă��A���̓K�p��[������߂Ă��邩�̂悤�ɂ݂���B�ނ�̑������܂��A���ЁA�̉�̋����W�������Ő������Â��Ă��邽�߂ɁA�W���������Ⴆ�W�u���𗠐�A�����܂����ăi���X�}�V�̎����ɂ��肩������l��ւƕϖe���Ă��܂��̂��B
�@ �킽���������̍��̍���}���ك��r�[�ɂ́A�v���g���̃A�J�f���C�A�́u�w���w������̂��̖��������ׂ��炸�v�Ƃ���⼌����M���V����œ��X���������Ă���B���܂̃O���[�o������ɂ����Ă͂������̂��ƁA�ǂ�Ȏ���ɂ����Ă��A���Y�̗��e�����Ƃ��哱����w��Ȃ�Z�p�̓����͕K�v�ł���B�������A�M���V����⒆����A�p��A���w��AAI����ň���Ă����킯�ł͂Ȃ��҂ɂƂ��ẮA�O�����ꐸ�_�������w�Ԃ܂��ɁA���ɂ͂��炭�@�̑̓����ɂ������ƍl����͎̂��R�̊���ł���͂����B�g�����ꂽ���̖@�̎����Ƃ���ɂ��ƂÂ����Ȋw�I�Ǝ����@�_�̊m���Ȃ����āA���E�ɒʗp����n���I�ȂȂɂ����ł���Ƃ����̂ł��낤���B���ׂĂ̐[���v�҂ƁA�s�ׂ̍����Ƃ������̂́A�ǂ̎���A�ǂ̌��ꕶ�����̂ЂƂтƂɂ����Ă��A����̌��ꐸ�_�Ɋ�Â��Ȃ����̂͂Ȃ��ł��낤�B�܂��āA�Ȃɂ����킽���������̕��ɂ́A�l���C���ւ荂���Î�����u���������ʍ��̃��^�t�B�W�J�ƁA�t�B�W�J�v�̂Ƃ�ł��Ȃ��z���������Ă���̂��B�����ꐸ�_�����ɗR������ߑ㎩�R�Ȋw��A�l���Љ�Ȋw�͂��ׂāA�����������̗͊w�����o���A������x�_�ɂ������Ƃ��A�͂��߂Ă����ŁA�킽���������ɂƂ��Ă̗L�Ӗ������܂��A�����炵�����܂�Ă�����̂Ǝv����B���o�ɓ�����ׂ��a�́A�o�~�́A����傪���̂܂܂̂������Ŋ��������@�ł���A��̓I�ȍ��W�ł���B�����A�����ւ͂��炭�@�̎����Ƃ����œƎ�������|�����Ƃ����A�A�J�f���C�A�̊ɑ�ցA�킽������������{�Ƃ��ׂ��w�тȂ̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�@�@�u�a�́A�o�~�ɂ͂��炭���t�̖@���w����ҁA���̖�ɓ���ׂ��炸�v
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���i��������j�@���w������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
�@�@�@
�@�@�@�@�@
|
�v�v�v�̉ʂ��Ă�����Ƃ��閳����̒q�d��
.................................................................
�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@About us

�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
.................................................................
*��j�F���i��������j�ł́A�����ے�̑������Ȃ����Ǝ��̃G�C�h�X�Ƃ������ׂ��`���`�� �����̔ے�̎l�̕����ɉ����āu�s���E��ہE���ӁE�����v�ƌĂ�ł���B���������W�T�O���͂��߂Ƃ��邱��炷�ׂĂ̗p��͂����܂ō�Ɖ����ł��邱�Ƃ�f���Ă��������B�Ȃ��A�ʔ������Ƃɕ����s�\�őΏۉ������ނ��̂�������ȑ㕨�̉�Ƃ́A�O�N�O���炷���߂Ă������[�}���\�z�̏ؖ���ƂƉߒ����قڏd�Ȃ��Ă���B������\�ۂ��\�ɂ��钊�ۓI�v���b�g�t�H�[���̗L�����L�[���[�h�ɂ����Ƃ����҂̌��ꔟ���͂Ƃ��ɕ\���̊W�Ɉʒu���邩��ł���B
*��j�ꑰ�͔ނ�̌���K�͂ɂ�鎞��Ԃ̋��ł́A���ׂĂ̑��ݎ��������\�������W��ւƍČ����A�����ŕ�����Ώۉ�����ȊO�Ɏv�l�̕��@��m��Ȃ��B���̍s����������̂ЂƂ��w�[�Q���u���_���ۊw�v���B���̓`���I�ϔO�_�̘g�g�݂͂��̂܂܃t�H�C�G���o�b�n���o�āA�p���o���_�����B���_�̃}���N�X�ցA����́u�U�f�҂̓��L�v�̃L���P�S�[������n�C�f�b�K�[�̃h�C�c���}���e�B�V�Y���̌n���։�A���Ȃ���p������Ă������B�������A���̌�̂ǂ�ȃ��A���Y���̍����f����@�┽�|�p�A���ە\����`�O�q�^�������̊ϔO�_�̘g�g�ݎ��̂��ɂ͎���Ȃ������B���܂̔Đ��E�I�Ƃ������鎩�R�E�Љ�Ȋw�̊�{�g�����ǂ͂��̌Ñ�M���V���ȗ��̃R�X���X�ϔO�_�ō\������Ă����B
*�O�j���t���������[�b�^�X�g�[���ɂ��āA�Ì��̌���֕�������B
�Ì��̐��_�����Ƃ�������藣����Ă��܂������̂��錻��̂킽���������ɂ����āA�ꎚ�ꉹ�̕������̌ÕM��铂��T�O�_���Ō������āu���v�Ƃ��Č��A���̏�Ő^�����肪����ɂ��̉��̌�����q�˂Ă������Ƃ��ł���A�h�u���́v�͂��Ȃ킿�u���Ɓv�ł���Ƃ����Ì��̒n���h�֒��ɍ~�藧�Ă邱�ƂɂȂ�B���̂Ƃ��A������p�́u���̔h�v�́u���v�̍�i�́A��j�̑����ꕶ�̔g�������ꎮ�⒆���̉Ή����̊�Ɠ��l�ɁA���̖{�`��`�ʂ③�`�I�ȍČ����ɒu�����A�u���v�Ƃ��āu���v�̂͂��炫���̋�̓I�菇�ɒ��ڂ��Đ������u���́v�ł��邱�ƁA�����Ă܂��u���㕑���v�̐U��̎p�����A��͂�u���Ƃ��Ă̐g�v�̂͂��炫���ɂ��̒��ړ_�Ǝ菇�̂��ׂĂ��݂邱�ƂɋC�t�����ƂɂȂ邾�낤�B����͂܂蕽�����ꎚ�ꎚ�́u���v�Ƃ��Ă̕M铂₻���Ԃ̊֘A���ł���A��铂̓W�J�̂���l���A�͂邩��j�̓ꕶ��̐���`���ƌĉ����A�����ĘA�́A�A�o�A����Ɍ�����p�̐�����@�܂ł�����т���u���v�̂͂��炫�̂��Ƃɐ��������̂ł���A����͈�̏���Ȕr�Ƃ��āA��q��Z�����铝���`�����̂��̂ł���A�������N�_�Ɂu���v�̔×����p�N���Ă���Ƃ��ӈ�_�ŁA���ׂĂ͗�O���Ȃ������ɓ������Ă��邱�ƂɋC�t�����Ƃł�����B
�@ �Ì��͍P�Ȃ錻����܂��ɑO�q�Ƃ��Ċ��������Ă��関���̊፷���ł���B
�@ �I�єV�͕��������Í��W�Ɠy�����L�Ő����A�����������A�����̍�Ƃ͗Ǝ��̕��@�ɑ����āA��������ƕ��i���E��铁j�ɂ킽��A�G�Ȃ��V�X�e���A�b�v����Ƃ�����厖�Ƃł������B���Ȃ킿����͕������̂��ꂼ��ꎚ��铂́i�ÕM�j��铂�����u���v�̃A���S���Y���Ƃ��Đ����������A���̎l�\��铂ɂ����{��v���O���������������Ƃł������̂��B
�@ �Ƃ���ŁA��������؎����Ă������j�ɂЂ��Â��A���̗R���������ĕ������̖{���Ƃ��Ă��܂����Ƃ��������A����ł͊̐S�ȕ������̖{�`�������Ƃ��Ă��܂����ƂɂȂ�B�]������w�̕����T�O�ɂ͎��p�����݂��Ă���̂ł���B���̂ЂƂ͕������̂��̈ꎚ��铂̏�铂ŏ����ꂽ�����́A���������ł��銿���̂悤�ȊO�E�������ے��������\�ӕ����łȂ��̂͂������̂��ƁB������Ƃ����āA����������Ă����ĒP���ɃA���t�@�x�b�g�̂悤�ȕ\�������ɂ������̂ł��Ȃ��Ƃ����_�ɂ���B�������͂��ꎩ�g�͈Ӗ������Ȃ��B������������Ƃ����ĈӖ��T�O���\������P�ʋL���ł���Ƃ������Ȃ��̂ł����B
�@�@ �i�������́u���v���u���v�Ƃ��Ă���݂�����悭�ώ@����A�������������\�ӕ����ł��Ȃ��\�������ł��Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ��Ă��邪�A�����œ����ɉ��`���⌾����̐��̂������ł��邱�Ƃ����炩�Ƃ�����B
- �o�[�W����5.01�ŏڍ� - ���̗ɂ�����u���v��u���v�͂��ꎩ�g�����ꎩ�̂̑��݂ł���ȊO�A�Ȃ��̈Ӗ����\�ۂ��ێ����Ă��Ȃ��B�������Đ^���Ɉ���Ă����\�ۂ�Ӗ��_���Ƃ������Ґ��̎c���O�ꂵ�Ė������悤�Ƃ��Ă͂��炭�B��j����L�j����т��Ă����u���v�̕K�R�Ƃ��āA���̗��j�I�ǖʂŋ�̉��������̂��������ł���B����Ȍ��╨�ɗ삪�h��Ƃ������l�����̓A�j�~�Y���ł���A����͓V���A���A�א��̌��̓V�X�e�����v�����鉼�\���ꂽ�ʑ����O�E�ƑΉ������Ă������ʁA�u���v�Ɓu���v�Ƃ̕���v�l���K�R�����u�s�K�Ȃ�ӎ��v�B���̕���ӎ��̋��ɂ������a�ȊϔO�ւ̑f�p�ȐM�ɂ����Ȃ��j
�@ �������͉��W�����̂悤�ɊT�O�_�����\������L���Ƃ��Ă̈�P�ʂł͂Ȃ��B�������͂܂������ǂ̕��������ɂ����ނł��Ȃ��u���v���u���v�Ƃ��Ă̓��قȂ镶���̌n�������������ł���B�嗤�n�̊e�핶���̂悤�ɕ\���`�ʂ��邽�߂̃c�[���Ƃ��Ă̕����ł͂Ȃ��B���܂܂Ő��E�����̖{�����������Ă��Ȃ���������w��Ŗ����ށA�������̕����Ƃ��ĕ\�ӁA�\�����Â�ɂ������Ȃ���O�̕����Ȃ̂ł���B����͌�����p�u���̔h�v�̍�i���]���̂ǂ�ȑ��`���_�������E�������p�����̑�O���p�ł��鎖�ԂƓ����ł���A���̑�\��Ƃł��鐛�́u���v�̍�i�Ɠ��ʑ��ɂ�����G�C�h�X�i�`���j�Ƃ��āA�u���v���u���v�����ꂽ���ʂɐ��������Ԍ���Ƃ��Ă̕����Ȃ̂ł���B���_����肷��ƁA���E�̓��ƊO�Ƃ̋��E�ł���A�\�Ɨ��Ƃ�Ԃ��Ƃ��̐܂�ڂ��������ł���B���̈�ɂ��ď���ȌÕM��铂݂̍�l���F���i��������j�͌`�����邢�͊O�k�Ƃ����Ă����B�i�ڍׂ�
�F���o�[�W����5.01�Łj�^�������[�b�^�X�g�[���Ƃ��Ă����̂܂�l�\���̃A���S���Y����input��output���t�Ɍ��Ă����A�̐�j����̌����ƈӖ��̑S�Ă��A�܂����̗��ꐸ�_�Ɋ�Â��S�Ă̊�����]���Ƃ���Ȃ��A�������G�Ȃ�����߂邱�Ƃ��ł���B�^�������[�b�^�X�g�[���Ƃ����Ƃ��̌ÕM�������́u���v�Ƃ��Ă̏�铂͂���ȃ^�C���g���l���ł���A�����m��ꂴ�邵�����A�Ȃ������������������ԌÌ��́u���v�̔×����錴��ւƗU���Ă���Ă���̂ł���B
���j�������FXP���r�X�^�B�P�S���P�V�C���`�BExplorer
5.5�ȍ~�B�Ȃ��A�o�C�I�ȂLjꕔ���i��}�b�N�ŁA�c�������C�A�E�g���@�\�s�B
�@
���j�I���W�i���ȊO�́A���ׂẴR���e���c�́A�C����Ԃ�T�������F���i��������j���A���w�����p�ɁA��f�[�^���c�����\�L�ϊ��������̂ł���B���e�Ɉ�؎�͉����ĂȂ��A�{���ɒ��ڊW�̂Ȃ�
�O���ȂǁA������A���������ӏ�������B����ĕ��w�����Ƃ��Ă̐��m�x�� ���߂�����́A ������ׂ���啶�w�f�[�^�֒��ړ����邱�Ƃ����E�߂������B